知らない間に操られる!? 世界の歴史から学ぶ「たのしいプロパガンダ」の構造

- 『たのしいプロパガンダ (イースト新書Q)』
- 辻田真佐憲
- イースト・プレス
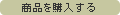
- >> Amazon.co.jp
- >> HMV&BOOKS
現代において"プロパガンダ"と聞くと、なにやら物騒な印象を抱く人もいるだろう。かつてのナチ・ドイツをはじめ、戦時中に政治的な意図をもっておこなわれた熱狂的な宣伝活動のイメージは、いまだ広く根付いていると言える。
一見すると怖い印象がつきまとう"プロパガンダ"だが、過去には人々の「楽しい」という感情に結びつけるソフトな方法での政治的宣伝も、世界中で数多くおこなわれてきた。今回紹介する書籍『たのしいプロパガンダ』(イースト・プレス)を読むと、巧みなプロパガンダの歴史を垣間見ることができる。
本書の著者である辻田真佐憲氏は、近現代史研究者として政治と文化・娯楽の関係性をテーマに執筆活動を続ける人物だ。そんな辻田氏によると、政治的な意図で群衆を扇動するには「楽しいプロパガンダ」こそもっとも効果的だと語る。
「銃で脅しながら宣伝しても、民衆を心の底から服従させることなどできはしない。だが、質の高いエンタメ作品に政治的なメッセージを紛れ込ませ、ソフトに宣伝したとしたらどうだろう。民衆はそのエンタメを楽しんでいるうちに、抵抗することすらできず、知らず知らずのうちに影響され、特定の方向へと誘導されてしまうかもしれない」(本書より)
実際に日中戦争がおこなわれていた当時、陸軍省新聞班に所属していた清水盛明中佐が内閣情報部主催の講習会で、「宣伝は強制的なものではなく、楽しみながら自然に啓発されるものでなくてはならない」といった旨を発言。さらに清水中佐は、音楽・映画・演劇をはじめ、さまざまな文化的要素がプロパガンダに利用できるという点まで事細かに指摘していた。
具体的な「楽しいプロパガンダ」の一例として挙げられるのが、当時夫婦のお笑いコンビとして活躍していたミスワカナ氏と玉松一郎氏のプロパガンダ漫才だ。実際に戦地に赴いて披露された漫才の中で、2人は次のようなやりとりを披露する。
ミスワカナ「[戦地では]女の姿なんてものは絶対見られないですもの。」
玉松一郎「女なんて全然をりませんよ。」
ミ「支那の美人はみな逃げてますしね。残つてる女いふたら、下駄の裏みたいなのばつかりやから。」
玉「また、ものすごい顔ですな。」[...]
ミ「その思ひがけない戦場へ、半年ぶりでこんな日本の掘り出しモンが行つたさかい......。」
玉「誰が掘り出しモンですか。」
ミ「あたしアカンわ、謙遜するタチやから。」
玉「厚かましいな、自慢してるんでせう、それは」(本書より)
内容としては、自分のことを「美人」だと言うミスワカナ氏に玉松氏が「厚かましい」とツッコミを入れるというもの。
「このような女性芸人の『ボケ』は今日でもありふれたものだろう。そこにさり気なく戦争の話を混ぜているところが、プロパガンダとして巧みだということになる」(本書より)
このようなエンタメを活用したプロパガンダが展開されたのは、他の国でも同様。例えば第二次世界大戦時には、現・ウォルトディズニーカンパニーとして知られる、かつてのウォルトディズニープロダクションや、ワーナーブラザーススタジオもプロパガンダ作品の制作に協力していた過去がある。
なかでも代表的な作品が、1943年制作のディズニーアニメ「総統の顔」だ。作中では、ドナルドダックがナチ・ドイツを連想させる"狂気の国"で暮らしている様子が描かれる。肖像画に向かって「ハイル・ヒトラー!」と何度も叫ぶ姿を滑稽に描いたり、主題歌の歌詞にわざとドイツ語らしき発音を取り入れたりと、ナチ・ドイツを嘲笑うような演出が多いのも特徴だ。
「鮮やかなカラーフィルムといい、今日でも飽きさせない構成といい、この映画は米国の国力を物語ってあまりある。当時『心理戦争』と呼ばれた、米国のプロパガンダの戦いを象徴する作品といえよう」(本書より)
現代においてもプロパガンダ大国というイメージの強い国としては、北朝鮮が挙げられるだろう。その北朝鮮に第二代最高指導者として君臨した金正日氏もまた、映画や音楽といったエンタメを利用しプロパガンダをおこなってきた。
例えば1970年前後には、映画制作の現場に関与。父である金日成氏が創作したという抗日武装闘争がテーマの戯曲をもとに、映像作品を複数プロデュースしている。
「北朝鮮ではこうした金日成の創作物を『不朽の古典的名作』と呼ぶが、金正日はこれをあえて映画化することで、映画をプロパガンダの道具として有効活用するとともに、金日成の個人崇拝を進め、その歓心を買ったのである」(本書より)
「楽しさ」を重視して展開されてきた過去をもつ、各国のプロパガンダ手法。これまでの歴史から、キャッチーで拡散力のあるコンテンツは政治的にも利用されやすいことが実感できるだろう。本書を手に取れば、知らず知らずのうちに民衆へ影響を与える「楽しいプロパガンダ」の構造に気付けるようになるかもしれない。











