過保護な社会が「脆弱な若者」を生む? アメリカの大学で進む【安全イズム】の蔓延

- 『傷つきやすいアメリカの大学生たち: 大学と若者をダメにする「善意」と「誤った信念」の正体』
- ジョナサン・ハイト,グレッグ・ルキアノフ,西川 由紀子
- 草思社
- 3,080円(税込)
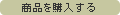
- >> Amazon.co.jp
- >> HMV&BOOKS
子どもを守りたい――そう願うのは親の本能だ。ケガをしないように、悲しい思いをしないようにと、つい手を差し伸べてしまう。しかしその"善意"が、いつしか子どもたちの成長を妨げているとしたらどうだろう。
そんな逆説に光を当てたのが、グレッグ・ルキアノフ氏とジョナサン・ハイト氏による著書『傷つきやすいアメリカの大学生たち:大学と若者をダメにする「善意」と「誤った信念」の正体』(草思社)だ。本書は、アメリカの大学で実際に起きている現象を通して、現代社会に潜む"過保護な優しさ"の落とし穴を鋭く描き出している。
本書の核となるのが、家庭や教育現場に蔓延する3つの「大いなるエセ真理」だ。ひとつは「困難な経験は人を弱くする」という脆弱性の思考。ふたつ目は「常に自分の感情を信じよ」という感情至上主義。そして3つ目が「人生は善人と悪人の闘いである」という二極化した世界観だ。
どれも一見、子どもたちを守るための優しい教えのように聞こえる。しかし実際には、若者の精神的な耐性を奪い、対話や葛藤を避ける傾向を強めてしまうのだ。
アメリカの大学現場では、教授や講演者の言葉尻をとらえて糾弾し、「不快だから」という理由で講演をキャンセルさせる学生運動が相次いでいるという。著者たちはこのような現象を「安全イズム」と呼び、次のように定義している。
「『安全イズム』とは、安全であることが強烈な価値を持つ文化や信念体系を指し、そうなると、人々は他の現実的かつ道徳的な問題による必要があっても、安全について妥協することをしなくなる」(本書より)
「安全であること」が絶対的善とされると、人は挑戦を避け、異なる考えに触れることすら"危険"とみなしてしまう。結果として、学問の多様性も奪われてしまうのだ。
さらに、SNSの普及も若者たちに大きな影響を与えているという。本書によれば、アメリカではZ世代と呼ばれる10代の若者の間で、うつ病や不安症などの精神疾患が増加傾向にある。著者たちは、これは研究途上のテーマであり、さらなる検証が必要だと前置きしたうえで、スマートフォンや電子デバイスの使用も一因ではないかと指摘している。
興味深いのは、対面での人間関係に多くの時間を費やす若者よりも、SNS中心の生活を送る若者のほうが、心の健康に悪影響を受けやすいという点だ。著者たちはSNSそのものを否定しているわけではない。むしろ、日常的に否応なく目にする些細なストレスにどう向き合うかが重要だと説く。
「インターネットがある現代の子どもたちは、生活の端々でくだらないことに対処する必要がある。自分の感情的な反応に気がつき、うまく操り、適切な反応を選べるようになることが肝要だ」(本書より)
ここで注目したいのは、人類にとって快適さや安全性は非常に有難いものである一方、そこには代償があるということだ。快適さが増した環境に適応するにつれ、我慢できないと感じる不快感や危険とみなす基準が徐々に下がっていく。
アメリカでは、いわゆる「ヘリコプターペアレント」が子どもを四六時中監視し、過保護に守ろうとする傾向が強まっている。誘拐や事故などのリスクを過度に恐れ、子どもから目を離さない。法律や社会規範も、大人の監視なしで子どもだけで過ごすことを難しくしている。もちろん危険な場面で見守る必要はあるが、子どもが自ら判断し挑戦できる時間も不可欠だ。日本でも同様の傾向がみられるだろう。
著者たちは、子どもはもともと反脆弱性を備えており、過保護にされると軟弱でたくましさにかけた大人になっていくと警鐘を鳴らす。
「子どもが自分でリスクを判断し、悔しさ、退屈さ、人との衝突に対処できるようになるには、体系化されていない、大人の監視なしの時間を過ごすことが必要で、まずはその認識を持つことが大切だ」(本書より)
そこで重要になるのが、「自由遊び」だ。子どもは大人が思いつかないような遊びを考え、大人には無意味に思えるようなことにも熱中する。それが学びや成長に直結する。特に、屋外での自由遊びは重要で、子ども自身が判断し、工夫し、時には小さなリスクを負う経験もできる。
「遊びは、機能的に優れた大人をつくれと哺乳動物の脳にプログラミングする上で不可欠である」(本書より)
さらに本書では、心の健康に有効とされる認知行動療法の実践方法も紹介している。具体的な手法や考え方を知ることで、ストレスへの向き合い方や自らの感情を適切に調整するヒントが得られるだろう。本書はアメリカを舞台にしているが、日常生活や子育ての場面でも参考になる示唆が多く、「かわいい子には旅をさせよ」という言葉の重みを再認識させられる一冊だ。











