大阪人も知らない「大阪のなぞ」 都市研究の第一人者が語る"大阪イズム"
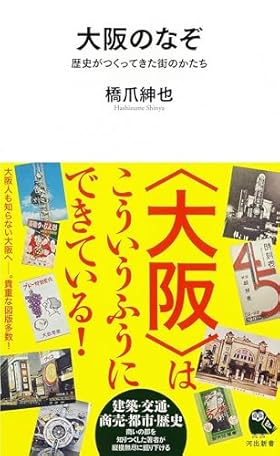
- 『大阪のなぞ: 歴史がつくってきた街のかたち (河出新書 088)』
- 橋爪 紳也
- 河出書房新社
- 990円(税込)
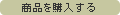
- >> Amazon.co.jp
- >> HMV&BOOKS
現在、大阪・関西万博が開催され、世界中から注目を集める大阪。かつては東京をしのぐ「大大阪」と呼ばれ、合理的な生活文化から「日本のアメリカ」とも称されました。その歴史は、大阪各地に残る文化遺産や繁栄の痕跡からもうかがえます。
『大阪のなぞ:歴史がつくってきた街のかたち』は、関西の都市政策や都市文化を研究してきた生粋の大阪人である橋爪紳也教授が、大阪にまつわる歴史の謎を建築・交通・デザインの視点から解説する一冊です。
たとえば、本書で取り上げられている謎のひとつが、昭和6年(1931年)に復興した大阪城天守閣。昭和初期としては最新の工法であった鉄骨鉄筋コンクリート造を採用し、徳川時代の石垣のうえに豊臣時代の天守の姿を創作するという画期的な都市施設は、いったい誰が思いついたのでしょうか。
通説では名市長の誉れの高い関 一によるものとされていますが、大阪市電気局および大阪市立美術館の嘱託として働いた上田令吉が発表した文章によると、都市計画部にいた「某」によるアイデアが関市長に進言され、採用されたというのが実情のようです。橋爪教授は「上田の回顧文にある最初の提案者である『某』の名前は、歴史に埋もれて、今は語られることはない」(本書より)と指摘します。
続いては、大阪初のカフェについて。大阪は喫茶店王国としても知られますが、その元祖となる店は、現・阪急宝塚線、箕面線の終点となる箕面駅にあったそうです。ここには「お伽倶楽部」なる童話を広める組織の活動拠点があり、その事務所であった洋館こそが大阪初の珈琲店「カフェー・パウリスタ」1号店だったといいます。
また、万博とは違う博覧会ネタとして知っておきたいのが「今里のエチオピア」。これまでに大阪で開催された博覧会には、公式報告書もないような小規模なものもあったのだそうです。昭和9年(1934年)に今里駅の南側一帯で開かれた「皇太子殿下御誕生記念 非常時国防博覧会」では、5万坪の会場に本館、陸軍館、海軍館、射撃場、遊園地などが特設されました。その中でもユニークな存在だったのがエチオピア館。当時、日本と友好的な関係だったことから「親エチオピア」と称すべき雰囲気が大阪にあったことは、知らない人も多いのではないでしょうか。
ほかにも「難波橋筋に難波橋はない」「豊中の曽根は『美食文化』の中心であった」「元祖ビリケンを探せ」「グリコより福助足袋が早かった」「大阪に世界一のプールがあった」など、大阪を熟知する橋爪氏ならではの知見が、絵はがきやパンフレットなど自身の膨大なコレクションとともに記されています。「大阪人も知らない大阪のなぞ」について網羅されている本書。大阪の生活文化や合理精神が育んだ"大阪イズム"に、ぜひ触れてみてください。
[文・鷺ノ宮やよい]











