地震も台風も怖くない! 古代日本建築に宿る"超高度な技術と智慧"とは?

- 『古代日本の超技術〈新装改訂版〉 あっと驚く「古の匠」の智慧 (ブルーバックス B 2249)』
- 志村 史夫
- 講談社
- 1,210円(税込)
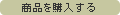
- >> Amazon.co.jp
- >> HMV&BOOKS
古い時代に建立された神社仏閣や大仏を見て、「一体どうやって作ったの?」と疑問に思った経験はあるだろうか。現代まで遺されている歴史的建造物の構造を紐解くと、まだ"ハイテク"と呼ばれるような技術がなかった時代のものづくりを垣間見ることができる。「当時の日本人たちはどんな技術を用いていたのか知りたい」という人にぜひ手に取ってほしいのが、今回紹介する書籍『古代日本の超技術〈新装改訂版〉 あっと驚く「古の匠」の智慧』(講談社)だ。
本書の著者である志村史夫氏は、これまで日本やアメリカで半導体結晶などを研究してきた工学博士。近年は古代文明、基礎物理学といったさまざまな分野に注目していて、教科書や専門書、一般向け書籍など多くの著書がある。
"古代の技術"が垣間見える建造物として志村氏が本書で挙げているもののうち、特に有名なのが「五重塔」をはじめとする日本古来の木塔だ。彼いわく、古くから地震大国だった日本において、日本の木塔が地震で倒れたことはほとんどないという。
「暴風で倒壊した例もなく、木塔の崩壊は、火災による焼失がほとんどなのである」(本書より)
高層建造物である日本古来の木塔は、なぜ強い揺れや風にも耐えられるのか。その理由のひとつが、"心柱"の存在である。
心柱とは、塔の中心に通された1本の太い柱のこと。五重塔をはじめとする日本の多重塔で多く用いられている構造だ。
「五重塔の中心を貫く"大黒柱"が心柱である。事実、五重塔建造の木材の中で、最も念入りに選ばれ、加工され、そして最も太いのが心柱である」(本書より)
心柱の大きな特徴は、塔の各層と柱そのものが分離されているという点だ。そのため地震などで塔が大きく揺れた際も、心柱と建物は別々の動きをすることになる。
「つまり、振動周期の違いによって共振することなく、揺れる力を緩和し、分散させているのである」(本書より)
心柱には、基盤の上に柱を固定する「貫通型」や、塔の内部で柱を宙吊りにする「懸垂型」などの種類がある。貫通型であれば観音開き扉の閂(かんぬき)のような効果を、懸垂型なら振り子のような効果をそれぞれ発揮することで、塔全体の耐震性能を上げているのだ。なかでも貫通型の心柱はもっとも耐震性が高いとされ、現代では東京スカイツリーの制振構造にも応用されている。
また日本古来の木塔においては、各層同士を固定しない"キャップ構造"が用いられているケースも多い。キャップ構造とは、帽子あるいは鉛筆のキャップを縦に重ねたような建物構造のこと。建物全体が完全にはつながっていないため、地震の横揺れが塔上部に伝わりにくくなっているのだ。
日本古来の優れた技術が活かされているのは、決して巨大な建物構造だけではない。古くから日本の木造建築に使われてきた"古代瓦"にも、伝統的な技術が詰まっている。
現代において使われている瓦と古代瓦の大きな違いは、内部の気孔率および吸収率の高さにある。
「古代瓦は、全体積のおよそ三〇パーセントが"気孔"なのだ。その気孔率は、現代瓦の二倍にも達する。その結果、吸収率も大きく異なることになる。
古代瓦は、たとえ室内に置いておいても水分を吸収し、天気になれば吸収した水分を外へ放出する。
これが、瓦の"呼吸"である。つまり、昔の瓦は雨水は流すが、水蒸気は吸収し、天気がよくなればそれを外部へ放出する『湿度調整機能』を備えているわけだ」(本書より)
高温多湿になりやすい日本で、湿度から木造建築物を守るのに適している古代瓦。機能面では現代瓦よりも優れているように見えるが、生産効率や同規格での量産のしやすさという点では、現代瓦に軍配が上がる。
現代社会では、生産性、経済性、規格化といった価値観が重視されがちだ。そしてどれだけ高い技術であっても、社会の要求に応えられなければやがて失われていくことになる。
「取り返しがつかないことに、日本古来の智慧や技術を伝える職人が、明治以降、とりわけ『戦後』、急激な勢いで消えていっている。職人が消えつつあり、彼ら職人の仕事に敬意が払われなくなったのは、近代工業によって推進された"質より量"、"経済効率最優先"の価値観と不可分であろう」(本書より)
最先端の技術だけが優れているとは限らない。さまざまな最新のテクノロジーが活用されている現代だからこそ、本書を通じて古代日本の技術をあらためて振り返ってみてはいかがだろうか。











