日本にしか存在しない「麹菌」も 農学博士が語る【発酵】の奥深さ
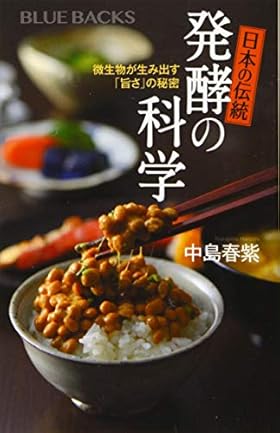
- 『日本の伝統 発酵の科学 微生物が生み出す「旨さ」の秘密 (ブルーバックス 2044)』
- 中島 春紫
- 講談社
- 1,100円(税込)
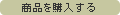
- >> Amazon.co.jp
- >> HMV&BOOKS
日本では、納豆、味噌、醤油など、発酵の力を使った食材や調味料が広く親しまれている。私たちにとって身近な存在である発酵食品は、どのような仕組みで生まれているのだろうか。"発酵"という文化を科学的な視点から解説したのが、今回紹介する書籍『日本の伝統 発酵の科学 微生物が生み出す「旨さ」の秘密』(講談社)だ。
本書の著者・中島春紫氏は、大学の農学部で教授を務める農学博士。専門分野は応用微生物学で、麹菌にまつわる研究を行ってきた。中島氏によると、学術的な文脈での"発酵"とは、「微生物が有機物を嫌気的に分解してエネルギーを得る反応」と定義されるという。
「『嫌気的』とは酸素を使わないという意味であり、『有機物』とは炭素を含む化合物であるから、『発酵』は酸素を使わずに炭水化物などの有機物を分解してエネルギーを得る反応のことである」(本書より)
例えば乳酸菌やアルコール発酵に用いられる酵母などは、酸素を使わずに生きられる嫌気性の微生物だ。ところが文脈が変われば、"発酵"の定義も変化する。なかには酸素を必要とする微生物が、発酵の過程で利用されるケースもあると中島氏は言う。
「生育に酸素を必要とする微生物を好気性菌という。納豆を造る納豆菌や、食酢の製造に用いられる酢酸菌、味噌・醤油の醸造に用いられる麹菌などは好気性菌である」(本書より)
それぞれの特性を生かし、さまざまな食品の発酵に利用されてきた微生物。多くの種類がある中で、中島氏が日本の食文化に大きく関連していると考えるのが麹菌だ。
麹菌とは、前述した醤油や味噌に加え、日本酒、みりんなどの製造過程にも用いられるカビの一種。なかでも事実上日本にしか存在しないと言われている麹菌が、アスペルギルス・オリゼー(黄麹菌)である。
2005年に完了した麹菌のゲノム解析結果によると、アスペルギルス・オリゼーは人間に有害なカビ毒を生産できなくなっていることが判明。その他の特徴も含め、発酵に利用するうえで都合の良い性質を持つことがわかっている。
このような麹菌が、いったいなぜ日本でのみ利用されているのか。その理由について中島氏は、日本人が長い時間をかけて発酵に向いた麹菌の株を選抜し、育ててきたからだと考える。蒸した米に唾液を含ませて発酵させる「口噛み酒」をはじめ、「米麹」の誕生、酒造家にカビを卸す「種麹屋」の出現などにより、発酵食品作りに向いた麹菌が独自に流通していったのだ。
「一般の教科書では、微生物の純粋培養はドイツの細菌学者ロベルト・コッホが1870年代に寒天培地を用いた培養法を考案したのが元祖とされているが、14世紀の日本で麹菌の事実上の純粋培養と商業化が達成されていたことは特筆に値する」(本書より)
なお、発酵食品の特徴のひとつとして挙げられるのが"旨味"だろう。この旨味は、発酵過程で微生物がタンパク質を分解する際に生まれるアミノ酸の混合物によるもの。一般的にタンパク質自体には味がないが、発酵という工程を経ることで食品としてのおいしさが引き出されるのだ。
また発酵には、食材の栄養吸収を助ける働きもある。例えば日本の食品にも多く使われる大豆は、消化に時間がかかりやすい固いタンパク質を持っているのが特徴。さらに繊維質も分解しにくい構造なため、そのまま火を通しても効率的に栄養を吸収することが難しい。
そこで日本では、古来からさまざまな工夫を凝らして大豆を食してきた。その工夫のひとつが、発酵技術を用いた食品作りだ。
「大豆を煮たものに納豆菌を繁殖させたものが納豆である。大豆のタンパク質の一部を納豆菌が分解しているので、食べた人の消化が楽になっている。さらに、大豆に麹菌と耐塩性の微生物を作用させてタンパク質をじっくりと分解したものが、味噌であり醤油である。醤油では大豆のタンパク質がほぼ完全に分解されてアミノ酸になっている」(本書より)
そのままでは分解するのが難しいタンパク質を、消化吸収しやすい形に変えられるのも、"発酵"が私たちの食にもたらすメリットだと言えるだろう。
日本人の暮らしに欠かせない数々の発酵食品。食材自体の良さを引き出した料理が特徴的な"和食"においては、日本独自の発酵食品であるさまざまな調味料が大きな役割を果たすと中島氏は語る。先人たちの知恵や工夫から生まれ、伝統として受け継がれてきた奥深い発酵の世界。本書を通じて、ぜひ覗いてみてはいかがだろうか。











