人生の本番で役に立つ教育とは? 学術論文で明らかになった信頼性の高い"教育効果"

- 『科学的根拠(エビデンス)で子育て 教育経済学の最前線』
- 中室牧子
- ダイヤモンド社
- 1,980円(税込)
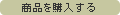
- >> Amazon.co.jp
- >> HMV&BOOKS
子どもを持つ親であれば、「将来につながる教育とは何か」を一度は考えるのではないでしょうか。しかし、世の中には情報があふれており、どこに信頼を置くべきか迷うことも多いものです。そこで今回取り上げるのは、中室牧子氏による『科学的根拠(エビデンス)で子育て 教育経済学の最前線』という一冊。本書では、教育経済学の研究成果の中から、国際的な学術雑誌に掲載された信頼性の高いエビデンスだけを厳選し、わかりやすく解説しています。
近年、教育効果の研究は飛躍的に進み、「子どもの頃のある地点で受けた教育が、大人になってからの就職、収入、昇進、結婚、健康、そして幸福感などに与える影響を明らかにすることができる」(本書より)ようになってきました。本書が注目するのは、幼少期や学生時代の"短期的な成果"ではなく、社会に出てからの「人生の本番で役に立つ教育とは何か」という視点です。
たとえば、「第1志望のビリ」と「第2志望のトップ」では、その後の人生でどちらが有利に働くのでしょうか? 「少しでも偏差値の高い学校に行ってほしい」「優れた友人から受ける影響は『良い』影響に違いない」との思いから、前者を選ぶ人も少なくないでしょう。しかし、アメリカ・フロリダ州の公立小中学校のデータを分析した結果、「優れた友人から良い影響を受けるのは、もともと学力が高い児童・生徒だけ」ということが明らかになりました。また、第1志望校にギリギリで合格したAさんと、同じ学校を惜しくも不合格となり第2志望の学校に進学したBさんとを比べた場合、学力は同程度でも、その後の成績や進学で有利になるのはBさんであるという結果も報告されています。
中室氏は、「たとえ運良く実力より上の志望校に滑り込み合格を果たしたとしても、学内やクラス内の順位が低くなれば、長い目で見ればよい結果をもたらさない可能性もあります」(本書より)と指摘。偏差値だけで判断するのではなく、「それぞれの子どもに合った学校かどうかを考えること」(本書より)が重要なようです。
ほかにも同書では、「将来の収入を上げるために、子どもの頃にやっておくべきことベスト3」「非認知能力はどうしたら伸ばせるのか?」「勉強できない子をできる子に変えるには?」「別学と共学、どちらが有利なのか?」といったテーマを取り上げています。信頼できるデータに基づき、子育てや教育について考えたい人にとって、大きな助けとなる一冊です。
[文・鷺ノ宮やよい]











