責任逃れの常套句や隠語を使った駆け引き......言葉と責任の関係について言語哲学者が解説

- 『誤解を招いたとしたら申し訳ない 政治の言葉/言葉の政治 (講談社選書メチエ 821)』
- 藤川 直也
- 講談社
- 2,420円(税込)
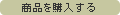
- >> Amazon.co.jp
- >> HMV&BOOKS
世の中には「発言には責任が伴う」ことが往々にしてあります。いったん言葉に出したら、それは実行しなくてはならない、守らなくてはいけないと考える人が多いのではないでしょうか。たとえば「明日には金を返す」と約束したなら、翌日にお金を返さなくてはならない。けれど、「今は手持ちがないんだけど、明日には間違いなくまとまった金が入るんだ」と言われて翌日になってもお金が返されなかった場合、果たして相手を非難することはできるでしょうか。
他にも、言質を与えない、責任を伴わない言い方はいろいろとあります。「『そんなつもりはなかった』や『誤解を招いたとしたら申し訳ない』という言い逃れの常套句、『まだちょっと時間あるし、うちでネットフリックスでも見ない?』などの言外の意味や隠語を使った駆け引き、『広く募ってはいたが募集はしていない』のような意味を捻じ曲げる試み、果ては『これはオフレコだけど......』といったあからさまな責任回避など」(同書より)。そうした「意味の表と裏はどう決まるのか」という問題について考察したのが、言語哲学者の藤川直也氏が著した『誤解を招いたとしたら申し訳ない 政治の言葉/言葉の政治』です。
同書で扱う「意味の表と裏の揺らぎ」は主に大きく二つに区別できるといいます。ひとつは「否認可能性の揺らぎ」によるものです。著者はその具体例として、ジャーナリストの伊藤詩織氏が衆議院議員の杉田水脈氏を訴えた訴訟における「いいね」の否認の問題を挙げます。ある人物を中傷するツイートに「いいね」しながら、「『いいね』が中傷的内容への好感の表明である証拠にはならない」と否認することは通用するものなのでしょうか。一審と二審での判断が違ったことを見ると、「誤解の余地としての否認可能性の有無は、状況に応じて変わりうる」(同書より)と言えるでしょう。「発言にどんな責任が伴うのかを否認可能性に基づいて判断するとき、私たちには、複数の異なる種類の否認可能性が選択肢として与えられている。そのうちどれを使うのかに伴い、意味の裏表は揺れ動くのである」(同書より)と著者は説明しています。また、「イチジクの葉」や「犬笛」といった異なる言質回避の術を紹介しながら、意味の否認可能性には多様性があることも述べています。
そしてもうひとつ、意味の表と裏の境界が揺らぐ要因となるのが「意味と力の揺らぎ」です。最終章となる14章では、政治家の言い逃れの常套句「誤解を招いたとしたら申し訳ない」を例に出し、これの何がまずいのかを8つのパターンを挙げながら論じたうえで、「主張や命令、約束といった発言の力もまた一定不変ではなく、変化し揺らぎうる」(同書より)と説いています。
普段のコミュケーションの中で私たちが自然と使っている"言外に意味を含んだ言葉"を非常に論理的に解き明かしている同書。悪用の可能性もある中で、こうした言葉と私たちはどう向き合うのがよいのでしょうか。著者は「意味の表裏の揺らぎをなくすことはまず不可能だ」「意味の表と裏のゆらぎ・言質の不確かさは、それを悪用する人にコミュニケーションにおける責任逃れの余地を与える一方で、私たちのコミュニケーションを豊かなものにもする」(同書より)と言い、締めくくりでは悪用を牽制するための二つの視点を示唆しています。同書は、日ごろ言葉と責任の関係についてモヤモヤしたことがある人にとってはその真理を知ることができるとともに、より豊かなコミュニケーションを築いていくうえでの大きな参考になるのではないでしょうか。
[文・鷺ノ宮やよい]











