雑誌『tattva』編集長・花井優太インタビュー「辺境から『宙吊りの問い』を投げかけた10冊の雑誌」(前編)

- 『tattva Vol.10』
- tattva編集部
- ブートレグ
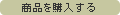
- >> Amazon.co.jp
- >> HMV&BOOKS
雑誌『tattva』の最新号、vol.10「わたしたちが普段言葉にする本物について」が2025年7月発売になりました。ビジネス、アート、テクノロジー、カルチャーなど、さまざまな切り口から多様な視点を取り上げてきた同誌は、「10年後の再始動」を掲げ、このvol.10でいったん活動を休止します。
そこで、2021年の創刊から約5年の歩みを編集長の花井優太さんと振り返ります。前編となる今回はポストコロナ時代を見据えて紙媒体を選んだ経緯について。聞き手は、読者でもあり、花井さんとも親交のあるアーティストの布施琳太郎さんです。
■自分たちが読みたいものを作る
布施:『tattva』 vol.10、面白かったです。知らない話もたくさんあって。読んでいて、雑誌を作ることは、すごく勉強にもなるだろうなと感じました。花井さん自身の意識としては、雑誌の編集はインプットの時間だったのか、それともアウトプットの時間だったのか、どちらの気持ちが強かったんでしょう?
花井:まず、『tattva』はとても恵まれた媒体であったと思っています。企画にあたっては、読者層よりも自分たちが知りたいことを調べる、という感覚でしたね。
最初にぼくが掘りたいテーマを編集部のみんなに投げかけます。
例えば今回の「わたしたちが普段言葉にする本物について」特集であれば、「〝本物〟ってよく言うよね」と。このテーマは普通に考えたら、フェイクニュースとかポストトゥルースの文脈で考えていくことになる。でも、それだけだと虚しい結論にしかならない。「結局、本物なんてないよね」「それぞれにとっての本物が乱立している時代だよね」という話になってしまうだけですから。
布施:例えば、「〝お袋の味〟なんて幻想だ」とか。
花井:そうそう。そういった指摘は重要なものだと思うけど、一方で自分をポジティブにしてくれる〝本物〟っていうのも必ずあるはずだと思うんですよ。
布施:花井さんが特集ステートメントで書いていた、「本物とは?」「俺が信じられるかどうかである」というやつですよね。
花井:あの態度は危険なものとしても書いているんだけど、でもたとえ幻想だとしても、自分の背中を押してくれるもの、それが〝本物〟なんだっていう思いも大切じゃないですか。今回の特集では、そういうことを言いたかったんです。
その上で個々の企画では、「人はどう物語を解釈するのか」とか「みんなが言っている普通の人生って何だろう?」とかっていうのを考えられると面白いよね、と編集部でディスカッションしながら作っていきました。まさに「読みたいものを作る」感覚です。
こういう作り方でバカみたいに売れるとは思っていないですよ。そんなおこがましいことは考えてない。でも、少なくとも自分たちは本読みだから、自分たちみたいな人は買ってくれるんじゃないか? という気持ちでは作っていました。
■辺境からの視点
布施:編集者には、世界や読者に期待をしていてほしいなと思うんです。みんなのコンプレックスとかネガティブな感情を刺激するような本の企画もたくさんありますけど、『tattva』は、そういうものではなくて、だから読んでいて爽やかだと感じました。
花井:うれしい感想です。ありがとう。
布施:あと、武邑光裕さんの巻頭連載で、「1980年代に当時はメインストリームの場所ではなかったクラブに通っていたことが、自分の活動の基礎を作っている」「辺境に触れることが創造性をもたらす」みたいなことが書かれていました。年齢を計算すると、今70代である武邑さんにとっての1980年代は20代から30代というタイミングなんです。花井さんが『tattva』を作り始めた年代と同じくらい。
ぼくはクラブも雑誌も人が集まる場所という意味では似ていると思います。だから、『tattva』という辺境を作ることで、コロナ後の社会について考えようとした花井さんを、辺境を探索することで活動のヒントを得てきた武邑さんと勝手に重ねてしまったんですけど、そういったことは意識していました?
花井:いや、すごくありがたい指摘だけど、あえて辺境を探索するみたいなことは考えてなかった。でも、そもそも自分はずっと業界の辺境にいるんですよ。
布施:それは何業界の、ですか?
花井:出版でも広告でも、結局は野良なんです。編集者としては出版社の出身ではなくてフリーランスだったし、広告代理店にはいたけど、他業種からバイトで入って中途入社なので王道のキャリアではない。だから永遠に、真ん中って感じじゃない。
布施:「真ん中に入りたいな」という気持ちは?
花井:うーん、もともと自然に好きになるものが周りからするとマニアックだったり、メジャーじゃないものが多かったりするからか、真ん中はおこがましい。『tattva』も、それこそ書店で面陳されるような、10年も20年も続いている雑誌の仲間入りをするぞと意気込んで作っていたわけではないですし。なんていうか......、まだ名前がないものを作りたいんです。価値が断定されていないものというかね。
「編集って何ですか?」と聞かれたら最近よく言っているんですけど、それは「Login to the Reality」だと。現代美術家の松田将英の作品の名前を引用しながら答えています。
つまり、現実にログインするための枠組みを作る。言い換えれば「複数の人が乗りたいと思う船を作る」のが編集なんじゃないかと思う。
そう考えたとき、おそらくあの時点(創刊時の2021年)では『tattva』みたいに小規模な雑誌っていうのは、書店にドカンと置かれて、青山ブックセンターにポスターが貼られるような扱いの媒体ではなかったはずなんです。でも、いざ出してみたらそうなったっていうのが面白くて。でも、それは「真ん中を狙いにいった」ということではないんです。ぼくらが作った船に、乗りたいと思ってくれた人がそれなりの数いて、実際に乗ってくれた。そういう印象です。
布施:さっきの武邑さんの話にしても、あの人は「辺境に行こう」という意識で生きてきたのではないですよね。「こっちのほうが面白いじゃん」をやっていたら、いざ振り返ったときにずっと辺境を探索していたと言っていて。きっと、花井さんもそうなんでしょうね。
花井:自分が面白いと思うもの、今回で言えば〝本物〟だなって思うものって、今後どうなるかわかんない、ヒリヒリするようなものなんかも含まれるんです。歴史や信頼があるものだけじゃなくてね。
布施:はいはい。
花井:価値がついてないものに対してドキドキするのが好きなんです。『tattva』も「世の中に宙吊りの問いを」と言って作ってきたんですけど、やっぱり、まだ答えが出てないものには謎の引力があって、そういうものはみんなで考えるためのプラットフォームになりうる。だから、ぼくは端っこにずっと興味があるのかもしれない。
■なぜ紙の雑誌だったか
布施:創刊は2021年ですよね。僕の印象だと、当時のコミュニケーションや言説は、コロナ禍も手伝ってSNSにどんどん巻き取られていった記憶があります。トークショーや刊行イベントもオンライン開催するのが当たり前になりました。でも、あれってめちゃくちゃ不思議な感覚で。
本当だったらこの場だけの裏話をしていたはずが、誰が聞いているかわからない環境でしゃべることになった結果、話す内容が変わった。ロフトプラスワンみたいなクローズドが売りだった場所ですらも、どこかでSNSの拡散を意識しながらしゃべるようになったと思うんです。
でも、そうやってあらゆる言説がSNSに影響される中、『tattva』の誌面には「みんなでオフラインの環境で考えるために本を出しているんです」という感触がすごくあって。それが今振り返ると、意外に新鮮でした。
花井:今の話に被せると、創刊当時の自分はまだ会社員で、先輩もいれば後輩もいて、組織の中で新人育成の話なんかは頻繁に交わされるわけですけど、リモートワークが導入されたことで「背中を見せる」のが不可能になったんですね。
布施:確かにそうですね。
花井:それってコンテクストがないまま仕事をするってことで。例えば、忙しそうにしている人が打ち合わせ中に怒っちゃったり、雑な言い方になっちゃったりしたことに対して、横で見ていれば「あの人忙しいからな」「寝てないしな」とか思ったりできるけど、Zoomのコミュニケーションだけだと、そういう想像がすごく難しくなって「あいつ何キレてんだよ」とかしか思わない。それが進むとチームがタスク処理の関係だけになってくるんですよ。
でも、本来のコミュニケーションって、そうじゃないよなと思っていました。コミュニケーションを単純化していくことで、大切な何かが抜け落ちてしまっているんじゃないか。そういう実感がありました。
だから、オフラインの雑誌という形式にこだわった。みんな同じものを手にするっていう再生環境の限定と身体性でつなぎとめたい何かがありました。それが2021年というタイミングでウェブ媒体を選ばなかった理由です。加えて、雑誌は時代とともに古くなって捨てられてしまうものだから、ずっと本棚に置いてもらえるように、書籍のような活字中心のフォーマットにしようと考えました。耐久性への挑戦ですね。
これは特集テーマの選び方にしてもそうです。一応、ぼくらも編集者だから、〝いま流行っているもの〟はわかっているわけです。このテーマにしたら、今だったらこういう読者がつくだろうってくらいの読みはできる。
2021年の創刊時で幅広い読者層を狙おうと思ったら、「サウナ」とか「コミュニティ」とか。実際、そういう雑誌特集も見かけたはずです。でも、『tattva』はそっちには行かない。〝いま流行っているもの〟は情報に接触した人の理解も早い。でもむしろ、コミュニケーションを遅くしたかったんです。
よく創刊時に言っていたのは、内容が難しくて実際は理解もできてないかもしれないけど、浅田彰の『構造と力』を本棚に入れていた時代があったよね、と。コミュニケーションが遅いものが日常にあったほうがいい。それがオシャレってなんかいいじゃないですか。そういうものになりたかったんです。
■「真ん中」を目指さない雑誌づくり
布施:今はまとまった長さの文章でひとつの価値観や考え方を示すための場所がすごく減っているわけですけど、それは雑誌が売れないことだけが理由ではなく、そもそも『tattva』のようにまとまりあるテーマで集まることを怖がっているようにも思えるんです。
「本物とは何か」というテーマよりも、例えば「21世紀のスラヴォイ・ジジェク」とかにして、専門家を並べたほうが特集は組みやすいです。誰も文句言わないし。そういう意味では「この内容だと怒られるかな?」と思うことはなかったですか? このテーマであの人がいないのはまずいよね、とか。
花井:そういうことは気にしてなかったかな。むしろ、「このテーマなら、この人を呼んだら盤石だよね」みたいな考え方では、みんな同じような内容になってしまう。それよりは「どうなるかわからないけど、こういうテーマでしゃべってもらったほうが、いい話をしてくれるんじゃないか」みたいな観点で企画を考えていた気がします。
布施:そうなると、花井さんは『tattva』をどう定義しているんでしょう? 活字中心の雑誌は大まかに文芸誌とビジネス誌に分けられますが、どちらのつもりで作っていた?
花井:総合誌ですね。文芸も思想もビジネスの話題もある。あえていうなら週刊誌っぽい作り方だと思います。企画の面白さがすべてというか。文芸誌、論壇誌は基本的に業界誌だと思うんですよ。だから並びを気にするのは仕方ない。でも、ぼくらはそうじゃないし、業界の真ん中の人たちとは違うことをやらないと意味がないと思っていました。
布施:なるほど。先ほど花井さんは「業界の真ん中にはいない」と言っていましたが、業界の辺境にいるからこそ、『tattva』という雑誌が作れたんだなということがわかりました。
花井:それはほんとに大きいですよね。いろんな偶然が重なって。よく10冊も作ったなって思います。
<プロフィール>
花井 優太
クリエイティブ・ディレクター/ 編集者。 エディトリアルをバックボーンに、情報戦略、コピーライティング、事業・商品コンセプト開発、PR、TVCMやミュージックビデオの映像企画、ブランドブック制作などを行う。2021年に雑誌『tattva』創刊、編集長。受賞歴に日経広告賞部門優秀賞、毎日広告デザイン賞準部門賞など。著書に『カルチュラル・コンピテンシー』(共著)がある。IG:@iamyutahanai
布施 琳太郎
アーティスト。iPhoneが発売されて以降の都市における「孤独」や「二人であること」をつくりだすために自主企画の展覧会を中心として、映像作品や絵画、インスタレーションの制作、詩や批評の執筆などを行っている。主な活動にキュレーション展『惑星ザムザ』(小高製本工業跡地、2022年)、個展『新しい死体』(PARCO Museum Tokyo、2022年)、一人ずつしかアクセスできないオンライン展『隔離式濃厚接触室』(2020年)など。著書として『ラブレターの書き方』(晶文社)、詩集『涙のカタログ』(パルコ出版、共に2023年)。国立西洋美術館や金沢21世紀美術館などでも作品を発表。IG:@rintarofuse、X:@rintarofuse











