雑誌『tattva』編集長・花井優太インタビュー「10年後に、また同じテーマで、また『tattva』10冊を作る意味」(後編)

- 『tattva Vol.10』
- tattva編集部
- ブートレグ
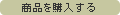
- >> Amazon.co.jp
- >> HMV&BOOKS
雑誌『tattva』の最新号、vol.10「わたしたちが普段言葉にする本物について」が2025年7月発売になりました。ビジネス、アート、テクノロジー、カルチャーなど、さまざまな切り口から多様な視点を取り上げてきた同誌は、「10年後の再始動」を掲げ、このvol.10でいったん活動を休止します。
そこで、2021年の創刊から約5年の歩みを編集長の花井優太さんと振り返ります。後編は10年後の再始動を掲げる理由について。聞き手は、読者でもあり、花井さんとも親交のあるアーティストの布施琳太郎さんです。
■休止と同時に再始動を宣言する理由
布施:花井さんは『tattva』をvol.10まで作ってきたわけですが、雑誌であるにもかかわらず、広告は入っていませんでしたよね。それは意識的に避けていたんでしょうか?
花井:創刊からしばらくはお金を出してくれた会社がありました。ただ、純広告ではなく、サポート的な関わり方でした。いろいろあって途中からなくなり、最後は完全に自己資金で作りました。だからこそ、内容を好きに作れたところもあって。
布施:自分もアーティストとして展覧会を企画しますが、どうしても予算とか、この内容で採算がとれるのかということは気にせざるを得ないんですよ。そこはあまり気にしなくてよかった?
花井:というより、自分たちみたいな人間は絶対にこういうものが読みたいはずだって信じていて、それは何万人もいないかもしれないけど、数千人だったらいるんじゃないか。だから、そのサイズ感でやれる経済モデルで最初から作ったという順番ですね。
布施:なるほど。しかし、『tattva』を読み直して、改めて雑誌という存在はありがたいなと思いました。これからまた世界情勢が変わり、都市も変わっていくだろうときに、懐かしい気持ちにさせてくれる紙媒体があるのはありがたいなって。
花井:また紙で10年後も作りますから。
布施:それについても聞きたいのですが、10年後でも雑誌を作るレベルのインプットとアウトプットを維持できそうですか?
花井:むしろ、自分たちにプレッシャーをかけているんですよ。『tattva』は「宙吊りの問い」を集めた媒体なので、あくまで「現時点では」という仮の結論をまとめているんです。だから、10年後に10冊分のテーマで「進捗はいかがですか?」とやるのは当然というか。それが問いかけた側の責任だと思っています。
10年後の再始動で期待しているのは、「ほら予想通りだった」よりも、「間違っていたんだ、あのとき思っていたことは」となることですね(笑)。今、編集部の平均年齢は30代で体力的にもまだまだ元気。でも、10年後にはぼくも47歳だから、同じテーマでも違った見え方をするだろうし、それはそれで面白いだろうなって今からワクワクしています。
ただ、まったく同じ作り方はしたくないですね。それこそ10年後は同世代だけでなく、今のぼくらと同じくらいの年齢の世代とか、もっと下の世代とも一緒に作りたい。
■10年という時間軸の意味
布施:素朴な疑問なんですけど、「5年やったんだから次も5年後」のほうがありそうですよね。なんで10年後なんですか?
花井:うーん、それぐらい時間を置かないと、それぞれのライフステージも世の中も変化がないだろうなって。問いは時間を置いてから問い直すことに意味があるけど、5年だと変化の兆しが見えるぐらいの期間なんですよね。
実際、今から5年前だと2020年。コロナ禍こそあったけど、テクノロジーも価値観もそれほど大きくは変わってはいない。でも、10年前にさかのぼったら、働き方改革よりも前なんですよ。コンプライアンスも今ほど騒がれていなかった。
布施:確かに世の中の倫理観も違いました。
花井:だから、やっぱり10年ぐらい寝かすことには意味がある。それで言うと、布施くんも学生時代に展覧会を初めてから、10年ちょっとが経ったわけだよね。このタイミングで新しい展覧会(「人工呼吸、あるいは自画像の自画像」展 2025年6月20日~8月2日)を行うわけですが、10年という月日の変化は感じている?
布施:そうですね。ぼくは20歳で自主企画の展覧会をやり始めて、今年で10年くらいアーティストとして活動してきたんですが、30歳になって、改めて「自画像を描こう」という気持ちになりました。
花井:そうなんだ。
布施:ぼくはアーティストとしては人前で話す機会が多いほうですけど、そのときに見た目を取り繕ったりとかしちゃうので、あえて「素の自分を描く」っていうのをやってみようと。
あと、今までは他の作家と展覧会をやってきたんですが、関わる人が増えた結果、人に対する疑心暗鬼が芽生えてしまうことも増えてしまって。どこからどこまでが自分のアイデアなのか、自分の責任の範囲なのか、よくわからなくなってくるんですよ。そうやってモヤモヤしたいろいろを抱えるようになってきた中で、まず1人で完結する個展をやって、人生のピンを打ちたいと思ったんです。
花井:うんうん。
布施:だから、今回は「自画像」というテーマにしました。
花井:今までの布施くんは作品をシリーズで作り、その個展をやっていくっていうよりは、他の作家も巻き込んだインスタレーションをやっているイメージのほうが強いと思うんだよね。
布施:そうですね。
花井:他の人と常にいる感じ。だから「自画像」を選んだのは、「青い服を着てなくても布施琳太郎だぞ」って宣言するためでしょう?
■「青い服を着てなくても布施琳太郎だ」
布施:そう考えたことはなかったですけど(笑)。
花井:でも、そうなんじゃないかなと思って。要するに、すでに「青い服=布施琳太郎」という固定化されつつあるイメージがあるのに、わざわざ「自画像」って言い始めたってことは、やっぱり、「俺は青い服を着てなくても布施琳太郎だ」と言いたくなったんじゃないかと思って。
布施:ああ、そう言われてみれば、そうですね。
花井:例えば、「三上晴子だったら、こういう感じ」とか「フェリックス・ゴンザレス=トレスだったら、こういう感じ」とか、アーティストには固有の手触りがあるじゃないですか。
布施:ありますね。
花井:だから、布施くんが「自画像」と言い始めたってことは、ついに自分らしい手触りを手に入れるために動き出したんだなって解釈したんですよ。
実際、今回はコンセプトが前に出てない。100枚のドローイングとか、モノとしての作品のほうを前に出そうとしている。それも自分の仕事を再定義しようとしているのかなって。
布施:そうですね。今回は自画像だけではなく、パフォーマンスもあるんですけど、それも自分の等身大のシルエット、つまりは自分自身の影に人工呼吸するという内容なんです。意図を説明しちゃうと元も子もないんですけど、要するに自分にとっての仕事って何なんだろうって考えたとき、やっぱりモノを作ることがどうしても好きだというのと、ある場所に息を吹き込んでみんなで熱くなるのも好きだということを、最もシンプルに表現したかったんですよ。
花井:それはとてもいいよね。2月の「パビリオン・ゼロ」展もすごく良かったと思うけど、あれは作家の手仕事というよりは、プランニングの妙だと思っているんですよ。
布施:はい、はい。
花井:あくまでコンセプトとコンテクストを巧みに編み合わせた成果だと思う。でも、このままでいったら、「布施琳太郎は企画者や演出家ではあるかもしれないが、果たしてアーティストなのか?」という疑問が出てきてしまう。でも、そこから今回の個展の方向に行ったので、やっぱり布施くんは作家として生きていきたいんだなって思いました。
■手仕事がある人でいたい
布施:実際、「パビリオン・ゼロ」の後、最終的なキーワードとして出てきたのが「手仕事」だったんですよ。
「手仕事がある人」って何か。それは手ぶらで現れても自分の世界が作れる人だと思っていて。だから、自分も手ぶらで世界を作れなければ、モノを作る人じゃないよなと思っちゃったんです。
「パビリオン・ゼロ」にはたくさんの人が来てくれましたけど、具体的に手仕事のクリエイションをしているのは他の作家たちであって、「これで俺、プロデューサーって呼ばれるようになったらイヤだな」とは普通に考えさせられましたね。
花井:あの時点で言われかけていたかもしれないよね。
布施:だから、それは避けたいと思って。これは花井さんもそうだと思いますけど、自分が面白いと思う人に面白いと思われたいじゃないですか。
花井:はい。自分の面白いと思う人に面白いと思ってもらえたら十分ですね。
布施:だから、今回の個展では、そうなっていくための道をちゃんと作ろうって思ったって感じですね。みんな、「自分はこういうタイプだな」と人生のスタイルを決めるのが早くないですか? ぼくは30歳になって初めてわかりました。
花井:ぼくはまだ分からない。だって、キャリアはライター・編集者でスタートしているけど、最近は雑誌より、企業のブランディングとか、ミュージックビデオの仕事が圧倒的に多いわけで。ただ年々、アウトプットの数は増えてるんです。
布施:「俺は何屋さんなんだ」みたいな(笑)。でも仕事のジャンルはバラバラでも、ずっと手仕事ではあるわけですよね。
花井:はい。だから10年後の『tattva』も手仕事で作っていたいですね。
<プロフィール>
花井 優太
クリエイティブ・ディレクター/ 編集者。 エディトリアルをバックボーンに、情報戦略、コピーライティング、事業・商品コンセプト開発、PR、TVCMやミュージックビデオの映像企画、ブランドブック制作などを行う。2021年に雑誌『tattva』創刊、編集長。受賞歴に日経広告賞部門優秀賞、毎日広告デザイン賞準部門賞など。著書に『カルチュラル・コンピテンシー』(共著)がある。IG:@iamyutahanai
布施 琳太郎
アーティスト。iPhoneが発売されて以降の都市における「孤独」や「二人であること」をつくりだすために自主企画の展覧会を中心として、映像作品や絵画、インスタレーションの制作、詩や批評の執筆などを行っている。主な活動にキュレーション展『惑星ザムザ』(小高製本工業跡地、2022年)、個展『新しい死体』(PARCO Museum Tokyo、2022年)、一人ずつしかアクセスできないオンライン展『隔離式濃厚接触室』(2020年)など。著書として『ラブレターの書き方』(晶文社)、詩集『涙のカタログ』(パルコ出版、共に2023年)。国立西洋美術館や金沢21世紀美術館などでも作品を発表。IG:@rintarofuse、X:@rintarofuse











