公共施設が20年で崩壊!? 国家レベルで進む「ファスト建築」の流れ

- 『ファスト化する日本建築 (扶桑社新書)』
- 森山 高至
- 扶桑社
- 1,155円(税込)
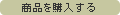
- >> Amazon.co.jp
- >> HMV&BOOKS
私たちが日ごろからよく目にする「ファスト」という言葉。「速い」「迅速な」といった意味を持ちますが、「ファストフード」の「ファスト」には、単に速いだけではなく「安い、便利、お手軽、気軽」といった意味も含まれていることは、皆さんもご存じかと思います。また、近年では、時短や倍速で映画を観る「ファスト視聴」や、映画の切り貼りをして短縮した「ファスト映画」なども生まれました。
こうした「ファスト化」の流れは、建築のジャンルにも起きているのではないか――そう指摘するのは、建築エコノミストの森山高至氏。そもそも建築とは長い時間をかけて造り、長い時間を使用する、「ファスト」とは真逆のものであるはずなのに、それを「早く・短く・手軽に」と考えた結果、個人の住宅や公共施設の建築、さらには都市計画や国のあり方にいたるまで、さまざまな影響をおよぼしているのが現状だといいます。森山氏の著書『ファスト化する日本建築』は、今の建築業界に山積する問題と、その原因は何かについてさまざまなテーマから解説した一冊です。
その象徴的な事例として挙げられているのが、第一章「公共施設のファスト化」で取り上げている「腐る建築」問題。ある公共の美術館が有名建築家の設計のもと建設されたものの、完成からおよそ20年という短期間で木造屋根の材料が腐って崩れ落ちたというニュースは、一時大きな話題となりました。これについて森山氏は、日本の建築文化の成立を歴史から丁寧に読み解いたうえで、こう記します。
「現代人の社会に最適化した生産性の高い普遍的な技術や素材で出来上がる普通の建築に、いきなり技術的接続性のないまま、地域性や伝統的建築でできたかつての日本建築の素材要素を、ただ単に見た目だけの、視覚表現だけをもとめて、気安く木の素材感を、建築に被せてしまったことによる、技術史上の矛盾の結果」(同書より)
これはまさに「現代的な工法で簡単に建てながら、伝統建築の視覚イメージを付けたい」(同書より)という「ファスト思考」によるものだと考えられるのではないでしょうか。
こうした安易な建築思考は、現在では大型商業モールやチェーン店、都市型狭小住宅など、いたるところで見られます。さらにこのファスト化は、明治神宮外苑再開発問題や東京オリンピックでの新国立競技場問題、現在開催中の大阪・関西万博2025など、都市開発や国際社会における国のあり方などにまで広がっていることがうかがえます。しかし、森山氏によると「最近になって急にファスト化しているわけではなく、むしろこの数十年間、どんどんファスト化していた」(同書より)とのこと。
世の中が建築にも「早い・安い・手軽」を追求し続けた結果、私たちは何を得て、何を失ったのか――。同書はファスト化社会の縮図を垣間見ることができる一冊と言えるかもしれません。
[文・鷺ノ宮やよい]











