電車で喫煙、ポイ捨て当たり前...... "昭和レトロ"ブームからはわからない「裏」文化史

- 『不適切な昭和 (中公新書ラクレ 841)』
- 葛城 明彦
- 中央公論新社
- 990円(税込)
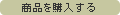
- >> Amazon.co.jp
- >> HMV&BOOKS
今では若い世代に広まっている「昭和レトロ」ブーム。当時のファッションやインテリア、グルメなどに魅了される人も多く、昭和の暮らしをテーマにしたデパートや博物館のイベントは軒並み盛況です。いっぽうで、昨年ヒットしたテレビドラマ『不適切にもほどがある!』では、現代とはあまりに異なる昭和の価値観が面白おかしく描かれており、当時を知らない人たちの中には「昭和ってこんなだったのか!」と、驚きを覚えた人もいるかもしれません。
今回紹介する書籍『不適切な昭和』は、そんな理想化されていないほうの昭和にスポットライトを当てた一冊。著者の葛城明彦氏は同書について、「テレビなどではほとんど報じられないような『裏』の昭和文化史をテーマとしている」(同書より)と記しています。
全部で6章から構成されている同書。第1章「社会」では、「タバコを吸えない場所がほとんどなかった」「ポイ捨て当たり前で、街はどこもゴミだらけだった」「川がドロドロに汚れていて、凄まじい悪臭がした」など、しょっぱなから「暗くて汚かった街」というリアルな昭和の風景を提示します。私も葛城氏と同じ世代ですが、たしかに当時は電車内、駅のホーム、映画館、病院、会社と、ほぼどこでも喫煙OKだった記憶があります。それもそのはず(?)、日本の喫煙率のピークである1966年(昭和41年)は、成人男子の喫煙率が83.7%だったそうです。「吸わない男は『クソ真面目』『カタブツ』『ちょっと変わった人』のようにみられており、今とは反対に肩身が狭かった」(同書より)という記述にはうなずけると同時に、現代との価値観の違いに驚かされます。
また、ゴミについてもタバコの吸い殻や吐き捨てたチューインガム、紙クズなどが道に落ちているのは当たり前。生活排水や工場排水、粗大ゴミとなった家電を川に捨てるなどもよくあることで、各河川が浄化され始めたのは昭和50年ごろ(1975年以降)からだったといいます。美化されがちな昭和ですが、「この点に関してはまったく文句なしに改善された一面といってよいだろう」(同書より)と葛城氏は記します。
このほか同書は、第2章「学校」、第3章「家庭と職場」、第4章「交通」、第5章「女性」、第6章「メディアと芸能界」という章立て。現代の常識からすると、差別もセクハラも放ったらかし、メディアも規制ユルユルのやりたい放題で、これを「おおらかでよい時代だった」と見るか、「コンプラ意識ゼロ」と見るかは意見が分かれそうなところです。ただし、時代というのは良い面もあれば悪い面もあるもの。「おそらく、『表』のみならずこうした『裏』の一面も知ることで、あの時代をより具体的かつ立体的に捉え直していくことも可能になるのではないかと思う」(同書より)との葛城氏の言葉のとおり、同書は昭和の時代の実情を知るうえで、役立つ一冊になるのではないでしょうか。
[文・鷺ノ宮やよい]











