「謝ったら死ぬ病」が急増中!? そのいびつな精神的メカニズムを心理学者が解き明かす

- 『絶対「謝らない人」: 自らの非をけっして認めない人たちの心理 (詩想社新書)』
- 榎本博明
- 詩想社
- 1,155円(税込)
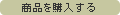
- >> Amazon.co.jp
- >> HMV&BOOKS
皆さんの周りに、「すみません」のひと言を絶対に言わない人はいないでしょうか。ミスをしても謝らずに平然としている、それどころか指摘すると逆ギレする、「聞いていません」「言っていません」とシラを切る、平気で見え透いた言い訳をする――。心理学者の榎本博明さんによると、こうした「絶対に謝らない人」が、ネット上でも実生活でも急増しているといいます。榎本さんが著した『絶対「謝らない人」:自らの非をけっして認めない人たちの心理』は、こうした「謝ったら死ぬ病」ともいえる人々のいびつな心理メカニズムについて解き明かした一冊です。
「絶対に謝らない人」はどのような人に多いのでしょうか? それは意外にも、自分に自信のない「硝子のプライド」の持ち主に多いそうです。「自信がなく、不安でいっぱいだからこそ、偉そうに振る舞って、自信ありげな態度をとる必要がある」(同書より)とのこと。ほかにも、人の気持ちがわからない根っからの自己チュータイプや、叱られずに育ったことでストレス耐性の乏しい人、認知能力に課題がある人、メタ認知がうまく働かない人なども当てはまるそうです。
とはいえ、そもそも「謝罪ってそんなに大切?」と思う人もいるかもしれません。同書では、謝罪が持つ心理的効用についても解説されています。日本では「自分に非があるとも思えない場合でも、なんらかの存在を被り、やり場のない気持ちを抱えて傷ついている相手を思いやり、とりあえず謝る」(同書より)ということがあるのは、皆さんも経験があるのではないでしょうか。欧米人やアラブ人にとって、「非を認めることは責任を追及されるのはどちらであるかを決めるための正しさを競う争いに負けることを意味する」(同書より)のに対し、日本人にとって謝罪は「相手の気持ちに救いを与え、その場の雰囲気やお互いの間柄を良好に保つことを意味する」(同書より)ものだと言えます。こうした「思いやりに基づく謝罪」という文化があるからこそ、よけいに、「絶対に謝らない人」のことを私たちは特異に感じるのかもしれません。
では、こうした人々とどのようにつき合えばよいのでしょうか。結局のところ、相手に深入りせず、過度な期待を持たないことが最も有効だとされています。同書では「絶対に謝らない人」とのかかわり方についても詳しく記されているので、日ごろ困っている方はぜひ参考にしてみてください。「絶対に『謝らない人』の心理メカニズムがわかれば、その種の人に振り回されることなく、無難にかかわれるようになるはずだ」(同書より)という榎本さん。自分を省みることはないと思える相手には、応対するこちらが意識を変えるほうが、より建設的だと言えそうです。
[文・鷺ノ宮やよい]











