猫探しの呪術、意味不明のまま続けられてきたゲーター祭...... 不思議な民間信仰はまだまだ日本に生きている

- 『現代「ますように」考 こわくてかわいい日本の民間信仰』
- 井上真史
- 淡交社
- 1,650円(税込)
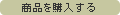
- >> Amazon.co.jp
- >> HMV&BOOKS
信仰心がない、無宗教などと言われることの多い日本人。しかし、神様や見えざる世界への信仰らしきものは日本にも確かに存在し、宗教性がまったくないかというと決してそういうことはない。そんな日本の民間宗教を集めて紹介した書籍が、『現代「ますように」考 こわくてかわいい日本の民間信仰』(淡交社)だ。
著者である井上真史氏は、神社には「〇〇しますように」と書かれた絵馬があるように、神仏の存在を確信しているわけではないけれど「叶うと嬉しいな」くらいの受動的な態度で、日本人は「カミ」との距離感があるという。
そんな「ますように」を集めた同書は、ただ民間信仰を紹介する本や学術書ではなく、なにかを願わずにはいられない人間の心に思いをめぐらせた一冊だ。
町内会の掲示板や地域のお店で見かけることのある「迷い猫」のチラシ。その中にも「ますように」を見ることができる。もちろん「猫が帰ってきますように」という願いを込めてチラシは作られているが、一種の呪術のような手法がとられていることもある。
「猫とは気まぐれにふらりと姿を消すやつら。猫を探す呪術は様々なものが報告されています。『まつとし聞かば』は特に有名だったようで、全国のバリエーションを見ると、『猫の食事する場所に逆さに貼りつけておく』(長崎県)、『上の句をかまどの柱に貼る。帰ってきたら下の句を書いて貼る』(群馬県)など、広い範囲で伝わる様子がわかります」(同書より)
百人一首にも収録されている中納言・在原行平の歌「たちわかれ いなばの山の 峰に生ふる まつとし聞かば 今かえりこむ」は、もとは旅立ちの思いを詠んだ歌。しかしいつの頃からか、人や迷い猫を探すまじないとして広まった。
「まつとしきかば」のまじないは、昭和を代表する小説家・内田百閒の『ノラや』(文芸春秋新社)にも登場し有名となった。かわいがっていた猫のノラが行方知れずになり、4種類も作った猫探しチラシのひとつにレイアウトされていたのが「まつとしきかば」の歌。今も猫好きたちの中で残り続けている民間信仰のひとつだ。
また、数ある「ますように」の中でも代表的なものが、病気の治癒を祈願した「治りますように」の願い。その思いを具現化し民間信仰として広まったひとつが、触ってお参りする像「撫で仏」だ。日本各地にあり、頭が痛かったら像の頭を撫で、腰が悪かったら腰を撫でて祈願するものである。
「摩耗の仕方が激しいものを見るとテンションがあがります。特定の部位、指や目などが特にすり減っていると、なおよし。同じ人が何回も何回もお参りし触れていったのか、同じ悩みを持つ人たちが何人も訪れたのか、あるいはほかよりすり減っている部分をなんとなく触ってしまいたくなる子供めいた喜びを持つ人が私以外にもいたのか」(同書より)
像の摩耗や欠損は、参拝者たちが訪れてきた過去の歴史を物理的に記述している。井上氏は、なにかに触れる行為が物体と自分との間に関係を構築し、見えない繋がりとの連続性や共感が発生されるという。それこそが「ますように」が残り続ける理由なのであろう。
同様に、見えない繋がりとの関わり方のひとつが「祭」である。祭とは本来、人と「カミ」の交流する場であり、日常から逸脱し、どんどん「ヘン」になっているものが多い。
「世の中にはわけのわからない祭が存在します。ゲーター祭こそは、我が人生において最高にわけのわからない祭でした。由来一切不明。意味一切不明。わかっているのは、元旦早朝、輪を竿でもって突き上げ、そして叩き落とす祭ということくらい。もうなにもかもわかりません」(同書より)
三重県鳥羽港から船で40分ほどの離島・神島で行われる「ゲーター祭」。細長い竿を持った男たちが港に集まり、「アワ」と呼ばれる木で作られた輪を竿で突くように持ち上げ叩き落とす。何の意味があるのかまったく不明のまま、やっている人たちも何なのかわからないまま続けられてきたという。
「ますように」の祈願やパワーの由来を説明する縁起が忘れられ、本人たちもよくわからずとも続いている信仰は全国に多々ある。井上氏は、ただなんとなく続いている民間信仰のある種の極致だという。
消えていくもの、忘れられたものもあれば、新しい解釈や物語が違う意味に変化するものもある。時代が変化しても、人間はおそれることや願うことがなくなることはなく、「ますように」は常に変化して在り続けるのだ。
人間の願いのかわいらしさとおそろしさを知ることができる民間信仰。この本をきっかけに、住んでいる地域の神社や信仰物の由来や起源をたどってみるのもいいかもしれない。











