チョコレートを切り口に学ぶ、ヨーロッパとキリスト教の歴史や世界情勢

- 『チョコレートで読み解く世界史 (ポプラ新書 253)』
- 増田 ユリヤ
- ポプラ社
- 1,078円(税込)
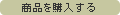
- >> Amazon.co.jp
- >> HMV&BOOKS
普段、コンビニやスーパーで気軽に手にすることも多いチョコレート。これほどまでに世界中で愛されている食べ物も珍しいかもしれません。そんな私たちに身近なチョコレートを切り口に、中世ヨーロッパから近代までの歴史と宗教について解説しているのが、ジャーナリストの増田ユリヤさんが著した『チョコレートで読み解く世界史』です。
チョコレートの起源は、今から数千年前のマヤ・アステカ文明までさかのぼります。それまで果肉を食べていたカカオ豆が、「焙煎することで美味しくなることに気付き、煎ったカカオ豆をすりつぶして飲み物として飲むようになりました。これが、チョコレートの原点」(同書より)とのこと。最初のチョコレートは滋養強壮などの薬効を期待した健康ドリンクとして、王や貴族といった特権階級の人たちに愛飲されていたそうです。
その後、カカオがヨーロッパにもたらされるきっかけとなったのが、コロンブスの新大陸到達。学生時代に「大航海時代」として習ったことがある人も多いかと思いますが、最近の世界史の教科書や資料集などでは、見出しやタイトルには「スペイン・ポルトガルの海洋進出」という表現が使われています。「これは『大航海時代』という言い方が、ヨーロッパ中心の視点だという批判があるため」で、「国際情勢の大きな変化や、人権や平等、宗教、世界平和といった観点から見ていくと、同じ出来事を語るときでも表現や言葉の使い方を再考する必要が出てきた」(同書より)と増田さんは説明します。このように、私たちがヨーロッパ視点で見てきた世界史をふたたび学び直すことができるというのも、同書を読む意義のひとつです。
さてその後も同書では、ヨーロッパ各地に広まっていったチョコレートが、スペインのキリスト教聖職者たちの間では「断食の時期に摂取してもよいのか」との大論争を呼んだり、ルイ14世時代のフランス宮廷ではチョコレートを飲むための器まで愛でられるようになったりと、興味深い話がどんどんと展開されます。さらに最終章では、増田さんが取材した「ヴィタメール」や「ブノワ・ニアン」といった日本でも知られているチョコレートブランドを挙げながら、21世紀のチョコレート事情についても紹介されています。
まさにタイトルの通り、チョコレートをもとに世界史を読み解くことができる同書。チョコレート好きな人、世界史に興味がある人にとっては、ページをめくる手が止まらなくなるのではないでしょうか。「チョコレートの歴史をたどると世界史が見え、それが現在の国際ニュースを理解する助けになることを目指して執筆しています」(同書より)と「はじめに」で記している増田さん。これまでとは少し違った視点から世界史を見てみたい人にとっても、読む価値のある一冊になることでしょう。
[文・鷺ノ宮やよい]











