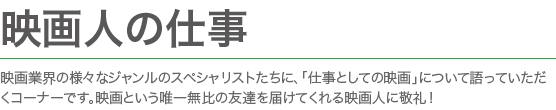映画業界で活躍するすごい映画人に、「仕事としての映画」について語っていただくコーナー。第7回は、映画ジャーナリストの斉藤守彦さんを訪ねました。
70年代後半〜80年代前半にかけて、「決してひとりでは見ないで下さい」(『サスペリア』)や「ジョギリ・ショック」(『サランドラ』)などの、いわゆる"ハッタリ宣伝"で黄金時代を築き、しのぎを削った、「東和」「ヘラルド」「松竹富士」といった独立(インディペンデント)系配給会社の歴史を紐解いた著書『映画宣伝ミラクルワールド』。10月30日に発売し早くも増刷がかかるなど、特にハッタリ宣伝被害者世代(主に40後半〜50代)から大きな支持と共感を集めています。
著者である映画ジャーナリストの斉藤守彦さんもまた、1961年生まれの52歳で、まさに東和に嬉々として騙されつつ青春時代を駆け抜けてきたお一人。とにかく愛にまみれた一冊ではありますが、それと同時に、緻密かつ膨大な情報量の蓄積には驚きと尊敬の念を抱くばかり。映画ジャーナリストってすごい! 単純に純粋に、そんな風に思ったのです。そこで、日本ではあまり見かけない「映画ジャーナリスト」ってどんな仕事なのか。なぜなりたいと思ったのか。どうしたらなれるのか。ご本人に伺いました。(注:長いので、前編・後編に分けています。それでも長いですが)。
評論家とジャーナリストの違いって何だ?
映画評論家という肩書きはよく見かけますが、映画ジャーナリストという肩書きを見かけることはあまりありません。斉藤さんがこの肩書きを初めて使ったのは、1996年に9年勤めた映画業界紙を辞め、フリーランスになった時だそうです。
「必ず聞かれるんですよ。映画ジャーナリストって、映画評論家とどう違うのかって。漠然とした肩書きですから、広い意味で受け止めてくださって構わないのですが、基本的には"可能な限り取材したことを基に書く"ということでしょうか。僕のように配給や興行など映画の経済的な面を書くというスタンスの人もいれば、日本映画の撮影現場に出かけてメイキング取材をするのも映画ジャーナリストとしての仕事です。僕自身もゴジラ映画の密着取材をやって、それを本にしていますし(『ソノラマMOOK ゴジラ・モスラ・キングギドラ/大怪獣総攻撃/朝日ソノラマ刊)。今は少ないですが、映画ジャーナリストという肩書きをもっとたくさんの人が使うようになってくれれば、自分の立ち位置もはっきりしてくるんじゃないかなと思います」
15の頃から、興行少年でした。
映画的ファーストインパクトは、1974年の正月に観た『日本沈没』で人の不幸を見るために立ち見まで出たという光景で、中学・高校時代は東映のヤクザ映画と日活ロマンポルノ以外の日本映画を観まくり青春を謳歌していたという(特に「百恵友和の映画は全部封切りで観た!」そう)、至極純粋な映画少年だった斉藤さん。ではひとりの映画好きの少年が、映画ジャーナリストの方向へと向かうきっかけはどこにあったのでしょうか。実は現在の仕事に繋がる「映画興行」に関心を持たれたのは想像以上に早く、15歳の時に遡るのだそうです。
「高校進学と同時に、ひょんなことから地元の浜松で映画の自主上映活動に参加したんです。活動内容は16ミリのフィルムを浜松市児童会館というホールでかけて人を集め、また次の上映をやるというサークルのようなもの。上映していた作品は、フェリーニの『道』や『死刑台のメロディ』、『いちご白書』、『青春の蹉跌』などの名作の類いで、映画の内容はお墨付きだったんですが、お客さんが来ないこともあったんです」
名作をかけているのに客が来ない=客が悪い! それが、斉藤さん以外全員社会人だったメンバーの思考回路。でも斉藤さんはメンバーにこんなことを言ったそうです。
「15歳の僕が言うのも何ですが、宣伝しなきゃダメですよね。次の上映会の時には、宣伝費を設定してください。チラシを作って撒くべきです。とにかく次は目標動員数200人!」
なんと高校生にして宣伝戦略を練っていたのです。
「お前のは自主上映じゃなくて自主興行だ、と大人たちからは呆れられましたが。興行少年だったんですよ。映画=商品であるという認識が15歳の時にできあがっちゃっていたんですよね」
"当たる映画こそがいい映画だ!"このことは、15歳の時から今も変わらず斉藤さんの価値基準になっているようです。
「だから立ち見で見た映画が忘れられないんだろうね。映画の内容よりも、どうやって宣伝するか、どう当てるかということの方を、その頃から注目していたんですよね」
"プリントショップ店長"から"映画業界紙編集長"へ、異色の転身
青春時代からずっと映画が好きで、今ではベテランの映画ジャーナリスト。きっとサラブレッド的に映画と関わり続けてきたのだろうな、と思いきや! その経歴はちょっと変わっていました。高校卒業→印刷専門学校→街のプリントショップ店長→映画館でのアルバイトを経て、26歳で映画業界紙の記者に。意外にも遅咲きです。というより、なぜに印刷なんですか!?
「大学受験をしたものの、全部落ちちゃったんです。今後どうしようかと迷っている間に母親が"知り合いの印刷会社の社長と話を付けて来たから"と。そこの印刷会社が街角のプリントショップを展開するから店長をやれって。でも店を作るまでにまだ時間が少しあるから、東京の印刷専門学校に行って印刷の勉強をするようにと言われたんです。だからいまだに軽印刷機は動かせますよ!」
とはいえ映画から心が離れたわけではなく、浜松から東京へ上京し、印刷専門学校に通った3年間は、年間200本もの映画を映画館で見ていたそうです。
「卒業して浜松に戻り、プリントショップの店長になったものの、東京で自由に映画を見ていた時期のことが忘れられなくて。どうせ給料をもらうんだったら、もっと自分の好きなことをやりたいなという気持ちがふつふつと出て来たんです。それで2年目で会社を辞めて、地元の映画館"テアトル有楽"でアルバイトを始めました。地方都市でできる、唯一の映画の仕事が映画館のアルバイトだったんですよ。時給は500円、映写やモギリの仕事をしていました」
また当時「テケツ」(「チケット」が訛ったもの)と呼ばれたチケット売り場の仕事では、後に携わることになる「映画業界紙」を初めて目にしたと言います。
「テケツの中は2畳ぐらいの部屋になっていて、そこに1日中座って切符を売っていました。5ヶ月で7kg太りましたね。郵便物なんかもテケツの部屋に配達されるんですが、その中に混じって、封筒に入った5〜6枚の小汚いわら半紙が毎日のように配達されていたんです。ある日試しに見てみたら、それが映画業界紙だった。しかもそこには、僕が知りたがっていたことが全部載っていたんですよ。次の正月映画はどういう番組になる!とかね」
ブラック企業よりもブラックだった、映画業界紙時代
とにかく映画関連の仕事に就きたい。だからもちろん記者以外にもいろんな選択肢が頭をよぎったそうです。しかし配給会社への就職は、大卒以上新卒採用という条件から、早々に断念。製作方面への就職も考えるも、『Wの悲劇』でエキストラを体験した時に目の当たりにした、撮影現場の体力勝負ぶりに「体力ある方じゃないしな......」と断念。そして22〜23歳頃、「昔から現代国語だけは勉強しないでもできたし、こういう人たちのことを書く仕事だったら自分でできるかもしれない」と、漠然とながら映画について書く仕事をしたいと考え始めたそうです。
「遅いですよね、もう。映画館でアルバイトして貯めたお金で、24歳の時に再度上京したんですが。ビデオ会社でアルバイトしたりと紆余曲折を経て、2年ぐらい経った1987年に業界紙に就職しました」
「映画について書く仕事」の第一歩を踏み出したその会社は、今はなき「東京通信」という社長1人、タイピスト1人、そして新人の斉藤さんという3人だけの小さな会社だったそうです。
「あとになってわかったことなのですが、実はその会社は会社登記も何もしていないもぐりの会社だったんです。今、ブラック企業が問題になっていますが、会社登記しているだけいいじゃないか!って思いますよ(笑)。福利厚生なんて一切なかったですからね。要するに映画業界紙というのは、映画業界に長くいるおじさんたちの顔で仕事が成り立っているようなものですから。東京通信も、社長が個人でやっている仕事だったんだけど、人を雇うために会社であると言い張っていた。ただ他の業界紙の多くは人を雇うことをきっかけに会社登記をして、福利厚生のある会社組織をとっていたんですが、残念ながらうちは違ったんです......」
やがて入社2年目を迎えた頃、社長の入院をきっかけに編集長に就任(1人編集部)。そのさらに数年後に社長が亡くなり、会社を継ぐかどうかの選択を迫られるも辞退。
「やっぱり非常に閉鎖的な業界なんですよね。わけのわからん年寄りが威張ってるんですよ。だから仮に僕が社長を襲名するということになると、まず同業者のおじいさんたちが出て来て、挨拶がないだとか、お前はそれにふさわしい器なのかとか、いろいろ言ってくる。だいたい10年この仕事をやっていれば認められるという暗黙の掟のようなものがあるんですが、僕はその時点ではまだ6年ぐらいでしたから、社長になったらきっといじめられるなと。戦うのも面倒なので継ぐ気はありませんとはっきり断っちゃったんです」
そして1996年、35歳の時に持病が悪化して入院。それを機に会社を辞めフリーとなり、映画ジャーナリストという肩書きで仕事をスタートさせました。最初は知り合いが編集を手がけていた劇場用パンフレットやプレスシート(マスコミ向けのパンフレット)の原稿(『インデペンデンスデイ』や『踊る大捜査線』などそうそうたる作品の!)を手がけ、そこで評価を得て、雑誌の連載や、書籍へと仕事が広がっていったそうです。
後編では、映画ジャーナリストの仕事の実際や現状について伺っていきます。
(取材・文/根本美保子)