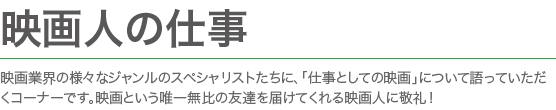引き続き、山田康介さんに聞く「カメラマンの仕事」をお届けします! 伝説のカメラマンとも言われる木村大作さんとのお仕事も多い山田さんに、まずは木村さん伝説をうかがってみたいと思います。
木村大作さんのこと
黒澤明監督から絶大な信頼を寄せられ、今なお第一線でご活躍されている日本屈指の名カメラマン、木村大作さん。そんな木村さんに、山田さんが初めて助手として付いたのは、中国ロケを中心に据えた『赤い月』(2004年/監督:降旗康男)でした。
「もちろん最初は名前も呼ばれなければ、話しかけてももらえない。そういう中ですごく緊張してやっていましたね。中国ロケは3カメでの撮影でしたが、チーフ1名、セカンド3名でサードはなしというコンパクトな体制でした。これは木村さんのやり方というか、自分たちだってこうしてやってきたんだから、お前らも少人数でもちゃんとやれよ!ってことでもあると思います。もちろん統率しやすいという面もありますし。僕はBキャメのセカンドを担当していたんですが、Bキャメのフォーカスをやりながら3台分のフィルムの管理をするというのはやっぱり大変でしたね。でも一番ドキドキしたのはフィルムをすべて日本に持って帰ると木村さんが言い出したことです。要は現像を中国でやらずに、日本に帰ってからやる。でもフィルムで1ヶ月くらい撮り続けていますからね。途中でラッシュ(撮ったものを現像して見る)が一度もできないので、ピントがちゃんと合っているだろうか、フィルムに傷が入っていたらどうしよう......と、ずっと緊張しながら臨んでいました。日本に帰ってまとめてラッシュを見る前の晩は、本当に眠れなかったですね。結局すべて何も問題がなかったので、ほっとしましたが」
木村さんのスタイルって、どんなものなんですか?
「唯一無二な感じはしますよね。木村さんは木村さん。いろんなカメラマンがいますが、その中でもやっぱり特別な人だと思います。怒鳴ることでもすごく有名ですが、それによってみんなが見る方向が同じになるというか、進むべき道がシンプルなんですよね。現場としてはとてもスムーズに進行しますし、木村さんはそうやって時間と人をコントロールし、最終的に自分の撮りたい画を撮るというスタイルだと思います。今もう74歳になられますが、変わらずに怒鳴っていますよ。そこはやっぱりすごいところですよね。ものすごく突っ張ったりもしますが、それでも結果を出し続けている。誰にも真似できないです」
木村さんから学んだことは何ですか?
「僕が一緒にやらせてもらったのは、先ほどの『赤い月』と『単騎、千里を走る。』(2006年/監督:チャン・イーモウ、降旗康男)、『憑神』(2007年/監督:降旗康男)、『剱岳 点の記』(2008年/監督:木村大作)の4本。学んだこと......いっぱいありすぎますけどね。"うまくやらずにちゃんとやる"って木村さんが言っていたことがあるんです。うまいことやる要領のいい人はたぶんいっぱいいると思うんですが、それよりちゃんとやれよ!ってことだと思います。木村さんもある意味で不器用な人ですよね。僕? 僕もめちゃくちゃ不器用ですよ(笑)」
一本立ちへの足がかりとなった『剱岳 点の記』
そんな木村さんとの仕事のなかでも特に面白かったと言うのが、木村さんの初監督作でもある『剱岳 点の記』。
「1年半ぐらいやっていたので大変ではありましたが、ほんとに面白かった。最初期はプロデューサー、木村さん、チーフ助監督、撮影部の先輩と僕の5人でスタートして、浅野さんの扮装をして吹き替え(代役)をやったりしていました。"お前、ちょっとあそこ行って来い!"って言われるんですが、雪山なので凹凸がよくわからず、実際に行くとものすごい谷になっていたりして(笑)。そこを必死になって歩いて行くと、"お前、そこ足が入るからもっとあっち歩け!"とか言われて遠回りして。そういうことを最初の一ヶ月くらいずーっと山に入ってやっていたんです。作品の立ち上げから参加できたのは、とても勉強になりました」
また木村さんの助手に付いた作品では初めて、カメラを回すという重大な役割を任されたそうです。
「別班の撮影を任せてもらったんです。それまで助手で付いた作品ではカメラ自体を回すというのはしていなかったんですが、歩いている人や風景、紅葉している山などを撮ってきてくれと言ってもらって。僕が一番体力があったからというのもありますが(笑)、チャンスをもらえたのは本当に嬉しかったですね。木村さんは面と向かっては褒めてくれませんが、ラッシュ中に"はぁ〜"とか"ほぉ〜"とかいう声が漏れ聞こえてきて。そういう風に驚いてもらえることがすごく嬉しかった。ちょっと恥ずかしいですが、映画公開の時に木村さんのインタビューがキネ旬に載ったんですが、名指しで"山田康介はカメラマンとして大丈夫だ"って書かれていて。それはやっぱり、すごく嬉しかったですね」
カメラマンになった思い出の作品『神様のカルテ』
22歳の時に東宝にサードカメラマンとして入社し、実に12年もの月日を経て山田さんがカメラマンとして初の一本立ちを飾ったのが2011年に公開された『神様のカルテ』(監督:深川栄洋)。2010年に本屋大賞第2位を受賞した同名小説の映画化で、観客動員数150万人以上を記録する大ヒットとなりました。
「自分が初めてカメラマンとして一本立ちした作品ですから、やっぱり思い入れは強いですよね。もちろんわからないこともたくさんありましたし、手探りでやっていた部分はあります。そんな中で一番気にしていたのは、お芝居の邪魔にならないように撮りたいということ。人を見るときに、ワイドレンズで近くから見るのか、望遠のレンズで遠くから見るのかって、お芝居を撮るうえでとても大事なことなんですが、その辺りのことをシーン毎にすごく考えて撮ってましたね。例えば、ワイドレンズを使うとどうしても歪みが出たり画が閑散としてしまったりということがあるので、あえて望遠レンズで引きをとることで圧縮された感じの絵にしたりとか。深川監督はわりと任せてくださるタイプの方なので、自分なりに試行錯誤してやっていけたのもよかったです」
撮影時に思い出深かったことはありますか?
「最後に撮りに行ったのが、山で写真を撮っている宮﨑さんの後ろ姿のシーンでした。千畳敷の山小屋に最少人数のスタッフで泊まって、毎朝5時に起きて撮影に臨みました。2日間撮れなくて、3日目にようやく撮れた時は本当に気持ちよかったですね。実景の撮り方は、それこそ木村さんから教わったことでもあります。極意があるとしたら、待つということ。自然を相手にした時はやっぱり勝てませんから、待って撮らせてもらうという気持ちでやっています」
カメラマンの醍醐味とは?
「単純にいい画が撮れた時は嬉しかったりするんですが、それだけじゃないんですよね。現場の雰囲気もよくて、すごくいい作品ができた時、それからいろんな人から"観たよ""よかったよ"って言ってもらえる時も、本当に嬉しいですし。でも、なんでこんなに続けているんだろう。やっぱり好きなんでしょうね(笑)。『神様のカルテ』の時の話ですが、公開前に劇場チェックというのがあって、日劇のデカいスクリーンでひとりで観たんですが、ものすごく感動しましたね。自分が撮ったものを、この大きなスクリーンで、これだけのお客さんに観てもらえるんだって。その時にすごく感じました。やっぱり一番の醍醐味は、いろんな人に観てもらえるということかもしれないですね」
ちなみにその『神様のカルテ』、「2」が来年公開ということで、今年の1〜2月に撮影をしたそうです。「1」の時には櫻井くんの髪型も話題になりましたが(?)、また同じ髪型なんでしょうか?
「それはちょっとお答えできないですね。乞うご期待ということで(笑)。次観たら、あれ?ってなるかもしれない! 来年です!」
山田康介さんのこの映画がすごい!
では最後に、山田さんがカメラマンとして素晴らしいと思う映画や、個人的に好きな映画についてお聞きしていきたいと思います。
<その1> 『オブリビオン』がすごい!
「映画を観ると、カメラマンの名前はけっこうチェックしますが、最近だと『オブリビオン』のクラウディオ・ミランダはすごいなと思いましたね。普通はセットの背景にはグリーンバックを使うんですが、『オブリビオン』はそれを全部プロジェクターで投影した実際の画の中でやっているんです。ハワイの火山の頂上近くで3週間以上にもわたって収録した映像を投影して、その風景の中で役者が演じる。アイデアがいいですよね。役者だってグリーンバックの中でお芝居するよりも、そこに本当に素晴らしい風景が見えていれば自然と馴染むと思うんです。それからグリーンバックだとどうしても色が映り込んでしまうんですが、プロジェクターで投影してやっている分、写りも全部本物に近い状態なので素晴らしく綺麗なんです。実際にその場所で撮っているかのように見えますから。もともと車の走りをセットで撮る時に背景をプロジェクターで流すという時代はありましたが、まったく主流ではなくなっていたんです。技術が進歩してこれをやったのは初めてなんじゃないでしょうか。『オブリビオン』では高さ約12m、横約150mほどもある巨大スクリーンに21台ものプロジェクターを使ってリアルタイムに投影しているそうですから、ものすごい規模ですよね。技術の革新とともに出たアイデアだと思いますし、ほんとに素晴らしいですよ。観た方がいいです!」
<その2> スピルバーグはやっぱりすごい!
「例えばコーエン兄弟やクリストファー・ノーラン。好きな監督や映画はたくさんありますが、スピルバーグもやっぱりすごいなと思うんですよね。すごく視覚的な表現をやっているにもかかわらず、ちゃんとお芝居も撮れているという。それでいて話も面白いし、バランスがすごくとれているなって思います。最近はシンプルな感じがしますけどね」
また、コーエン兄弟の作品の撮影監督として知られるロジャー・ディンキンスは、好きなカメラマンのひとりだそう。
「『ショーシャンクの空に』の撮影監督もやっているんですが、モーガン・フリーマンとティム・ロビンスが対峙している横位置の引きのシーンが素晴らしくて。影が画面の真ん中を通っていて、モーガン・フリーマンの方にだけ少しシャドウが入っているという。それがそのシーンにすごく合っていたんです。ロジャー・ディンキンスは光や影の使い方が上手いんですよ。光と影で描くというのは映画の撮影の根本的な考え方でもありますが、それをいかに効果的に見せるかというのは大事ですよね。まったく光がないとお芝居が見えませんが、見えないことによって表現できることもありますしね」
山田さん、ありがとうございました!