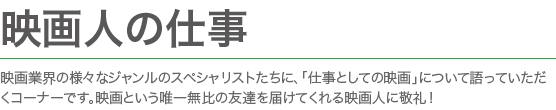映画業界で活躍するすごい映画人に、「仕事としての映画」について語っていただくコーナー。第4回は、編集技師の上野聡一さんを訪ねました。手がけた作品は『ピンポン』『ジョゼと虎と魚たち』など、20年で80本。ほぼ毎年のように日本アカデミー賞にノミネートされている敏腕編集マンです。
きっかけは、大学の映画研究会
映画編集歴は、今年でちょうど20年(助手時代が6年、編集技師として14年)。現在44歳の上野聡一さん、意外にも少年時代はごくごく"普通"の映画体験を送ってきたそうです。
「子どもの頃は、テレビで放映している映画を観ることがほとんどで、劇場ではアニメ映画くらいしか観ていなかったですね。映画館に行くようになったのは、小学校高学年くらいから。思春期を過ごした80年代には、朝から晩まで映画を観ているようなこともありましたが、そこまでむさぼるように観ていたという感覚はないですね」
そんな上野さんの転機は、大学時代。
「ゲーム、漫画、アニメなんかが好きだったので、それにまつわるサークルに入りたくていろいろ面接を受けました。結果的になんとなく入ったのが映画研究会。なんで入ったのかな? 全然覚えてないんですよ。でも、入ってみたら8mmでの映画制作が無性に楽しくて。CMのようなものとか、それに毛が生えたような短編映画なんかを、お遊びで撮ってたんですけどね」
役者、カメラ、音入れ、編集、映写。特に決まった役割があるわけでもなく、それぞれにいろんなパートを担当しながら、制作していたそうです。
「ただ、役者だけはみんな嫌がってましたね。撮られ慣れていないから恥ずかしいのと、醜態もさらされてしまいますから(笑)。僕はけっこうノリノリで役者もやってはいましたけど、やっぱり作る方が楽しかったですね。特に、撮り終えたあとの音入れや編集が」
今はなきKYOTO映画塾で、編集を学ぶ
映画作りの楽しさを知った大学卒業後、「何を血迷ったか映画の専門学校に行った」という上野さん。その学校というのが、1990年に松竹京都映画撮影所内に開校したKYOTO映画塾。残念ながら2000年に閉校してしまいましたが、多くの映画人を輩出した2年制の映画専門学校でした。
「1年目は座学、2年目で撮影、照明、編集、美術、監督、プロデュースなどの中から専攻を選ぶんですが、その時に選んだのが編集でした。選んだ理由? みんな監督がやりたいですからね、監督コースへわーっと押し寄せまして。僕はそういうのが苦手だったので・・・。大学の映画研究会でも編集が面白かったので、やってみようかなって」
KYOTO映画塾で教わっていたのが、『座頭市』シリーズなど多くの勝プロ作品の編集を手がけた、大ベテランの編集技師・谷口登司夫さん。『3-4X10月』で北野武監督に編集術を伝授した、現代日本映画界の至宝のような存在です。
「授業には、谷口さんに師事していたフリーの編集技師・宮島竜治さん(『ALWAYS三丁目の夕日』編集、『歌謡曲だよ、人生は〜乙女のワルツ』で監督デビューなど)も応援にいらして。宮島さんとは年も近かったので馬が合いまして、卒業して東京に出てきたあとに、助手で呼んでもらいました。それからはずっと編集で食べてますね」
ちなみに上野さんは、会社に属したことは一度もなく、20年間ずっとフリーで仕事をされているそう。
「昔は撮影所それぞれに社員がいましたけど、今はもういないと思いますね。編集専門の会社というのもありますが、今はほとんどの人がフリーだと思います」
編集技師ってどんな仕事ですか!?
さて、ここからは編集技師の仕事について、上野さんに聞いてみたいと思います。
①依頼
「これは、それぞれの編集マンのネットワークによりますね。まったく知らないところから声がかかることもありますし、昔やった方から連絡があることも。作品にもよりますが、だいたいクランクインする半年〜1年前に声がかかることが多いですね。"体空けといてね"って」
②撮影素材のチェック・管理
「僕の場合は、クランクインから入れてもらえるように頼んで、撮影のたびにあがってくる素材をチェック、管理しながら少しずつ繋いでいきます。それを定期的に現場に送って見てもらう。この作業を撮影終了までずーっと続けていきます」
③クランクアップ。全編をざっくり繋ぐ
「撮影素材がすべて揃ったら、ひと通りざっくりと繋いで、監督との作業に備えます」
④監督との共同作業
「ここからは監督も編集室に入って、ざっくりと繋いだものを見ながら、だいたい3週間ぐらいで編集の決着をつけていきます。実際に頭から一緒に見てあれこれやっていく監督もいれば、試写だけ見て編集室とは関係ない場所で打ち合わせをし、監督のリクエスト通りに仕上げたものをまた試写で見て・・・というのを繰り返すタイプの方もいます。でも、だいたいは編集室で一緒にやっていくスタイルですね」
⑤合成部とのキャッチボール
「膨大な数の合成の管理、チェックも編集の仕事です。最近は合成がない映画って、そんなにないですからね。合成の作業自体は合成部が行いますが、単純に見えてはいけないものを消したり、緑の壁の前で役者さんが芝居をしたものに作り物の背景を合わせるという大掛かりなものまでいろいろあります。それらの合成カットを合成部に作成してもらってこちらに戻してもらい、それを入れ込んで編集して・・・というのを、キャッチボールしながら繰り返していきます」
⑥音入れ
「ここでは編集は一旦待機。できあがった編集に音楽や効果音を入れていく作業です。音の素材が全部集まったところで録音部が音楽、セリフ、効果音などのバランスをとって、音の編集をし、MIXしていきます。その後、完成前試写(0号試写)を経て、完成(初号)です」

デジタル時代ってどうですか? 「助手時代はすべてフィルムでしたが、独立してからはデジタルが圧倒的。2000年前後に、デスクトップのノンリニア編集機が出てきたので、ちょうど僕が独立した頃が変容期だったと思います」 と、上野さん。では、デジタルのメリットってどんなところですか?
「いろんな編集パターンを簡単に残しておけることだと思います。ちょっとした合成やオーバーラップ、フェイドアウトなども、かつては現像所にお願いして3日くらい待たないと見られませんでした。デジタルになってからはそういうものもその場ですぐにできますし、音楽も簡単に当てることができる。"即時性"がメリットだとは思います」
でもそのことは、同時にデメリットにもなり得ると上野さん。
「フィルム時代に比べると、緊張感が減った感じはありますね。フィルムではちょっと直すのにもすごく時間がかかりますから、トライする前にかなり熟考してやっていたんです。でもデジタルだと簡単で、取り返しもつくので、とりあえずやってみようという風潮になってはいますね。それが果たしていいことに・・・・なってるんだろうなぁ。うーん、でも、真っ白いキャンバスに絵を描いていく緊張感と、デスクトップでやり直しのきく絵を描く緊張感の違いとも、似ていると思うんですよね。例えば出版だって、アナログでやっていた人がやる出版と、デジタルしか知らない人がやる出版では、どちらがいいとは言えませんが、明らかな違いがあると思うんです。音楽だってそうですよね。ただ緊張感があるからいいものができるかというと、必ずしもそうとも言えませんが、やはり何かが欠けているような気はしてしまいます。今さらもう後戻りはできないんですけどね」
また前回、予告篇ディレクターの小松敏和さんもおっしゃっていましたが、"いろんな人がいろんなことを言う"現象は、編集の現場でもデジタル時代に顕著になったことのようです。
「その場でやってその場で見せられますからね。基本的には監督が決定権を持っていますが、プロデューサーや製作委員会の出資者の方など、いろんな意見が出てきます。それが悪いことだとは思いませんが、船頭多くして船山に登るとも言われるように、すべての人の言うことを聞いていたら、本質が全然違うものになってしまうことも、なきにしもあらず、です」
後編では、作品制作にまつわるエピソードや、好きな映画をうかがっています。お楽しみに!
(取材・文/根本美保子)