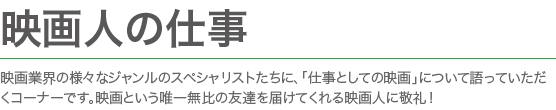前編に引き続き、予告篇界の重鎮・小松敏和さんのお話。今回は、予告篇の歴史や、予告篇制作の仕事の中身について聞いてみた!
日本で初めて予告篇を作った人のこと
「まず洋画でいうと、昔は本国からに送られてきた予告篇に、字幕を入れてそのまま流すのが一般的なスタイルでした。一方、邦画の場合は撮影所の助監督が作るというのが一つのパターン。今も昔も、予告篇の役割は新しい映画のお知らせということに変わりはないけど、昔は、素直でわかりやすい予告篇が多かったと思うんです」
そのスタイルが変わってきたのが、1970年代。まずは洋画で、本国のものをそのまま流すのではなく、日本人に合った予告篇を作りたいという意識が、映画会社の間に芽生え始めたといいます。
「とはいっても初めは作り方もわからないから、試行錯誤しながらやっていたみたいですね。そうして日本の予告篇を形作ってきたのが、いわゆる予告篇創生期、第一世代の人たち。その中に、佐々木編集室(現在は解散)の佐々木徹雄さん(故人)という方がいらっしゃって、この方が日本で初めて洋画のオリジナル予告篇を作ったそうです。佐々木さんが作られた『グレートハンティング』(1975年)というイタリア映画の予告篇は、すごく評判になって、予告篇を見るために映画館に行列ができたとか」
『人間の証明』『南極物語』......予告篇第二世代の台頭
オリジナルで作った洋画の予告篇が評判を呼ぶなか、日本の映画界も予告篇を専門のディレクターに頼もうという動きが出てきました。
「その頃から映画会社の撮影所がだんだん縮小してきちゃったんですよね。映画会社専属の監督、助監督が減ってきて、作品ごとに契約するというスタイルになっていったんです。それから昔は予告篇を作ることで才能を認めてもらうというのがあったんですけど、そういう流れもなくなってきて。またストーリーを説明するよりも、より印象の強いものが作りたいという声も出てきた。その頃から邦画の予告篇も、専門のディレクターが作るようになりました」
ちなみに前述の佐々木徹雄さんをはじめとした第一世代はたったの4〜5名。小松さんは第二世代に当たりますが、それでも7〜8人。予告篇制作の専門家自体がかなり少ないなかで需要がかなりアップしているのだから、小松さんの24時間缶詰状態(前編参照)も頷けます。そんななか、現在に繋がる邦画宣伝の形を作った作品が登場。
「よく語られるのが『人間の証明』(1977年)ですね。それまで映画でテレビCMというのはあまりやっていなかったんですが、原作本の宣伝を含めて大量にテレビスポットを流してヒットに繋げました。そういう流れの中で今度はテレビ局が映画を作るようになっていくんですが、その最初の作品が『南極物語』(1983年)。日本ヘラルド映画とフジテレビ、さらに出版社など数社が共同で作った映画です。この予告篇は僕がやらせてもらいました」
フジテレビが自局の電波を上手に使って大規模な宣伝活動を行った『南極物語』。25億円といわれる制作費に対して、50億円以上の配給収入を叩き出し大ヒット。
「『南極物語』がヒットしたことで、フジテレビは映画に力を入れるようになったと思うので、今の『踊る大捜査線』などの原点のような作品とも言えますね。今では他のテレビ局もみんな映画を作っていますが、やっぱりフジテレビが一番目立っていますよね。ただいろんな会社が共同で映画を制作するようになると、予告篇に対する要望もいろんな人から挙がってきますから、大変ではありました。『南極物語』は予告篇の制作現場を変えた作品でもあるんです。いろんな人がいろんなことを言うという意味でね」
技術の進歩によって「修正」が増えた(苦笑)
映画がフィルムからデジタルへと変わるのと同じく、予告篇もデジタルへと変わっています。それによっていろんなことがこれまでよりもずっと簡単にできるようになり、さらに予告篇制作現場は変わっていきます。
「例えば映像効果でいうと、オーバーラップやストップモーション、映像に文字をかぶせたりというのが、フィルム時代はそれだけに何日もかかるような、もの凄く大変な作業だったんです。だから映画会社の試写室で宣伝プロデューサーに見てもらう"ラフ"と呼ばれる仮の予告篇は、文字も音も入っていない、画だけのもの。見る方も慣れていないと、善し悪しの判断が難しいものだったんです。つまり関係ない人が見ても何なのかわからないから、口を出せない状況がありました。ある意味、本当に慣れている人だけで作っていたともいえます。それがだんだん技術が進歩してきて、今ではほとんど完成品に近いものが見せられるようになりました。便利なんだけどね、その分僕らの手間は増えたよね。あと誰でも見て判断できるから、いろんな人がいろんなことを言える感じになっちゃった。今だとインターネットで多数の関係者にラフを送れるから、さらにその状況は進んでいますね」
なんと多いときは、ひとつの予告篇に対する修正がかさみ、そのプロトタイプの量は「AタイプからZタイプまでいき、さらにスモールaに突入」ということもあるんだとか。
「映画会社の人には言えないけど、手間と時間はとにかく増えているけど、金額は一緒なので(苦笑)。でもこれは予告篇を作っているすべての人が感じていることだと思います!」
切・実・で・す!

小松さんが思い出に残っている予告篇とは?
さてここで、小松さんがこれまでに手がけた予告篇の中から、特に思い出深いものを聞いてみようと思います。
①『南極物語』 僕にとってのひとつの転機であり、前述の通り苦労したこともあって印象に残っています。
②『死霊のはらわた』 一本立ちし始めた頃は、ちょうどホラー映画がブームで、ホラーの予告篇ばかり作っていました。でも僕、ホラーは基本的に嫌いだったんです。怖いから。夜中にひとりでフィルムを編集していると怖くて仕事が進みません。
③『エルム街の悪夢』 これもいい映画だと思うし、予告篇もそれなりにできたかな。この辺りからはホラー映画が定着して、ホラーっぽい娯楽映画も増えてきた。それで僕自身にもホラーっぽい仕事が増えてきましたね。
④『アメリ』 映画を観て、子どもの頃によく観ていた昔のフランス映画のような雰囲気を感じました。そういう感じが匂うものにしたいなと作りました。若い女性を中心に大ヒットしましたが、そういう人たちを狙って予告篇を作ったわけではなかったのが、逆に良かったのだと思います。若い女性の気持ちは正直わからないから、無理に合わせようとすると、とりとめのないものになってしまうんですよね。たぶんこの頃が僕のピークだったかなと思います。
⑤『おくりびと』 予告篇を作っただけで、アカデミー賞には何も貢献していませんが、授賞式に連れて行ってもらいました。会場には入れなくて、近くのホテルのテレビで中継を観ていましたが、とてもいい経験でしたね。
⑥『ホワイトアウト』 アメリカの予告篇って、作り方が上手いんです。何でもないような短い映像をつなぎ合わせてイメージを作っていくのがものすごく上手い。観客を騙す感じというか、ダイナミックなんですよね。導入部があって、転換して、どうなるんだろうと思ったら、いろんなシーンがバタバタとでてきて印象的な画で終わる。そういうアメリカの予告篇のパターンを、日本映画で実現したのがこの作品です。
ちなみに『アメリ』のヒット以降、小松さんは「アメリの人」として業界から引っ張りだこになったそうです。
「安く買ってきたものが大ヒットしたということで、伝説的な作品になりましたからね。僕のところにも"アメリみたいな予告篇を作ってくれ"という依頼がいっぱいきました。たとえばオドレイ・トトゥの別の作品だと絶対に"アメリみたいに"ってなってくるし、そうじゃなくても"アメリみたいに"ってなってきます。もう"アメリみたいに"というだけで、僕のところに来るんだけども、そう簡単にはいかないですね。違う映画なんだから。さすがに今はもうなくなりましたけどね」

予告篇作りの醍醐味とは?
「予告篇作りには、面白くないものをいかに面白く見せるかというのも要求されるんですけど、だからこそどうしようもない映画ほどやりがいがあるんです。特にホラー系はその代表ですね。全然怖くないものを怖く見せるという。で、騙されて観に行ったという話を聞くと嬉しくてね。それが自分の喜びになっていた部分はあります。ただ、だんだんそれが辛くなってきてね。あんまり騙され続けていると、もう映画館なんて行くもんか!ってなっちゃう人もいると思うから。それで、だんだん騙すことに罪悪感が生まれて、今ではその映画の良さをいかに出していくかということを一番に考えています」
では、予告篇制作に向いている人とはどんな人でしょうか?
「まず一番は、映画が大好きだということですね。ほとんど仕事漬けになっちゃいますから、映画の仕事に就いているというだけで幸せでいられる人かな。あとは我慢強くて、クリエイティブな感覚を持っている人。とはいえ表現欲が強すぎる人は、予告篇よりも映画を作った方がいいです。予告篇はあくまで、人が作った映画をよく見せるための仕事ですから」
最後に、これまでに手がけた予告篇は1000本以上で数えたことがないという60歳の小松さんに、今後の展望を聞いてみました。
「僕の場合は定年はないんだけど、予告篇ディレクターとしての限度はやっぱりあるかなと。年間100本近く作っていた時期もありましたが、その頃みたいに仕事はないですし。映画会社の宣伝も若い人がやっているし、予告篇の若いディレクターも数十人という規模でいるのでね。若い人同士の方が仕事もやりやすいからね。依頼が来る限りはやりますけど、そのうちに来なくなるだろうなとは思っています。でも、そもそも僕は飽きっぽい性格なんだけど、今まで続いて来たのが不思議です」
それはやっぱり、映画が好きだからですか?
「それがなかったら無理でしょうね。ほんとに好きな人しかできないですよ。仕事もきついしね。それに、予告篇制作がすごく地味な仕事であることは、今も昔も変わらない。だけど、僕がこの仕事に就く前は、予告篇を誰が作っているかなんて考えもしなかったけど、今では予告篇制作を志望して応募してきてくれる若い人がいっぱいいます。優秀な人も多いし、やっぱり上手くなってるなと思います。ハリウッドの予告篇に負けないくらいのものになってきていますよ。それに、日本映画の良さを上手く出しているものもあるし。若い人、上手く作ってるな、面白く作ってるなっていうのはたくさんありますよ。『海猿』とかね。興味がないので観にはいかないけどね」
(取材・文/根本美保子)