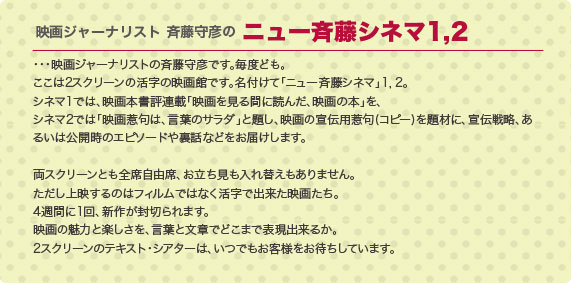第5回 『映画の神さま ありがとう 〜テレビ局映画開拓史〜』〜サブタイトルに偽りなし。テレビ局製作映画の創世記。

- 『映画の神さまありがとう~テレビ局映画開拓史』
- 角谷 優
- 扶桑社
- 18,840円(税込)

- >> Amazon.co.jp
- >> HonyaClub.com
- >> LawsonHMV
☆「定年退職後のお父さんの手柄自慢」とは一線を画す本。
発音するのがいささか気恥ずかしい「映画の神さま ありがとう」がタイトルで、サブタイトルが「テレビ局映画開拓史」か。自分だったら、サブタイトルをメインにするんだけどなあ・・・などと考えたのは、10年ほど前、「テレビ局の作った映画」と題してテレビ局製作映画の歴史と状況・考察を書籍にしようと考え、いくつかの出版社に企画を持ち込んだ経験が僕にあるからだ。結果的に企画を受けて入れくれる出版社はなく(特にテレビ雑誌を出している出版社は、企画書のタイトルだけで断ってきた)、現在に至るまでこの企画書は僕のPCの中に眠っているわけだが、もうそろそろ「テレビ局が作った映画」について、総括すべき時期に来ていることは確かである。彼らが映画を作ることによって、映画産業が大きく地殻変動を起こした。それは紛れもない事実で、そのことはきちんとした証言や事例をもとに、今こそ検証すべきなのである。
フジテレビの映画製作は、著者である角谷優が映画放映枠「ゴールデン洋画劇場」のために、配給各社から放映権を調達するうち「高い金を出して放映権を買うぐらいならば、映画を作ったほうが良いのではないか」と考えたことから始まる。フジテレビが1969年に『御用金』を東京映画と製作した"テレビ局映画創世記"から、80年代に入って『南極物語』『子猫物語』『ビルマの竪琴』等当時のフジテレビの勢いの良さと共に、これらの映画が大ヒットした背景やエピソードが、当事者の筆で語られる。よくある「定年退職後のお父さんがヒマにまかせて書いた、手柄自慢だけの備忘録」とは一線を課す本と言える。
☆「テレビ屋が映画を作るなんて生意気」と、若手スタッフがプロデューサーを殴った時代。
『御用金』が公開されたのが1969年。この時既に映画産業は斜陽化しており、その理由は「テレビが登場して、映像娯楽の王座の座を映画から奪った」とされていた。角谷が、当時フジテレビ社員の五社英雄監督と乗り込んだ『御用金』の撮影現場でも、「テレビ屋が映画を作るなんて生意気だ」と、照明の若手スタッフから角谷が殴られる事件があった(どうも若手スタッフは、別の筋からそそのかされたようだ)。また『もののけ姫』が出てくるまで、日本映画配給収入トップの座にあった大ヒット作『南極物語』についても、企画に惚れ込んだ角谷がフジテレビ上層部に出資を打診するも「そんな危ない企画に金は出せない」と断られ、映画会社からも「犬がウロウロするだけの映画に客が来るか!!」と断られてしまう。にも関わらず角谷は不安要素をひとつひとつクリアしていき、製作基盤を整えてしまうあたりは感動的だ。何よりも重要な製作費の調達は、学研の古岡社長の英断で全体の半額を出資することが決定。残る半分の額をフジテレビが出し、配給はヘラルド映画が東宝と共同で行うことに決定。すべては角谷がコツコツと説得を行った成果であった。
☆『栄光への5000キロ』オンエアの裏側。
大ヒット作『南極物語』の蔵原監督と角谷が、ディープなやりとりをしたのが「ゴールデン洋画劇場」放映用の映画を調達していた時代に遡る。ある年の年末、石原プロモーションの中井専務(当時)から「年内にどうしても5000万円が必要だ。助けて欲しい。担保として『栄光への5000キロ』の放送権を出す」との申し出を受けたことだった。角谷は早速社内で5000万円を調達。大晦日に振り込んだ結果、石原プロは難を逃れる。放映権を入手した『栄光への5000キロ』だが、オンエアするためには監督、脚本家の許諾が必要になる。ところが監督の蔵原も、脚本を執筆した山田信夫も「ノーカットでなければ、オンエアを認めない」と言い張る。困った角谷は一計を案じる。つまり、『栄光への5000キロ』のノーカット完全版を、深夜枠でまずオンエアする。その数ヶ月後、リピートという形で「ゴールデン洋画劇場」で、短縮版を放映というやり方である。この短縮版は角谷自ら本編を再編集し、蔵原監督の了解を得たバージョンだ。この時のやりとりが蔵原監督と角谷の関係性に繋がり、それが元となって『南極物語』へと発展するのであった。
☆あらゆるビジネスの基盤には、人と人との関係性がある。
その後フジテレビの映画製作は、亀山千広(現・社長)の指揮下で、『踊る大捜査線』シリーズ、『海猿』シリーズ、『テルマエ・ロマエ』など大ヒット作を連打。いちやく日本映画ビジネスをリードする立場となるが、角谷の時代に見られた、蔵原監督や市川崑監督といった巨匠たちに救いの手をさしのべる、当時の言葉で言えば「メセナ」的な姿勢であったことに対して、亀山時代の映画製作は企業として営利を得るための、いわばビジネスライクな姿勢が強く感じられる。しかし、いかにビジネスライクな姿勢で作られようとも、1本の映画を企画し製作・配給・興行へと展開するために必要なのは人と人との信頼関係であることを、「映画の神さま ありがとう」は、強く感じさせてくれる。読了した時、ずしりと重いものを感じさせる好著である。
ひとつ欲を言えば、巻末に掲載した「テレビ局映画製作一覧」図表には、テレビ局がイニシアティヴを持って製作した作品、つまり幹事会社を行った作品は、その旨示して欲しかった。幹事会社作品こそ「テレビ局製作映画」と呼ぶに相応しい映画だからだ。
(文/斉藤守彦)