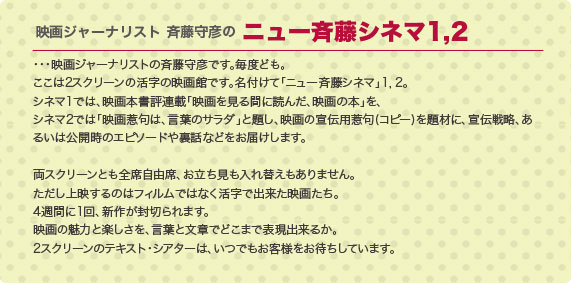第4回 『創造の狂気/ウォルト・ディズニー』 〜拝啓ウォルト・ディズニー様。あなたは......。

- 『創造の狂気 ウォルト・ディズニー』
- ニール・ガブラー,中谷和男
- ダイヤモンド社
- 2,090円(税込)

- >> Amazon.co.jp
- >> HonyaClub.com
- >> HMV&BOOKS
☆『ウォルト・ディズニーの約束』に描かれなかった事実。
3月21日から公開されている『ウォルト・ディズニーの約束』という映画は、ウォルト・ディズニーが『メリー・ポピンズ』を映画化するためにたどった苦難と感動のドラマが描かれた作品だ。映画の中心になるのは、『メリー・ポピンズ』を書いたP.L.トラヴァースから、なんとしても映画化への理解を得ようとする、ウォルトたちスタッフとトラヴァースとのやりとりだ。気むずかしいトラヴァースは、頑として彼らの提案を拒否。ウォルトのアイディアは、ことごとく裏目に出る。「アニメ? アニメはダメ!!」「ミュージカルですって?? 論外!!」「だいたい映画に向いてない」。なぜ彼女がそこまで拒否を続けたのか? 実は『メリー・ポピンズ』には、彼女自身の大切な思いが秘められていた......。
☆ディズニー・サイドの検閲なしに刊行された『創造の狂気』
常々ウォルト・ディズニーという人については、関心を持っていた。星の数ほどの名作アニメやミッキーマウスを筆頭にしたキャラクターで知られるウォルトだが、彼のそうした成功は、いかにして築かれたのか? そして、彼自身はアニメ映画の実製作にどのような形で関わったのだろうか? 『ウォルト・ディズニーの約束』の試写を見て、もう何年も前に入手した本を手に取った。『創造の狂気/ウォルト・ディズニー』という、厚さ3cmほどある本だ。この本を読むことで、もっとウォルト・ディズニーのことを知りたいと思った。ウォルトの評伝は数々出版されているが、本書は著者のニール・ゲイプラーがディズニー・スタジオの全面協力を得ながら、同社の検閲を得ずに刊行されている。昨今ではちょっとしたインタヴューでもそうだが、取材対象たる人は自身の発言内容を活字になる前に確認することを希望する。そしてその、いわゆる「原稿チェック」の際に、取材対象が自分の都合の良いように文章を直しがちだ。また描写対象が故人の場合でも不都合な事実を隠し、ブランド・イメージを守るために遺族や関係者が真実を抹消するケースが、多々ある。だから『創造の狂気』が検閲なしで刊行されたことは、極めて珍しいことなのだ。
☆傷だらけのプロデューサー、ウォルト。
そもそもウォルト・ディズニーという人物を語るに当たって、何かにつけて「愛」「夢」「ファンタジー」といった、情緒的な形容詞が必ず付加される。それが気に入らない。ウォルトは映画製作者であり映画会社の経営者であり、またクリエイターでもある。スタジオジブリで例えるならば、鈴木敏夫プロデューサーと宮崎駿監督を足して2で割ったような人物に違いない。彼が携わった映画は、なるほど「愛」や「夢」に彩られた楽しい作品ばかりだがが、そこに至るまでウォルトがどのようなビジネスを実践してきたのか? その軌跡を追いかけるべく「創造の狂気」を読み始めたが、いやもう、凄まじい限り。幼年期、少年期を経てアニメ作りに手を染めたウォルトは、何とかして質の高い作品を作り、世に出そうと努力するのだが、その理想を実現するためには多額の資金が必要だ。自身の着想をアニメ化するクリエイターであるだけでなく、現実的に作品を製作して上映を実現し、そこから充分な利益を得なければならないプロデューサーでもあるウォルトの苦難の連続は、想像を絶すると言っても良いだろう。
☆ウォルトを助けたチャップリンのアドバイス
ミッキーマウスを出演させた『蒸気船ウィリー』が完成するものの、ユニバーサル、MGMなど大手配給会社に拒否されたウォルトは、フィルムを直接映画館に持ち込み、興行的成功を収める。また『蒸気船ウィリー』は、ミッキーマウスのキャラクター・ビジネスも軌道に乗せる。だが収入のほとんどを新作アニメの製作に費やしてしまうウォルトの姿勢を反映して、ディズニー・スタジオは常に資金難に見舞われていた。そんな中、ウォルトの発案によって、実に3年もの歳月を費やした『白雪姫』が完成する。その出来映えに、誰もが息をのみ、賞賛を惜しまなかった。だが問題は、この傑作をどのような形で公開するかだ。配給会社RKOは海外を含む世界公開を目論み、ディズニーとの契約を迫る。ディズニーとしては製作会社であるが故に、流通・配給面でのノウハウは持っていない。契約はRKOに有利になりがちだ。そこで手をさしのべたのが、チャールズ・チャップリンであった。チャップリンは、自作『モダン・タイムス』の世界配給の実情を示した資料をウォルトに渡し、さらに彼からの相談に応じたという。ウォルトはチャップリンのこの協力に深く感謝し、「あなたの提供してくれた資料は、私たちにとってバイブルでした。それがなければ私たちは、狼の群れの中に放り込まれた羊のようなものだったでしょう」と感謝の言葉を贈っている。
☆ビジネスマン・ディズニーの交渉術。
『ウォルト・ディズニーの約束』でウォルトに扮しているのは、トム・ハンクス。まさにウォルト・ディズニーと聞いて人々がイメージするように、明朗快活にして前向きな映画人の姿を楽しそうに演じているが、そのウォルトがエマ・トンプソン演じるトラヴァースの心を開き、『メリー・ポピンズ』の映画化権を獲得するあたりも、『創造の狂気』では、極めてビジネスライクな書き方で事実を表している。本書によればウォルトが『メリー・ポピンズ』の映画化をトラヴァースに打診したのは1934年で、代理店(これはエージェントという意味だろう)などを通さずに直接彼女に接触するが、両者が映画化について話し合うのは1946年になってから。この段階でウォルトは映画化権の代償を1万ドルと提示し、トラヴァースもそれに同意するが、脚本を原作者が検閲することをウォルトが受け入れずに、破談に終わる。それでもウォルトは『メリー・ポピンズ』の映画化を諦めず、1959年に再度トラヴァースに接触すると、彼女は代理店を通じて75万ドルを要求してきた。さらに彼女は2ヶ月後にロンドンでロイ・ディズニーと会談した際に、10万ドルのギャランティと利益の5%を要求してきたという。強硬な態度を崩さないトラヴァースを軟化させるべく、ウォルトは彼女がスタッフと知り合いになり、スタジオのプレゼンテーションに理解を示すことを期待して、彼女をスタジオに招待する。そこから先を描いたのが、映画『ウォルト・ディズニーの約束』だ。つまり『創造の狂気』を読み終えてから『ウォルト・ディズニーの約束』を見ると、『メリー・ポピンズ』映画化におけるウォルトの行動のみならず、そこに至るまでの人生、アニメ製作やスタジオ経営のプロセスや、その時時の苦悩、喜び、悲しみなどがすべて把握出来るというわけだ。
『創造の狂気』は確かに、ディズニーの人生と仕事ぶりが客観的な視点で描かれた、信頼すべき書籍ではあるが、その日本語訳に関しては映画用語、業界用語や邦題の表記に間違いも複数見られることから、日本語翻訳者の映画産業や映画史についての知識には、疑問が残る。
(文/斉藤守彦)