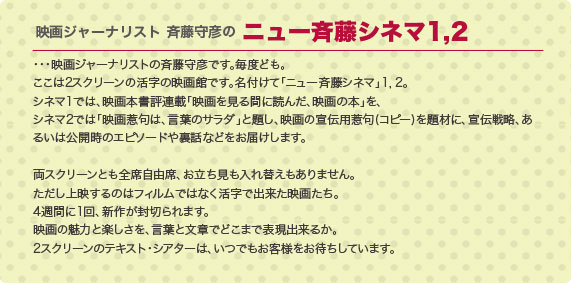第1回 『中子真治SF映画評集成/ハリウッド80's SFX映画最前線』〜ノスタルジーだけで、読んではいけない!!

- 『中子真治SF映画評集成』
- 中子 真治
- 洋泉社
- 4,104円(税込)

- >> Amazon.co.jp
- >> HonyaClub.com
- >> LawsonHMV
☆映画ジャーナリスト・中子真治って誰?
映画ジャーナリスト・中子真治さんの活動を知っている人は、そろそろ50歳に手が届く、そんな年頃だろうか。
1980年代。77年に公開された『スター・ウォーズ』の大ヒットが引き金になり、アメリカ映画界ではSF映画の異常繁殖が始まった。『スター・ウォーズ』のような作品を目ざすのならば、当然そうした技術が必要になってくる。日本では「特殊撮影」=「特撮」と呼ばれていたが、アメリカでは「スペシャル・エフェクツ」。これを「SFX」と称して広めたのが、他ならぬ中子さんである。その中子さん。SF映画の魅力に取り憑かれ、東京で16ミリ・フィルムの収集を開始する。やがてそれだけでは旺盛な好奇心を満たせなくなり、映画作りの現場ハリウッドに単身乗り込み、映画スタッフへの取材をスタート。中でも当時若かったフィルムメーカーやSFXピープルへの取材には熱心で、中子さんの記事によって、アメリカの最新SFX技術や新しい才能が紹介された。その功績は大きい。
☆シンジと仲間たち
組織的バックグラウンドを持たない、フリーのジャーナリストであった中子さんが、いかにして映画製作の現場に潜入したか?
「あなたの仕事に、興味があります。取材させてください」。
極端に言えば、この一言だけが、中子さんのモチベーションであり、そして武器だった。その熱意と行動力を、多くのスタッフが受け入れた。スピルバーグやジョン・カーペンター、リチャード・ドナーといった面々が、彼のインタヴューに応じ、中子さんはそれを『キネマ旬報』『奇想天外』『HOT-DOG PRESS』等に載せ、今一番面白いアメリカ映画は何か、見るべき映画は何なのかを、僕たちに知らせてくれた。特に中子さんが注目したのが、まだ若い監督やSFXアーティストたちの仕事ぶりだ。ドン・コスカレリ、ジョー・ダンテ、ジョン・セイルズ、そしてジェームズ・キャメロン。それだけではない。撮影現場の片隅で働きながら、虎視眈々とチャンスをうかがう、まったく無名なスタッフにも中子さんは取材し、その仕事ぶりを丁寧に紹介してくれた。
☆取材対象との距離感と、深い信頼感。
年齢が近いこともあり、若いスタッフとは取材対象とジャーナリストの関係を超え、プライベートなお付き合いにまで発展するケースも多々あったようで、そうしたエピソードがふんだんに登場するのも、本書の面白いところだ。パッケージ・ツアーみたいなインタヴューを行い、はい書きました、載せましただけの取材では、こうした関係に発展することはない。ここでもやっぱり中子さんの「あなたの仕事に、興味があります」という好奇心と熱意が相手の心を開かせ、思いのたけを語らせるのであった。
僕自身も取材をしたご縁で、映画スタッフとプライベートでのお付き合いに発展するケースが、ちょくちょくある(残念ながら、女優さんとは皆無だが)。だが映画の趣向や世代的共感がマッチしても、結局のところ「取材する立場」と「取材を受ける立場」の関係。時には相手の意にそぐわないことを書かなければならないこともあるし、作品の出来が悪ければ、どう感想を言って良いのか困る時もある。本書での中子さんは、そんな忸怩たるシチュエーションに対して、自身の思いをきちんと伝えている。これは強い信頼関係がなければ出来ないことだ。『ハロウィン』に惚れ込んで取材したまでは良かったが、些細なことで仲違いしてしまったジョン・カーペンター監督の新作『ニューヨーク1997』『遊星からの物体X』には苦言を呈している。ジョンが憎くてそうしているのではなく、この場合は距離を取った上での客観的な評価としてだ。逆に、なんとなく顔見知りだった人間が、取材対象になったケースも。フランシス・コッポラ監督の『ワン・フロム・ザ・ハート』の撮影現場に通ううちに、ちょくちょく顔を合わせ、挨拶をするようになった青年が実はデビッド・リンチ監督で、これが日本人で初めてのインタヴューに繋がったエピソードは面白い。
☆祭りの後の、センチメンタルな時間...。
『中子真治SF映画評集成』は中子さん夫妻と若きフィルムメーカーたちの、公私に及ぶ交流が楽しく綴られており、460ページという大冊ながら、永遠にこの楽しさを味わっていたいと思わせるほどだ。そして登場するジョンやジムが低予算ながら必死に創り上げた『ハウリング』や『宇宙の7人』といった作品を見たくてたまらなくなってしまう。
ところが本書の「第四章 Hollywood Memorandum」では、それまでの楽しさ、賑やかさとは趣を変え、いささかセンチメンタルなタッチで綴られている。この章は6年間のハリウッド生活から日本に帰還した中子さんが、その3年後の時点で書いたものだ。若きSFXピープルとの日々は、ここでは楽しかった過去。現在の彼らはといえば、SFXから本編監督へのデヴューを果たした者、相変わらず昔のSF映画の資料漁りに忙しい者、メジャー大作を手がけたものの、思い通りの作品が作れず、小規模な作品で息を吹き返した監督、そして、エイズで死んでしまった友。自ら命を絶ったシネマショップの店員...。祭りが終わった後の、彼らの生き様が語られる。このくだりは、深い余韻を残す。
☆これは、ひとりのSF青年のライフ・ドキュメントだ
「80年代のSF映画がたくさん出てきて、懐かしかった」だって? その気持ちは分かるけど、懐かしさだけでこの本を読んでもらいたくはない。評論も、インタヴューも、SFXの詳しい技術解説も、作品紹介もメイキングもフィルムメーカーとの交遊録も、この本にはある。でも本書はSF映画が大好きなあまり、ハリウッドに渡ったひとりの青年の、ライフ・ドキュメントだ。すべてのページに、中子さんの「あの時」が刻まれている。そしてこの本は、あの時僕たちが中子さんに抱いた「あなたの仕事に、興味があります。取材させてください」という気持ちへの回答でもあるのだ。
(文/斉藤守彦)