日本の死刑制度とその運用にはどのような問題が考えられるのか? 専門家が徹底解説

- 『死刑について私たちが知っておくべきこと (ちくまプリマー新書 491)』
- 丸山 泰弘
- 筑摩書房
- 990円(税込)
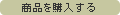
- >> Amazon.co.jp
- >> HMV&BOOKS
突然ですが、皆さんは死刑に賛成でしょうか、反対でしょうか。内閣府の調査によれば、日本では約8割の人が死刑制度に賛成(「やむを得ない」も含む)と答えているそうです。しかし、立正大学法学部教授で刑事政策・犯罪学を専門とする丸山泰弘氏は、こうした疑問を投げかけます。
「改めて考えてみてほしいのが、『果たして、死刑とはどのようなもので、どのように運用されているのか』をよく理解して『死刑存置(賛成)』と答えているか? ということです」
日本の死刑制度を詳しく知らないままに、「なんとなく」や思い込みで賛成、もしくは反対していることはないでしょうか。そこで、「現在の刑事司法にどのような問題があるのか、どのような制度運用ならば死刑が維持できるのか、できないのかを立ち止まって考えてもらいたい」との考えから丸山氏が著したのが、書籍『死刑について私たちが知っておくべきこと』です。
私たちの思い込みの一つに、「被害者感情」というものが挙げられるかもしれません。凄惨な事件の報道を目にすると、私たちは「被害者は極刑を望むはずだ」と考えがちですが、すべての被害者が怒りと復讐の思いにいたるわけではなく、中には「死刑以外の方法で、生きて罪を償ってほしい」と訴える被害者や遺族もいます。
また、事件直後は加害者への厳しい刑罰を望むものの、時間が経過するにつれて、むしろ事件によって崩された日常生活の立て直しのための支援を望む被害者も見られるそうです。刑罰によって被害者感情に応えるだけではなく、「これまで以上に被害者のニーズに沿った、継続的で息の長い支援を行うべき」(本書より)だと丸山氏は記します。
死刑賛成派の意見として「死刑制度には犯罪を抑止する効果がある」というものがあります。しかし、丸山氏いわく「それらを科学的方法によって検証したものはほとんど見受けられない」(本書より)とのこと。ただし、死刑を廃止した地域や国が、廃止する前と後でどのように凶悪犯罪が変動したのかについては知ることができます。
フィリピンではこの150年ほどの間で死刑が廃止され、復活し、再度廃止されていますが、死刑執行が行われている期間でも殺人の件数は高いレベルにあるいっぽうで、1987年の死刑廃止後に殺人事件が大幅に増加することもなかったそうです。韓国については、1997年以降は死刑を事実上廃止していますが、殺人の発生率は減少しているといいます。これらの国を見ただけで全体を語ることはできませんが、単純に「抑止力がある」「抑止力はない」とは言い切れないことがわかるのではないでしょうか。
たびたび丸山氏が断っていることではありますが、本書は死刑に賛成の立場にも反対の立場にも立っていません。死刑制度を存置する国が世界的に少数派となってきている中で、日本ではその実態が広く知られておらず、じゅうぶんな議論もされないままに運用されている点に警鐘を鳴らしています。他にもさまざまな視点から死刑制度について紐解かれている本書。死刑制度に賛成か反対かを考え、さらなる議論をしていく上で、よい判断材料となる一冊です。
[文・鷺ノ宮やよい]











