失敗を避けることに力を注いでいないか? 失敗を学びに変える「成長型マインドセット」の思考法
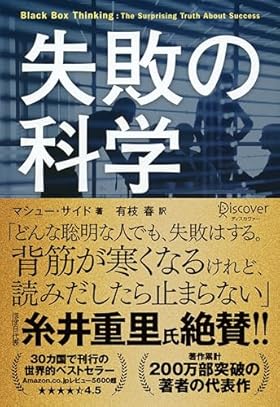
- 『失敗の科学』
- マシュー・サイド,有枝 春
- ディスカヴァー・トゥエンティワン
- 2,090円(税込)
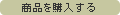
- >> Amazon.co.jp
- >> HMV&BOOKS
失敗から学ぶ――。この言葉を耳にする機会は多いが、実際に失敗するのは怖い。誰かに責められるのではないか、評価が下がるのではないか。自分の無力さを突きつけられるようで、つい目を背けたくなってしまう。
マシュー・サイドの著書『失敗の科学』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)は、こうした人間の心理や組織文化に深く切り込みながら、失敗を学びに変える方法を明快に示している。
冒頭で描かれるのは、安全性を重視する二大業界、「航空」と「医療」の対比だ。航空業界では、事故が起きれば必ず原因が究明され、再発防止策が講じられる。航空機には2つのブラックボックスが搭載されており、膨大なデータから事実が分析される。調査の目的は責任追及ではなく、教訓の抽出。失敗は隠すものではなく、共有すべき資源とされる。
一方、医療業界は異なる。英監査局によれば、回避可能な医療過誤は10人に1人、フランスでは7人に1人にのぼるという。つまり失敗が十分に共有されず、同じ過ちが繰り返されている可能性が高いのだ。
「医療過誤が最も起こりやすいのは、医者に悪意があるときでもやる気がないときでもない。患者のために真面目に仕事に取り組んでいるときなのだ」(本書より)
この指摘は、失敗の原因が個人の資質や努力不足ではなく、組織文化やシステムに潜む構造的な問題にあることを示している。だからこそ、失敗を認めるのは難しい。医療に限らず、日常生活においても失敗を「能力の欠如」と結びつけてしまいがちで、それゆえに強い心理的抵抗を抱いてしまう。
医療現場の複雑さやプレッシャーを思えば、失敗を認めることがいかに困難かは容易に想像できるだろう。著者は医療従事者の誠実さを否定するのではなく、その誠実さゆえに起こる"構造的な罠"にこそ目を向けている。失敗を責めるのではなく、仕組みを問い直す視点が本書の根底にある。
なぜ人は失敗を認められないのか。本書が繰り返し取り上げるキーワードが「認知的不協和」だ。自分の信念や自尊心と矛盾する事実を突きつけられると、人は事実を受け入れるのではなく、歪めてしまう。
「実は、ミスの隠蔽を一番うまくやり遂げるのは、意図的に隠そうとする人たちではなく、『自分には隠すことなんて何もない』と無意識に信じている人たちのほうだ」(本書より)
この逆説には、思わず頷かされる。専門家やリーダーのように強い自負を持つ立場の人ほど、こうした心理に陥りやすい。失敗は自尊心への脅威となり、学びの機会を閉ざしてしまう。さらに、人間の記憶はそもそも不完全で、過去は都合よく再構成されがちだ。いったん歪んだ物語を自分の中に築いてしまえば、そこから抜け出すのは容易ではない。
著者は本書で、医療や航空にとどまらず、スポーツ、司法、ITなど幅広い分野の人々に取材を重ねている。その中には、元イングランド代表のサッカー選手、デビッド・ベッカム氏の名も登場する。彼の成功の裏には、失敗を"欠かせない要素"と捉える姿勢があった。敗北や批判を学びの糧に変えてきた経験は、まさに本書の主題と重なる。
ベッカム氏の姿勢は、まさに「成長型マインドセット」の体現と言えるだろう。失敗を能力の限界と捉える「固定型マインド」とは対照的に、「成長型マインドセット」では失敗を学びの機会として前向きに受け止める。本書の興味深い点は、こうした思考の違いが行動や結果にどう影響するかを多角的に描いているところにある。
「失敗から学べる人と学べない人の違いは、突き詰めて言えば、失敗の受け止め方の違いだ」(本書より)
さらに、本書から浮かび上がるもうひとつの重要な視点がある。それが「マージナル・ゲイン」というアプローチだ。大きな問題を一気に解決しようとするのではなく、細かく分解し、少しずつ改善を積み重ねていく。「わかったつもり」という先入観を手放し、あらゆる方面から検証を試みる。その積み重ねが、前に進むための力になる。
実際、失敗への着目度と学習効果には密接な相関関係があるという。失敗はときに非難を浴び、痛みを伴う。しかし、その痛みから目を背けず、言語化し、共有すること。そこにこそ、成長の芽がある。日常の小さなミスであっても、振り返りの視点を持つことで、見え方は確かに変わってくる。
失敗は、できれば避けたいものだ。しかし、避けることに力を注ぐよりも、向き合い方を変えるほうがずっと建設的だ。本書は、失敗を責めるのではなく、そこから踏み出す勇気にそっと寄り添ってくれるはずだ。











