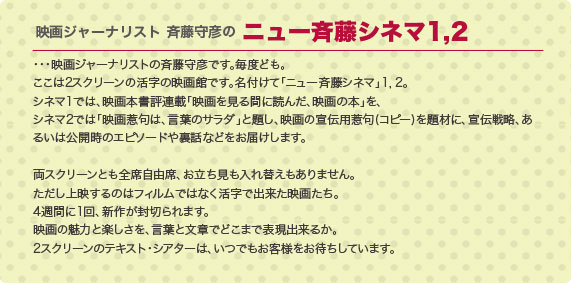【映画を待つ間に読んだ、映画の本】第22回 『スタアのいた季節/わが青春の大映回顧録』〜もと大映宣伝マンが、本当に書きたかったこと。

- 『スタアのいた季節 わが青春の大映回顧録』
- 中島 賢
- 講談社
- 1,944円(税込)

- >> Amazon.co.jp
- >> HonyaClub.com
- >> LawsonHMV
●素敵な人が大勢いた、素敵な時代。
サブタイトルにあるように、本書はかつて存在した映画会社・大映の九州支社宣伝課に永年勤務した、中島賢さんが宣伝マン時代のエピソードを綴った書籍である。最近でも若尾文子の旧作特集上映が多くのファンを集める等、この時代の映画、きちんと作られた日本映画が、今、新しい世代にも受け入れられている。そのまっただ中にいた中島賢さんは、若尾文子を始め山本富士子、京マチ子、中村玉緒、藤村志保、高田美和、江波杏子、渥美マリ、関根恵子、松坂慶子といった美人女優たち、市川雷蔵、勝新太郎、本郷功次郎、田宮二郎といった、まさに日本映画史を飾った大スターたちと、同じ時間を過ごした方だ。
当時の俳優たちは今のように芸能プロダクションに所属していたりフリーランスではなく、映画会社の社員や専属契約を交わした契約者という立場であった。同じ大映に所属する中島さんは、彼らが出演した映画の宣伝を手がけることはもちろん、スター俳優たちの話題なども、新聞や雑誌に売り込んで、なんとか映画のヒットに繋げようとする。言わば「同じ釜のメシを食った仲間」の関係であるのだ。九州に来る度に、京マチ子の大好物である「ふくやの辛子明太子」をおみやげにすべく買いに行かされたり、旅先のガイドに惚れてしまった若尾文子の恋愛相談に乗ったり、クール・ビューティー藤由紀子と雀卓を囲んだところ、「この野郎!!」「ちくしょう!!」と、男勝りの声を上げて驚いたとか、市川雷蔵の『眠狂四郎』シリーズに花を添える、通称"狂四郎ガールズ"を劇中で全裸のように見せかけるための仕掛けだとか、映画作りの裏側の楽しさと、中島さんと俳優たちの交流などが、豊富なスナップ写真と共に語られるあたりは、まさしく「素敵な人が大勢いた。素敵な時代」(本文より)の記録だ。
●カリスマ経営者・永田雅一の真の姿。
実は本書の刊行直後、著者の中島賢さんとフェイスブックで知り合うことが出来、メールで色々なやりとりをさせてもらった。そして、この本を読んで僕が気になっていることを、ズバリ聞いてみた。
「この『スタアがいた季節』というタイトルは、中島さんが命名されたのですか?」。
中島さんの回答は、「いくつかの候補の中から、最終的には出版社が決めるということで、私が了承したものです」とのことだった。
書籍のタイトルはすべて著者の意向で命名されるもの、と思っている方も多いだろうが、それは違う。書籍は著者にとって作品だが、それを刊行する出版社にとっては「商品」である。世に出す以上は1冊でも多く売りたい。無論著者としても、たくさん売れれば増刷になって印税も増えるから、このあたりに異論はない。だが時として、著者が思いを込めたタイトルと、出版社の意向が食い違うことがある。この場合も当初中島さんが出したタイトル案は「わが青春の大映回顧録」「永田ラッパと豪傑どもと女優たち」だったという。前者はサブタイトルに反映された。後者はかなり強いインパクトを残す。
このタイトル案に掲げられている「永田ラッパ」こそが、中島さんが所属した大映のカリスマ経営者・永田雅一に他ならない。本書の第3章の主役とも言える永田社長は、「ラッパ」の異名を取った人物だ。スケールの大きな構想や大言壮語を、次々にブチ上げていく、その様は当時の日本映画界の名物でさえあった。だが大映を倒産に導いたのもこの永田社長であり、経営者としては「一時代を築いた人物ではあるが、大手映画会社を潰した男」というのが、今日での一般的な評価だ。中島さんは、内部から見た永田社長の言動が、そうした評価と異なっていることを、本書ではっきりと指摘している。例えば、そのニックネームである「ラッパ」だが、永田社長本人によれば、「オレのラッパは進軍ラッパだ」と言ったそうだ。つまり「社員は俺を先頭にして、一丸となって進軍していこうと言って鳴らす進軍ラッパなんだ」という意味で、現に永田社長は大映が経営危機に陥った時でも「最後は俺が責任を持つから、おまえたちは俺の名前を利用して思う存分仕事をやれ! まだ俺の名前は使えるから」と言い放ったという。株主の突き上げを恐れて、都合の悪いことは部下の責任。自己保身に凝り固まったような、今日の経営者に100億回聞かせたいフレーズだ。
●日本映画史の汚点「五社協定」の真意。
永田社長が当時主導し、松竹、東宝、東映、日活と大映が交わした「五社協定」なる取り決めについても、中島さんは「五社協定こそが大映崩壊への第一歩であった」と、その行いに対して厳しく断を下している。この協定は自社の専属俳優が、他社作品に出演をすることを制限し、「お互いに俳優の貸し借りはしない」ことを五社の社長間で決めた協定だった。
当時大映に所属していた山本富士子は大映との契約期間中に、東宝作品に出演しようとして永田の怒りを買い、解雇されてしまう。問題はそこからで、フリーとしてどこの映画会社の作品でも出演出来る立場になったにも関わらず、協定を楯にどの会社も彼女を受け入れることを拒否したというのだ。このあたり、自分たちが不利と見るや徒党を組み、もとから持っている排他性をさらに強め、その責任を曖昧にしてしまうのは、今日に至るまで、我が国映画会社の恥ずべき伝統と言える。そして山本富士子は大映退社後、今日まで映画出演をしていない。1983年に市川崑監督が『細雪』の長女役に彼女の出演を切望し交渉を重ねたが、山本の意思は変わらず、結局長女役は岸惠子が演じることとなった。
もうひとり、五社協定の犠牲になったのが田宮二郎で、1968年公開の大映作品『不信のとき』での序列(どの俳優がトップにクレジットされるか)をめぐり、ポスターなどのそれがおかしいと異論を唱えた。田宮は作品内容から判断して、自身が主役に相応しいと永田社長に直訴するも、これまた永田の怒りを買い、解雇されてしまう。そしてそんな田宮に手をさしのべる映画会社はなく、やむなく彼はテレビに進出し、「クイズ・タイムショック」の司会などを務めることになる。
永田社長が言い出しっぺである五社協定が、ふたりの犠牲者を出してしまったことは事実だが、今回中島さんの書籍では「では永田社長は、なぜ五社協定を推進したのか?」について、部下の目から描いている。それによると「永田雅一が最も懸念したのは、俳優や監督が無理な掛け持ちをしたために現場が混乱し、映画の質が落ちることだった。それを防ぐために、専属契約や本数契約をしている者の名簿を五社まとめて作り、お互いガラス張りにして交渉出来る仕組みを作った」とし、特に「多大な労力とお金をかけて育てた若手を他社かがさらってゆくのでは、新人育成への情熱がなくなる。だから、新人養成年限中はお互い手をつけないと約束しようという条項を加えた。これがそもそもの五社協定だった」と述懐する。
日本映画史の汚点と言える五社協定だが、永田が本来目ざしたのは個々の作品のクォリティの維持と、新人俳優の養成を円滑に行うことにあったのだ。このことが、当時の様子を知るインサイダーから発せられたのは、大変に意義のあることである。本書は単に宣伝マンが俳優たちとの交流を回想したものではなく、永田雅一という希有な資質と行動力、ワールドワイドな視野を持った経営者の、真の姿を描写した点で、日本映画史に一石を投じた書籍である。
もし次に機会があったならば、中島さんの手による永田雅一伝を、ぜひとも読みたいものだ。
(文/斉藤守彦)