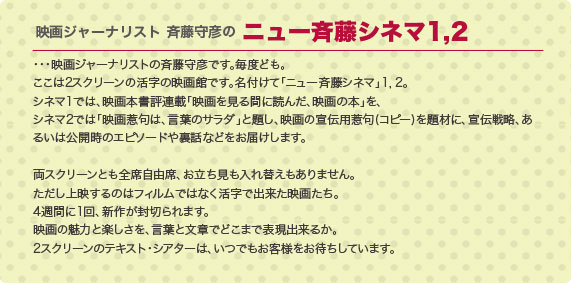【映画惹句は、言葉のサラダ】第5回 ミニシアター作品の惹句は、進化していると思えない。
![セックスと嘘とビデオテープ [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51eShWL2pfL._SX400_.jpg)
- 『セックスと嘘とビデオテープ [Blu-ray]』
- Happinet(SB)(D)

- >> Amazon.co.jp
- >> LawsonHMV
●人の心と脳に溶け込む、カルピスの原液のような惹句。
ふと思いついて、ミニシアター作品の宣伝用惹句を振り返ってみた。ミニシアターというか、いわゆる単館ロードショーですね。現在では純粋に1館だけでロードショー公開する作品は少なく、シネコンの中の1スクリーンとミニシアターとの、所謂「単館拡大」と呼ばれる興行形態が多いわけですが、80年代半ばから90年代末あたりにかけては、この単館ロードショーがブームを呼びました。どんなブームかといえば、まず映画を上映する映画館に注目が集まったわけです。例えば歌舞伎町にあった、昨年12月26日に閉館したシネマスクエアとうきゅう。ここなどは場内に設置した座席が当時としてはゴージャスで、この座席に座って作家性の強い、拡大公開されない映画を見ることがとてもオシャレという、一種の風評を形成したわけです。
そういう特殊な映画館で上映される作品ですから、宣伝に使われるチラシや新聞広告の類いも、全国公開されるハリウッド映画とは異なる方法論が用いられました。それまで映画惹句が心がけてきた「映画館にお客さんを、何としても向かわせよう」という姿勢を前面に出さない。惹句と言うよりコピー。惹句とコピーがどう違うかと言えば、惹句とはまさしく「惹きつける句」ですから、その目的は商品を売ること。映画の場合なら作品の存在とセリング・ポイントを強くアピールし、なんとか映画館に来させようという強い姿勢が反映されているもの。対するコピーは、イメージを伝達するための言葉で、その言葉をどう解釈するかは、大衆の主体性に委ねられます。
例えば1989年12月に公開された「セックスと嘘とビデオテープ」の惹句も、どちらかと言えばコピー風です。
「恐いほどナイーブな深層心理の再生。」
この場合、邦題そのものがコピー的な役割を果たしています。「セックス」「嘘」「ビデオテープ」という、まったく異質な3つの語句を並べることによって興味を引く。映画を売るための惹句も同様に「ナイーブ」「深層心理」「再生」と、3つの異なった印象を持つ語句をひとつの文章にし、その違和感から作品のイメージを形成するという手段を用いているのです。つまり、ミニシアター作品の惹句あるいはコピーとは、そのフレーズが即集客に結びつくのではなく、いったんチラシなり広告を見た人たちの心の中に溶け込み、脳内でイメージを膨らませることで、鑑賞意欲を高めるという方法をとっているのです。秋元康風に言えば、「カルピスの原液」のようなものです。
●今は亡きフランス映画社の名惹句。
ミニシアターがブーム化した1988年に、シャンテシネ2で26週間というロングラン記録を打ち立てたヴィム・ヴェンダース監督の「ベルリン・天使の詩」。この映画を配給したのは、昨年惜しくも倒産してしまったフランス映画社。ことミニシアター・ブームを語る上で無視出来ないのがこの配給会社の存在で、ここの宣伝材料に刻まれた惹句は、単に散文的な言葉でイメージを喚起するだけでなく、作品の輪郭をより鮮明にするための解説的フレーズも込められています。「ベルリン・天使の詩」の惹句がこれ。
「空のむこうの弦の響き
地に湧きあがるロック
愛に死んでいく天使がいる−
たぐいまれな詩情
全世界絶賛の傑作!」
この配給会社の惹句の特徴は、「詩情」「叙情」といったフレーズがよく使われること。そういう言葉の使い方が洗練されたアートワークとリンクして、知的な雰囲気を醸し出していました。
●「●●監督最新作!!」という惹句は、違うだろう。
ではここで、最近公開されたミニシアター作品及び単館拡大作品の惹句を見てみると、前述したミニシアター・ブーム時代と比べて、大きな変化は見られません。提示したイメージを受け手の中で熟成させていくという、宣伝の方法論は健在のようです。
「何度もやめようと思った。
でも歩き続けた。
人生もおんなじだ。」
(「わたしに会うまでの1600キロ」)
「さあ、人生のホームワークを始めよう。」
(「ヴィンセントが教えてくれたこと」)
このあたりは、うまいフレーズを使うものだなあ、と感心するのですが、中にはこんな惹句がチラシに大きく書かれている作品もあります。
「第68回カンヌ国際映画祭〈監督賞〉受賞」
(「黒衣の刺客」)
「『ぐるりのこと。』『ハッシュ!』橋口亮輔監督
7年ぶりの長編最新作」
(「恋人たち」)
よくハリウッド映画などに使われる「●●監督最新作!!」「●●映画祭にて●●賞受賞!!」という惹句のパターンは、公開規模が大きな作品であれば不特定多数に対して効果を上げますが、特定少数の観客をターゲットにするミニシアター作品の場合、こうしたアプローチはむしろ作品の個性を埋没させてしまい、陳腐なイメージだけが印象に残る危険性を孕んでいます。これはやっぱり、違うだろうと言わざるを得ません。
(文/斉藤守彦)