「労働」とは何か
都会であくせく働く人と、南の島の漁師の会話の小噺(こばなし)をきいたことはありませんか。「そんなに必死に働いて、貯めたお金で何をするの?」「引退したら昼寝しながら、のんびり魚釣りでもして暮らしたいからね」「ぼくはもうそれをしているよ」──。
私たちはいったい何のために働いているのでしょうか。小噺に登場する漁師は「働いていない」のでしょうか。本稿では、経済思想家、大阪市立大学准教授の斎藤幸平(さいとう・こうへい)さんと共に「労働」について考えてみたいと思います。
* * *
人間は、他の生き物と同様に、絶えず自然に働きかけ、様々な物を生み出しながら、この地球上で生を営んできました。家、洋服、食べ物などを得るために、人間は積極的に自然に働きかけ、自然を変容し、自らの欲求を満たしていきます。こうした自然と人間との循環的な過程を、マルクスは生理学の用語を用いて、「物質代謝」と呼びました。そして、自然を規制し、制御する行為こそが、「労働」だとマルクスは考えたのです。
マルクスが『資本論』に託したメッセージの核心に迫る上で、特に重要なのが、第一巻・第五章第一節「労働過程」で展開されるこの「物質代謝論」です。これを理論的土台として『資本論』を読み進めていきましょう。
労働は、まずもって、人間と自然とのあいだの一過程、すなわち、人間が自然との物質代謝を自らの行為によって媒介し、規制し、制御する一過程である。(193)
都市で暮らしていると忘れてしまいがちですが、インスタントラーメンもパソコンも、自然に働きかけることなしに作ることはできません。自然との物質代謝は、人間の生活にとって「永遠の自然的条件」だとマルクスは述べています(198)。
つまり、自然との物質代謝を離れて生きることはけっしてできない、ということです。もちろん、人間だけでなく、地球上のあらゆる生き物が、自然との物質代謝を行いながら生きています。人間が森から木を伐り出して家を作るように、熱帯地域のシロアリは人間も真似をするような、内部の温度をほぼ一定に保つ空調の仕組みも整った立派なアリ塚を作ります。
けれども、人間と他の生き物との間には、決定的な違いがある、とマルクスは述べます。それは、人間だけが、明確な目的を持った、意識的な「労働」を介して自然との物質代謝を行っているということです。
人間は、単に本能に従って自然と関わっているのではありません。本能を満たすための工夫は他の動物でも行います。ハキリアリはキノコを育てるし、道具を使う動物もいます。
しかし、暖をとるだけなら服を作れば十分ですが、人間は「よりきれいな服にする」目的のために、染料で服を染めます。食事をするための土器なら器があれば十分ですが、祭事や遊びなど本能以外の目的のために人形を作ったりしてきました。「労働」という行為によって、人間だけがほかの生き物よりもはるかに多様でダイナミックな“自然への働きかけ”ができるのです。
その際、人間と自然との物質代謝は循環的で、一方通行で終わるものではありません。自然に還らないゴミを大量に出し続ければ、例えばマイクロ・プラスチックを食べた魚が私たちの食卓に戻ってきます。核のゴミも問題ですし、化石燃料の大量消費による二酸化炭素排出も、深刻な気候危機を引き起こしています。私たちの暮らしや社会は、私たちが自然に対してどのような働きかけをしたかで決まる。これがマルクスの、資本主義社会を分析する際の基本的視座です。
つまり、マルクスは、人間の意識的かつ合目的的な活動である労働が資本主義のもとでどのように営まれているかを考察することで、人間と自然の関係がどう変わったかを明らかにし、そこから資本主義社会の歴史的特殊性に迫ろうとしたのです。
■『NHK100分de名著 カール・マルクス 資本論』より
私たちはいったい何のために働いているのでしょうか。小噺に登場する漁師は「働いていない」のでしょうか。本稿では、経済思想家、大阪市立大学准教授の斎藤幸平(さいとう・こうへい)さんと共に「労働」について考えてみたいと思います。
* * *
人間は、他の生き物と同様に、絶えず自然に働きかけ、様々な物を生み出しながら、この地球上で生を営んできました。家、洋服、食べ物などを得るために、人間は積極的に自然に働きかけ、自然を変容し、自らの欲求を満たしていきます。こうした自然と人間との循環的な過程を、マルクスは生理学の用語を用いて、「物質代謝」と呼びました。そして、自然を規制し、制御する行為こそが、「労働」だとマルクスは考えたのです。
マルクスが『資本論』に託したメッセージの核心に迫る上で、特に重要なのが、第一巻・第五章第一節「労働過程」で展開されるこの「物質代謝論」です。これを理論的土台として『資本論』を読み進めていきましょう。
労働は、まずもって、人間と自然とのあいだの一過程、すなわち、人間が自然との物質代謝を自らの行為によって媒介し、規制し、制御する一過程である。(193)
都市で暮らしていると忘れてしまいがちですが、インスタントラーメンもパソコンも、自然に働きかけることなしに作ることはできません。自然との物質代謝は、人間の生活にとって「永遠の自然的条件」だとマルクスは述べています(198)。
つまり、自然との物質代謝を離れて生きることはけっしてできない、ということです。もちろん、人間だけでなく、地球上のあらゆる生き物が、自然との物質代謝を行いながら生きています。人間が森から木を伐り出して家を作るように、熱帯地域のシロアリは人間も真似をするような、内部の温度をほぼ一定に保つ空調の仕組みも整った立派なアリ塚を作ります。
けれども、人間と他の生き物との間には、決定的な違いがある、とマルクスは述べます。それは、人間だけが、明確な目的を持った、意識的な「労働」を介して自然との物質代謝を行っているということです。
人間は、単に本能に従って自然と関わっているのではありません。本能を満たすための工夫は他の動物でも行います。ハキリアリはキノコを育てるし、道具を使う動物もいます。
しかし、暖をとるだけなら服を作れば十分ですが、人間は「よりきれいな服にする」目的のために、染料で服を染めます。食事をするための土器なら器があれば十分ですが、祭事や遊びなど本能以外の目的のために人形を作ったりしてきました。「労働」という行為によって、人間だけがほかの生き物よりもはるかに多様でダイナミックな“自然への働きかけ”ができるのです。
その際、人間と自然との物質代謝は循環的で、一方通行で終わるものではありません。自然に還らないゴミを大量に出し続ければ、例えばマイクロ・プラスチックを食べた魚が私たちの食卓に戻ってきます。核のゴミも問題ですし、化石燃料の大量消費による二酸化炭素排出も、深刻な気候危機を引き起こしています。私たちの暮らしや社会は、私たちが自然に対してどのような働きかけをしたかで決まる。これがマルクスの、資本主義社会を分析する際の基本的視座です。
つまり、マルクスは、人間の意識的かつ合目的的な活動である労働が資本主義のもとでどのように営まれているかを考察することで、人間と自然の関係がどう変わったかを明らかにし、そこから資本主義社会の歴史的特殊性に迫ろうとしたのです。
■『NHK100分de名著 カール・マルクス 資本論』より

- 『カール・マルクス『資本論』 2021年12月 (NHK100分de名著)』
- 斎藤 幸平
- NHK出版
- 599円(税込)
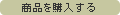
- >> Amazon.co.jp
- >> HonyaClub.com
- >> HMV&BOOKS














