ラクダ・そり・ベビーカー、飲酒運転として罰せられるのはどれ? 世にも奇妙な法律の世界を弁護士が紐解く

- 『世にもふしぎな法律図鑑』
- 中村真
- 日経BP 日本経済新聞出版
- 1,980円(税込)
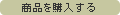
- >> Amazon.co.jp
- >> HMV&BOOKS
私たちの暮らしに大きく関わっている"法律"。社会が機能するために必要不可欠ではあるものの、法律自体は決して万能ではない。世の中の理不尽な出来事に対して、「どうして法律で裁けないの?」と感じることは多々あるだろう。一方で、「こんなことが法律違反になるんだ」と驚くケースも少なくない。今回紹介する『世にもふしぎな法律図鑑』(日経BP 日本経済新聞出版)を読むと、法律の不思議かつ興味深い側面が見えてくる。
同書の著者である中村 真氏は、法律の専門家である弁護士。彼曰く、日常で触れる機会の多い法律には、ときに不思議な解釈が可能な場合があるという。そのひとつが道路交通法だ。
「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」という文言は、飲酒運転防止の標語として世代を問わず広く知られているだろう。道路交通法65条1項においても「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」とあり、違反者に対しては罰則が定められている。
ではここに、ラクダ・そり・ベビーカーと3つの"乗り物"があるとしよう。酒気を帯びた状態の人がこれらを運転したとき、飲酒運転として罰せられてしまうのはどれだろうか? このようなケースでは、法律を細かく紐解いていくと答えが見えてくる。
今回注目すべきは、道路交通法で罰則対象となる"車両等"という文言が何を指しているのかだ。自動車や原付などはもちろん含まれるが、ここでカギを握るのが"軽車両"である。
「これには様々な運搬具が含まれるのですが、中心的なものを挙げると『自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車を除く。)』とされています。
そりで滑ったり、牛や馬に直接跨ったりしたとしても「軽車両」に当たってしまいます。乗馬や乗牛(?)も酒気を帯びて行うとたちまち道交法違反です」(同書より)
つまりそりは、飲酒運転に該当する可能性があるのだ。またラクダについては明確に示されていないものの、中村氏曰くラクダも哺乳類ウシ目ラクダ科であるため、同じく軽車両として扱われる可能性が高いという。
残るベビーカーについては、一見すると問題ないように見える。しかし中村氏は、「乳母車の乳幼児を乗せる車体部分全部を取り除き、車輪・車台・押す把手の部分のみとし、車台の上に板片2枚を載せる改造を施した上で高齢女性が手押ししていた改造手押車」が軽車両に当たるとされた過去の裁判例に言及。
「これが軽車両に当たるのであれば、酒に酔ってそのような改造手押車を押しているとやはり検挙されるおそれが出てきます」(同書より)
例えベビーカーであっても、その様相が一般的ではなければ飲酒運転になってしまう可能性はゼロではないようだ。
「結局、四輪、二輪、自転車、牛馬(そしてラクダ)を問わず、酒で判断力・身体機能の低下した状態では適切に制御ができなくなる乗り物に乗ることは、酒酔い運転の対象になると考えておいた方がよさそうです」(同書より)
さらに法律の不思議な部分が垣間見える事例として挙げられるのが、葬式の場面。実は和尚による"お説教"に対して茶々を入れると、「説教等妨害罪」に問われてしまうことをご存じだろうか?
「具体的な手段や方法を問わず、およそ説教等に支障を生じさせる行為であれば該当してしまいます。例えば滔々と語る和尚様の有り難いお話にツッコミや横やりを入れるのはまさしく『妨害』です。
この罪では、説教だけでなく礼拝や葬式も妨害罪成立の対象とされていますが、いずれも実際に説教や礼拝、葬式が停滞したり中止されたりすることまでは求められていません。ここで法が守ろうとしているのは、主宰者(和尚様など)の宗教活動の自由だけでなく、例えば参列者が説教や礼拝を通じ、平穏な気持ちで故人を偲び信仰する神仏に思いを馳せる利益も含まれるとみることができます」(同書より)
ちなみに説教等妨害罪に該当すると、罰則として1年以下の懲役もしくは禁錮、または10万円以下の罰金が科されてしまうという。なお説教中に和尚の頭を叩くなど「威力や偽計」によって妨害した場合は、業務妨害としてより重い罪に問われてしまう可能性もあるようだ。
「ピンと張り詰めた法事の空気の中のふとした緩和に面白みを感じてしまうのは人の背負った業のようなものですが、こと葬儀や法要の際には一線を踏み越えないよう注意が必要です」(同書より)
知っているようで知らない不思議な法律の世界。同書を一読すれば、難解なイメージの強い法律が少し身近なものに感じられるかもしれない。











