プロ野球誕生の歩みはまさに戦争そのもの 礎を築いた122名の選手の戦場記録

- 『プロ野球選手の戦争史 ――122名の戦場記録 (ちくま新書 1788)』
- 山際 康之
- 筑摩書房
- 1,210円(税込)
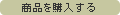
- >> Amazon.co.jp
- >> HMV&BOOKS
東京ドームに鎮魂の碑があることをご存知だろうか。そこには、戦没した野球選手の名が刻まれている。昭和11年2月のプロリーグ発足とほぼ同時に日本は戦争へとなだれ込み、野球界もその戦禍に巻き込まれていったのだ。戦地では手柄を立てる者がいる一方、病死する者や飢餓に苦しむ者、特攻に志願する者など、人生の数だけ戦争の記憶があり、幾多の悲劇がある。プロ野球の草創期は、まさに戦争の歴史そのものといっても過言ではない。
『プロ野球選手の戦争史 ――122名の戦場記録』(筑摩書房)では、122名のプロ野球選手たちによる戦場や軍隊生活の体験記録が、日中戦争から太平洋戦争に沿って書き留められている。著者の山際康之氏は、プロ野球の礎を築き、そして犠牲になった人々を書き残しておくために、同書の執筆に取り組んだという。
そもそも当時職業野球と呼ばれたプロ野球の誕生は、昭和6年と9年に開催された日米野球がきっかけであった。投手に贈られる「沢村賞」としても現代に名を残している巨人軍の名投手・沢村栄治は、圧倒的な強さの全米チームに対して、弱冠17歳ながら圧巻の球を投げ込んだ。しかし、最高殊勲選手賞が授与された2日後、沢村は徴兵検査を受けることとなった。
「徴兵検査は兵役としての意味だけではなく、世間から一人前の男として認められる元服の式でもあった。合格すれば立派な大人への仲間入りである。
検査に立ちあった大佐は沢村の大のファンだということで、『軍隊へ行っても肩の心配はいらんぞ、しっかりお国のために奉公してこい』と太鼓判を押した。合格といわんばかりの激励である」(同書より)
大ファンならば国への奉公ではなく球界での活躍を望むのではないか。今の時代を生きる我々の中には、そう考える人が多いだろう。当時、戦争が生活の一部であった人々との価値観の違いを思い知らされる。そして昭和13年1月10日、沢村は入営の日を迎えた。ほどなくして野球専門雑誌の取材を受け、「軍人としての天職に向かって邁進するのが僕の使命」(同書より)と軍隊口調で答えたという。自殺者や脱走者も出るほどの軍隊生活の中で、知らず知らずのうちに若者たちの思考は徹底的に破壊され、軍への服従だけが刷り込まれていった。
沢村は徐州会戦で軽機関銃手として初出征した。戦場では銃弾が尽きると、かつて職業野球選手だったことを知る戦友たちから手榴弾を次々に渡され、狙いを定めて制球力を披露。手元の手榴弾が尽きると、相手から投げ入れられた手榴弾を即座に投げ返して敵陣をさく裂させた。沢村は昭和14年8月に帰国し除隊したが、日中戦争を戦い抜いた後の沢村の球を受けた捕手の多田は、その変容ぶりに驚きを隠せなかったという。
「その様相は、目はつりあがり血走って鬼気迫るもので、近寄りがたい雰囲気を漂わせていた。多田は直感的に戦争で人を殺してきた人の目だと思った」(同書より)
早く試合で投げたいという想いとは裏腹に、練習不足、軍務や訓練中でのけがや蓄積疲労に肥満、さらには戦地での感染症や病気と、沢村の復調までの道のりは遠かった。しかし実は、沢村は5年越しの恋を実らせて結婚し、幸せの絶頂にあったのだ。そこに水を差したのは2度目の召集の知らせであった。
「軍にとっては個々の事情など関係ない。再び出征することになった沢村は妻に心配させまいとして、『わしゃ運が強いから敵のタマには当たらん』ということばを残して家をあとにした」(同書より)
今度の敵は、比島を統治する米軍とミンダナオ島に常駐する比軍である。大リーグ選手を相手に投げた日米野球大会や二度にわたる米国遠征など、野球を通じて米国から大きな学びを得ていた沢村。しかし米軍の卑怯で残忍な戦いぶりから、米国への憎しみは増大するばかり。もはや、米国への尊敬の念などはなくなってしまった。
比島から帰還した沢村は、選手の徴兵回避のための工員への偽装案に応じ、川西航空機の工場で飛行機の部品を作る工員となった。しかし、選手の招集や退団が続き混乱する巨人軍からは突然の解雇通告を受けてしまう。その後も球団に呼び戻されることはなく、昭和19年に「もう一度野球をやってみないか」と沢村に手を差し伸べたのは恩師の三宅大輔。このときは誘いに対して答えを出すことなく三宅の宿舎から帰宅した沢村だったが、ほどなくして沢村のもとには3度目の召集が舞い込んだ。
「父との別れの時がやって来ると、これまで語らずにきた悔しい気持ちを一気に吐き出し、巨人軍に解雇されたことを涙ながらに告白した。いつかきっとマウンドに立って見返してみせる、そんな心境だったに違いない。三宅のもとにも、『こんど戦争から帰って来たら、あの話の返事をします』と書いたハガキを残している。望みは捨てていなかった」(同書より)
昭和19年12月、球界を席巻したエースは米軍からの攻撃を受け、その生涯を閉じた――。戦地で散った野球戦士たちの悔恨はどれほどだったであろうか。
先駆者たちのプレーは、もう観ることができない。しかし不幸を繰り返さないために、決して忘れてはならない。そして記憶に刻み、語り継がなければならない。同書はその一翼を担う存在である。











