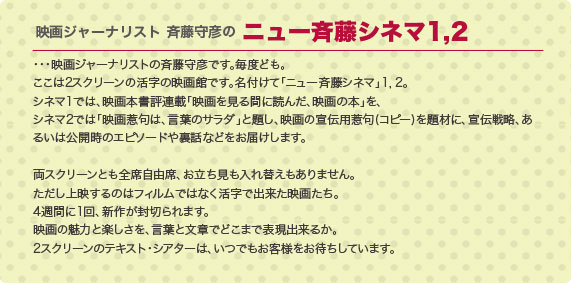【映画を待つ間に読んだ、映画の本】第41回『洋ピン映画史/過剰なる『欲望』のむきだし』〜まさに博覧強記。大衆娯楽の栄枯盛衰を探った傑作。

- 『洋ピン映画史(仮) (えろこれ)』
- 二階堂 卓也
- 彩流社
- 3,240円(税込)

- >> Amazon.co.jp
- >> HonyaClub.com
- >> LawsonHMV
●「商品」としての価値をはっきりさせ、
その「大衆娯楽」性に深い愛情を注ぐ姿勢。
「洋ピン」という呼び方にも、今や解説が必要だろう。つまり外国製のアダルト映画のことを言うのだ。我が国の配給会社の手で輸入され、映画館にかかった時には「成人指定」=18歳未満は鑑賞不可能となるケースが多く(このレイティングは70年代半ばから、細分化していくが)、即ち外国で製作されたピンク映画であることを意味する「洋ピン」なる呼称が定着したのである。
その洋ピンが盛り場の映画館に登場し、絶滅するまでを描いた「洋ピン映画史」。これは凄い本だ。まさに「映画史」の名にふさわしい、そのジャンルがいかに認知され、いかに多くの観客を集め、いかに盛り上がりを見せ、そしていかに淘汰されていくかを、著者の二階堂卓也氏は、溢れんばかりの知識と情熱で描いている。それも並大抵な知識ではない。例えばこうだ。1972年にアメリカで公開され、クリトリスが喉の奥にあるという、その奇抜な発想でヒット。75年に日本公開された『ディープ・スロート』についての項。「もともと、この映画は日本での上映は無理と言われていた。当初はニューヨークやサンフランシスコなどの大都市以外では上映禁止になっており、海外配給もポルノ解禁国たるスウェーデンとデンマークにとどまっている。それをあえて東映洋画が買い付けたのは新興の会社として業界にひと泡吹かせてやろうという意気込み、あるいは一か八かのギャンブル精神もあったろう。これもバックが東映という大会社であったればこそ」。
このように、単に『デイープ・スロート』という作品内容だけを語るのではなく、その作品が日本で公開された背景や、経緯についても疎かにしない。そして劇場公開された際に、どの程度の興行収入、配給収入をあげたかを、作品の商業的成否としてきちんと判定しているあたりは素晴らしい。なぜならこうした洋ピンは、「商品」として成立しているわけで、その価値はいかに商業的な成果を収めたかで決まる。そしてそこから、二階堂氏が洋ピンを大衆娯楽としてこよなく愛している姿勢が見て取れるのだ。
●「俗」であることの気高さとプライド。
それ故本書から感じられるのは、洋ピンのみならず映画とは商品であり、それは評論家のためではなく、何よりも観客を楽しませるために存在するのだという、揺るぎない信念だ。時折日活ロマンポルノを語る、年の頃なら60歳ぐらいの初老の人にありがちなのが、スケベを目的に映画を見に行ったにも関わらず、その監督が後年何かで注目されたりすると「オレはこいつのデビュー作から見ている。ずっと注目しているんだ」と、さも才能を発見したように、いっぱしの作家論を唸り始めるヤツがいてうんざりしてしまう。「あんたはただ単に、一時の性欲を満たしたかった、オカズを網膜に焼き付けたかっただけじゃねーか!!」と言ってやりたくなってしまう。その点二階堂氏の価値判断はシンプルでよろしい。「評論家のための映画し史か撮れない監督などダメだ」と一刀両断。いかに興奮し、いかに納得出来る内容で、いかに女優が魅力的かという点にフォーカスされており、もって回った抽象的な作家論などないのが潔い。
●『ブギーナイツ』に描かれた、あの時代・・・。
本書の構成は、製作国と時代別に、日本公開された主要な作品の内容とそのバックグラウンドやスタッフ、キャストを(スタッフが変名を使っている場合、その本名まで調査し、記述している!)紹介しているが、イザベル・サルリ、マリー・フォルサ、ジョージナ・スペルビン、シャロン・ケリー、ペネロープ・ラムール、マリリン・チェンバース、ダイアン・ソーン、そして80年代初頭、洋ピン史上最高の美女と言わしめたベロニカ・ハートといった女優たちの名前が頻繁に登場し、スクリーンに映し出されたセクシーな、セクシーすぎる肢体が脳内に甦る。と同時に、本書ではアメリカと日本における洋ピンの衰退についてもスペースを割いている。ポール・トーマス・アンダーソン監督の1997年作品『ブギーナイツ』で描かれた、あの時代だ。フィルムからビデオへ。場末の映画館から家庭のビデオデッキへと、アダルト産業の主戦場は移行した。
我が国で最期に洋ピンが封切られたのは、1993年10月15日。新宿国際劇場『巨乳生尻娘』、上野スター『爆乳クイーン』。共にイタリア映画で、翌年、映倫の外国成人映画指定本数欄に「0」と記入されたのは、1955年の「成人向」指定開始以来、初めてのことであった。
多くの人にとっては、どうでも良い雑多なカルチャー史。いや、だからこそ本書のような書籍が世に出る価値がある。本書に込められた「大衆娯楽」をリスペクトする視点。確実な知識と事実の見聞に裏打ちされた二階堂氏の表現スタイル。題材はどうであれ、これはジャンル・ムービーの栄枯盛衰を描いた、第一級のヒストリカル・ノンフィクションに違いない。
(文/斉藤守彦)