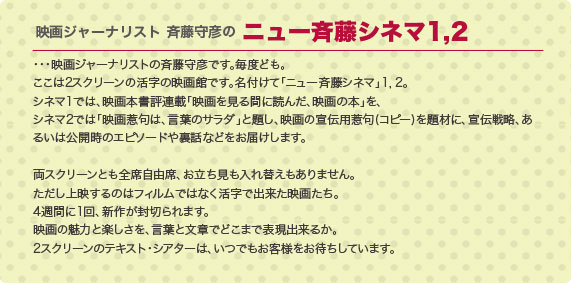【映画惹句は、言葉のサラダ】 第2回 スタジオジブリ作品の惹句には、映画をヒットさせるための仕掛けが込められている。
![もののけ姫 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51PEkSBYmaL._SL500_._SX400_.jpg)
- 『もののけ姫 [DVD]』
- 宮崎駿
- ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

- >> Amazon.co.jp
- >> HMV&BOOKS
●日本映画歴代ヒット作ベスト3は、すべてジブリ!!
前回が外国映画の歴代ヒット作の惹句を扱ったので、では今回は日本映画のヒット作をと、歴代ヒット作を調べてみたんだけれど・・1位『千と千尋の神隠し』興行収入304億円、2位『ハウルの動く城』196億円、3位『もののけ姫』193億円。なんだ。全部スタジオジブリのアニメ映画、3本とも宮崎駿監督特品ではないか。しかもジブリ作品については、鈴木敏夫プロデューサーが自らたくさんのエピソードを披露していることもあり、今さら云々しても・・と思うけど、今だからこそ見えることもまたあるはず。そんな発見を期待して、3本のジブリ作品の惹句を改めて云々しましょうか。
●すべての宮崎監督作品に共通する「生きろ。」という惹句
まず歴代ヒット作第3位の『もののけ姫』。1997年夏に公開され、その年の正月には『タイタニック』が大ヒットしたせいで、歴代邦画・洋画ヒット作ナンバーワンの座には半年弱しかいなかったけれど、それでもこれは凄い映画。壮大なスケール、骨太なドラマ。未だにDVDで見直し、そのたびに「ハヤオ様!!お見それいたしましたーっ!!」と平身低頭してしまうほどの、凄まじいパワーを感じさせる大傑作だ。この映画の惹句は、もう有名。
「生きろ。」
たったこれだけ。わずか4文字(マル込みで)。シンプル・イズ・ザ・ベスト。確かにそうだけど、映画をヒットさせるための惹句としては、説明もメッセージ性も不足しているのではないだろうか。通常、映画の宣伝用惹句にこの1行を提示された場合、どこの宣伝部長も即座にOKは出さないだろう。惹句の詠み人は、コピーライター・糸井重里。この3本のジブリ作品はすべて糸井さんの作品で、とりわけ『もののけ姫』の惹句を作るのには苦労したと、御本人がメディアで語っている。何回も何回も鈴木プロデューサーとFAXでやりとりをした。そのあたりの経緯は、鈴木さんの著書『映画道楽』を参照されたし。
ジブリ作品を宣伝するために、鈴木プロデューサーが心がけたことで、これまでの映画宣伝とは異なった点のひとつに「作品の中に入っていないことを、セールスポイントにしてはいけない」ということがある。これは鈴木Pが、初期ジブリ作品(『ナウシカ』か『ラピュタ』あたりか)のセールスポイントを挙げた際、プロデューサーを務めていた高畑勲監督から「お前は何を言っているんだ? そんなことが、この作品のどこにある?」と窘められたことがきっかけだそうだ。以来ジブリ作品の宣伝惹句に「宮崎監督最新作!!」や「●●万部のベストセラー、ついに映画化!!」などの、けたたましいフレーズが大きく扱われることは、基本的にない。あくまで内容本意に徹している。
では糸井さんの惹句以前に、そもそも『もののけ姫』の宣伝コンセプトを決めるために、鈴木Pたちが何をしたか? まず行ったのが、絵コンテを媒介にして「この監督は何を考えて、この作品を作っているのか?」を探ることだという。これは以前、筆者が鈴木Pにインタビューした際、直接聞いたエピソード。「まるで検事と弁護士のやりとりですよ」と。アニメの場合、クリエイターである監督の考えや主義主張は、すべて絵コンテに反映される。その絵コンテを間に挟んで、鈴木Pと東宝の宣伝プロデューサー、そしてパブリシティ実務を行う宣伝会社・メイジャーの面々が口角泡を飛ばしてああでもないこうでもないと、さながら宮崎駿監督の脳味噌の中を探検し、それをどんな言葉で伝えれば、世間が『もののけ姫』という作品を受け入れてくれるかを徹底的に話し合う。決して安易な「宮崎監督最新作!!」といったフレーズで作品を語らない。そこで確定した宣伝コンセプトに従い、糸井さんに惹句を依頼する。『もののけ姫』で糸井さんが作った惹句「生きろ。」は作品を徹底的に分解して、宮崎駿という監督の脳味噌の中を探検するほどの姿勢で書かれた、まさに我が国映画惹句史上の名作だ。そしてこの惹句は、『もののけ姫』のみならず、『千と千尋の神隠し』『崖の上のポニョ』『風立ちぬ』といった、後の宮崎監督作品の惹句としても有効であるように思う。宮崎監督が作品を通して語りかけてきたメッセージを一言で言うのならば、やはりこの「生きろ。」こそが相応しい。特に最後の長編となった『風立ちぬ』のラストでは、堀越二郎を迎える奈緒子の台詞「来て」を、アフレコの段階で「生きて」と、宮崎監督は変更していることからも、その思いの強さがうかがい知れようというもの。
●"宣伝をしない宣伝"『ハウルの動く城』の方法論とは?
さて我が国歴代ヒット作日本映画の部。その第2位『ハウルの動く城』の惹句も、極めてシンプル。
「ふたりが暮らした。」
ただしこの映画の場合、非常に特殊な宣伝展開が行われた事を念頭に置かなくてはならない。鈴木Pの言う「宣伝をしない宣伝」。これは前作『千と千尋の神隠し』の大ヒットについて、「宣伝が良いから当たった」との噂が宮崎監督の耳に入り、この巨匠ときたらスタッフをひとりひとり呼びつけ「作品が良くて当たったのか? 宣伝が良いから当たったのか? どっちだと思う?」と問うたのだという。そんなこと、「絶対に宣伝ですよ」などと監督に答えられるわけがないじゃん(笑)。でもひとりだけ「宣伝が良いから当たった」と答えた人がいて、その人はその後ジブリを退社したそうだ。宮崎監督のこうした振る舞いに対応して、鈴木Pは「宣伝をしない宣伝」を行うのだが、全国公開される新作映画で宣伝をしないなどということは、あり得ない。結果的にこの戦略は、作品の内容を詳細に解説した資料を作らない、広告出稿の時期を公開直前に集中させる。そして「宣伝をしない宣伝を行っている」ことを話題にして、パブリシティに反映させる。前作『千と千尋・・』の大ヒットを考えれば、宮崎監督の新作というだけで確実にヒットが見込めるからこそ可能になった展開だ。
映画館で配布されるチラシには、「ふたりが暮らした。」の惹句を使ったが、チラシという宣伝材料は、情報発信元(この場合はジブリと配給会社である東宝)が一方的にメッセージを発信するだけのアイテムだ。それも公開前に限定して。故に観客のリアクションなどを考慮した広告展開を行うのは、ジブリ作品の場合新聞広告に主眼が置かれる。鈴木Pが自らラフを描いたり、惹句を考えたりするほど、ジブリ作品が新聞広告を重視していたのは、そのヒット規模の大きさからオール・ターゲットと呼ばれるほど多くの人たちに訴えかける必要があったからだ。
『ハウルの動く城』の新聞広告には「ふたりが暮らした。」と一緒に、こんな惹句が添えられている。公開3週間前の朝日新聞に掲載された広告の場合だ。
「ヒロインは、90歳の少女。
恋人は、弱虫の魔法使い。
ふたりが暮らしたハウルの動く城。
このばあさんが、かなり元気!
宮崎駿が描く 生きる楽しさ、愛する歓び。
全世界注目の感動超大作。」
この惹句を関係者が「敏夫フォント」と呼ぶ、鈴木Pの書き文字を使い、広告の中央にレイアウトしている。「ふたりが暮らした。」というイメージ的なフレーズを補強するかのように、作品の内容を解説しているのは、「生きろ。」と言い切った「もののけ姫」の惹句とはまったくニュアンスが違う。なぜこういうことをしたのか?と考えた場合、思いつくのは「宣伝をしない宣伝」を行い、公開前の情報発信を控えていたことが影響していると思う。映画の宣伝には、まだ完成していない製作中の作品の存在を印象づけるための「製作宣伝」と呼ばれる段階があるが、『ハウル・・』の場合はそのプロセスに、しかるべき宣伝を行わなかった。これによって、多くの観客は唐突に宮崎監督の新作を認知しなくてはならなくなる。その場合、イメージ的な惹句を投げかけるだけでは、作品の内容が伝わらない。それを補強する意味での、いわばサポート惹句が必要になる。そしてこの手書きのサポート惹句は、公開後になると「生きる楽しさ、愛する歓び。それが、世界の約束。」と短縮され、本来はメインのはずの「ふたりが暮らした。」をさしおいて、大きく表記されるのであった。
新年になって「謹賀新年 ハウルによろしくね。」、1月8日からの三連休前日には「えっ?3連休なの!?」と、いずれも『ハウル・・』のキャラクターが語りかける図柄に、敏夫フォントの書き文字がかぶる。こうした季節感を広告で表現しているのも、ジブリ作品の宣伝・広告展開の特徴だ。公開前にはけたたましいほどの煽り文句を並べ立て、公開が始まるや「絶賛上映中」としか表記しない映画広告が多い、多すぎる。これでは季節感も立体感も出ないというもの。なんで未だに「絶賛上映中」ばかり連呼してるんだろ? もう。新聞広告の惹句に季節感を出した『ハウルの動く城』だが、年明けになって使った惹句「未来で待ってて。私、きっと行くから。」ってのは、本来この映画を監督するはずだった細田守の『時をかける少女』の、ラストの名台詞と似ているのは偶然だろうか。
●研ぎ澄まされ、力強くなっていった『千と千尋・・』の惹句。
ヒットした順番なので、下から『もののけ姫』『ハウルの動く城』『千と千尋の神隠し』になったけど、製作・公開順で言えば『もののけ姫』『千と千尋・・』『ハウル・・』の順。現在においても我が国で公開された日本映画、外国映画の歴代興行収入トップの座に君臨する『千と千尋の神隠し』の惹句は「トンネルのむこうは、不思議の町でした。」。詠み人は、またしても糸井さん。『もののけ姫』の惹句が、宮崎駿という監督の思考を深くトレースすることで行き着いたのに対して、『千と千尋・・』の惹句は、あくまでイメージを投げかけることにとどめている。こんなことが出来るのも、ジブリ作品が大ヒット確実で、世間の注目度も高いから。公開前には宮崎監督や鈴木Pら、たくさんの関係者がメディアの取材に答えて、作品の魅力を自らの言葉でアプローチする。広告出稿・TVスポットに加えてそうしたパブリシティの援護射撃があるからこそ、ジブリ作品はこれまで大ヒットを続ける事が出来たと言えるだろう。こうなると、宣伝材料や広告類に求められる機能とは、パブリシティとして露出された情報を包括し、この映画を鑑賞すべく観客の興味を喚起して、映画館に行くという物理的な行動に導くことにつきる。
ここでもまた、ジブリ宣伝の特徴が見られる。初動段階で投げかけた「トンネルのむこうは、不思議の町でした。」という惹句が、観客のリアクションやその時々の社会情勢などによって、徐々に変化していくのだ。それが新聞広告に反映されている。当たり前のことだが、映画の興行は公開初日から始まる。ところが映画会社、特に宣伝部のスタッフたちにとって、初日イコール・ゴールという考え方をする。「初日の舞台挨拶が終われば、宣伝は終わり」というのが業界内常識として認識されている。いや、それは違うだろ。初日はスタートライン。まだ最初の上映が始まったばかりじゃないか。大ヒットが期待されるジブリ作品の場合、半年間やそれ以上のロングランになることも珍しくない。それ故に宣伝活動を公開初日で終えるわけにはいかないのだ。シネコンが増えるに従って、公開直前に大規模な広告出稿やTVスポットを集中させはするものの、上映中の宣伝を疎かにしている例は、特に外国映画に見られる傾向で、こうしたオープニング偏重型の興行は、いたずらに作品を消費するばかり。
『千と千尋・・』上映中の新聞広告を追いかけてみると、公開前の時点では「トンネルのむこうは、不思議の町でした。」という惹句を使いながら、時にサブ扱いであった「生きている不思議 死んでいく不思議 花も風も街もみんなおなじ」をメインに持ってきたり。そして公開が始まると同時に「『生きる力』を呼び醒ませ!」と、ひときわ力強い惹句を投げかける。この言葉のインパクトは強烈だ。そして大ヒットとなるや、新聞広告にも遊びが出てきて、惹句も「この夏、映画と選挙に行こう。」と時事ネタを絡ませたり、「みんなの中にカオナシはいる 宮崎駿」と監督のコメント風に決めてみたり。しかし9月に入って使用した「ピリオドは打てない!」の惹句は、いささかやりすぎというか、はっきり言ってミスマッチ。鈴木Pが強力にプッシュした惹句だそうだが、これって東映の『仁義なき戦い』の追い広告に使われた惹句だから。やくざ映画とジブリアニメは、水と油だろう、やっぱり。詠み人は伝説の惹句師・関根忠郎。こればかりは鈴木さん、本当に・・・趣味ですなあ(笑)。
(文/斉藤守彦)