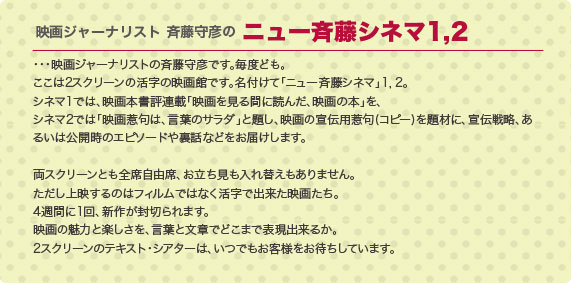第15回 『黒澤明が選んだ100本の映画』〜映画監督は、同業者とその作品をどう見ているのだろうか?

- 『黒澤明が選んだ100本の映画 (文春新書)』
- 黒澤 和子
- 文藝春秋
- 842円(税込)

- >> Amazon.co.jp
- >> HonyaClub.com
- >> LawsonHMV
●同業者の作品について、話したがらない我が国の監督たち。
前回、塩田明彦監督が書いた「映画術」を読んでいて、ふと思ったことがある。現役の映画監督としては、同世代の監督の作品を見て、どんな感想を持っているのだろうか。
実は以前、ある作品を複数の監督やスタッフに見せて、その感想を記事にしようと試みたことがある。ところが監督たちときたら、あまりハッキリと感想を言わないのである。聞けば「同業者の作品について、あれこれ指摘したりコメントをしないのは礼儀」なのだそうだ。はあ、そうですか。まあ業界というか、同業者間の暗黙の掟みたいなもんでしょうか。もちろんそうじゃない監督もいて、あそこが悪いここが悪いと、色々な指摘をされていましたが。
先日書店で見つけた『黒澤明が選んだ100本の映画』という新書には、巨匠クロサワが自ら選んだ、タイトル通り100本の映画についてここが良いとかここが見どころだとか、短いコメントを寄せている。拾い読みをしても良いし、通して読むと映画史を辿ることが出来たり(ご丁寧に、100本の作品は製作年度順に並んでいる)、様々な楽しみ方が出来る本だ。ただしこれは単に黒澤監督のコメントを並べた本ではなく、黒澤監督の娘である和子さんによるコメントも掲載されている、いわば父と娘の共同制作物なのである。
●007シリーズを好み、ネコバスの乗り心地を真剣に考えた巨匠。
例えば『ゴジラ』(1954)について。「(監督の)本多っていう男はマジメでさ、いいヤツなんだよ。もしゴジラが出てきたらさ、自分の職務忘れて逃げちゃうヨね。それなのに職員がちゃんとマジメに誘導したりしていて本多らしくて良いんだよね。」と、無二の親友であった本多猪四郎監督の個性を語り、それに和子さんが「『どんなタイプの映画でも、監督そのものが出るもんなんだよ』と父は言っていた」とフォローする。あるいはフェデリコ・フェリーニ監督の『道』について、黒澤は「ああいう独特な才能の人はもういないね。何か映像の中にものすごい存在感があって強烈な衝撃があるんだ。何度も会ったんだけどテレ屋で全然映画の話、してくれないの。」と語る。対する和子さんは「ローマのシャンデリアの下、抱擁して見つめ合う二人は、無言ながら互いの仕事を認め合い、賞賛し合い、ねぎらい合っているような眼差しで、とても感動的なシーンだった。」と、ふたりの巨匠の邂逅を目撃。その情景を具体的に語っているあたり、見事な父娘の連携だ。
世間的には「怖い監督」のイメージが強い黒澤監督だが、そんな巨匠の意外な一面が見られ、そこに和子さんが証言やエピソードが加わることで、さらに黒澤監督の個性や趣味が明らかになっていく。例えば『第三の男』について、黒澤監督はキャロル・リード監督を評して「ドキュメンタリー風でうまい監督です」と評価し、和子さんが「この作品の助監督ガイ・ハミルトンは初期の007シリーズを監督していた。父はこのシリーズが大好きだった」と、付け加える。あの黒澤監督が、007シリーズを楽しんでいたとは!
黒澤監督が宮崎駿監督のアニメ映画を高く評価していたことは知られており、特に『となりのトトロ』については「とても感激してね、ネコバスなんてすごく気に入った。だって思いつかないでしょ」と絶賛。これまた和子さんの手で、微笑ましいエピソードが加えられている。「八十を過ぎた父が、『ネコバスの乗り心地ばとうなのだろう?』と、本気で語っている姿には笑ってしまった」。
●出来れば、監督ご存命中に出して欲しかった...。
「僕を怖い監督にしたのは君たちだ。そういう記事を書くから、僕は怖いと思われている」。黒澤監督は生前、僕たちジャーナリストに対して、機会あるごとに不満をぶつけた。実は黒澤監督の遺作になった『まあだだよ』の撮影現場を取材した経験が僕にはあるが、その時も我々記者団に対して雷が落ちた。確かに怖かった。お世辞にも「優しく叱っていただいた」とは言えない。ただ、映画の撮影現場という場所は、たくさんのスタッフを船に乗せているようなものだ。時には間違った方向に進んでいる場合があり、そのことで取り返しがつかないミスを犯してしまうこともある。それを修正するのが船長たる監督の役目であり、そのためには強い姿勢でスタッフに接することも必要なのだ。どの組にも、時に現場の輪を乱してもその場を客観的な視点で見て、率直な指摘をする人材が必要とされるのである。
黒澤監督が、そういう面ばかり強調されるのを嫌がったのもよく分かる。無い物ねだりを承知で言えば、この『黒澤明が選んだ100本の映画』こそ、監督のご存命なうちに刊行して欲しかった。この本には映画作りを生業とし、映画を見るのが大好きな、巨匠の愛すべきエピソードが詰まっている。
(文/斉藤守彦)