二十五世本因坊治勲が畏怖した小林光一名誉三冠の姿とは
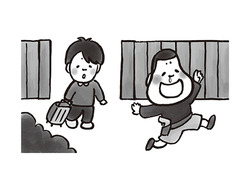
- イラスト・石井里果
『NHK 囲碁講座』の連載「二十五世本因坊治勲のちょっといい碁の話」。師匠・木谷實九段、呉清源九段の思い出から、石田章九段へのジェラシー、王立誠九段に対する恨み言まで、趙治勲(ちょう・ちくん)二十五世本因坊ならではの語り口で紡がれるエッセイは、碁界においてのみならず、広く人気を博しています。
1月号ではいよいよ同門のライバル、小林光一(こばやし・こういち)名誉三冠が登場します。
* * *
ここ数か月、小林家のお話ばっかりでした。飽きましたか?(笑) まあ、小林禮子(れいこ・七段・平成八年没)さんから始まって張栩(九段)・泉美(六段)夫妻とくれば、この人をほったらかしにするわけにはいきません。小林光一(名誉棋聖・名誉名人・名誉碁聖)さんにご登場願いましょう。
光一さんとはあれこれ、いろいろとありましたと書きたいところですが、皆さんが期待しているような話になるかなあ。まあ、出会ったころの話から始めます。
光一さんとは同門です。木谷實(九段)先生の下で切磋琢磨(せっさたくま)しました。もっとも、ぼくは6歳で来日。そんな昔の記憶はほとんど残っていません。
彼はぼくより4つ年上ですが、木谷先生のところへやってきたのは遅かった。入門はぼくが昭和37年の夏、彼は40年の春だったかな。当時のことは本当に、全く覚えていません。光一さんは「腰におもちゃのピストルをぶら下げた子供が(中略)走り回っている。私はてっきり『近所の子が紛れ込んだのだろう』と思っていた」(平成26年4月号「棋士に聞く」より)と、出会いを語ったそうなんですが、これが8歳のぼくだそうです(笑)。ちゃらんぽらんで遊ぶことしか考えていなかったんでしょうね。
碁はぼくのほうが強かった。生まれ育った北海道の旭川では天才と言われ、棋士を目指して上京してきた小林さんには相当なショックだったみたい。これも残念ながら、記憶にはないんだけどね。
ただ、ここから二人は全く対照的な日々を過ごします。小林さんは年下に負けたのを発奮材料としてとことん勉強した。逆にぼくは、とにかく遊んでばかりいた。勉強すればするほど伸びるのが子どもです。碁への取り組み方の差は、プロ入りの時期にくっきりと表れました。光一さんは昭和42年に入段。ぼくは一年後れました。
出会ったころは、もしかしたらぼくが天才で彼は鈍才だったのかもしれない。それなのにあっという間に追い抜かれちゃった。ライバル心が芽生えたのは入段のあたりでは?なんて言う人がいるけれど、それはどうなんだろう。
一つ、強烈な印象として心に刻み込まれているものがあります。ちゃらんぽらんだったぼくでも、このときは光一さんを強く意識せざるをえなかった。
彼のお母さんが亡くなったときだと思う。北海道の実家から、そういう連絡が道場に入ったんだろうね。母親というのは子どもにとっていちばん大切で、いちばん身近な存在。子どもは何かに困って泣くときは、「お父さ〜ん」じゃなくて、「お母さ〜ん」って言うじゃない? 父親としては悔しいけれどさ。
光一少年、どうしたと思う? 泣き叫ぶのが普通だよね。彼はね、ずっと碁盤に向かって碁を並べていたんですよ。信じられますか? じっと正座して、黙々と碁石を盤上に運んでいる。その姿がね、今でもまぶたの裏に焼き付いているんだなあ。こいつはいったい何者なんだ、涙をこらえながら碁を並べている姿を見て、こう思いました。尊敬とかじゃなくて、得体の知れないものに対する恐怖心というのかな。そういう感覚が湧いてきたのを覚えています。
これが小林光一・趙治勲の原点。そう思っています。母親が亡くなったのに、何のために、どんな気持ちで碁盤に向かっているのか。もっと言えば、今碁を並べる必要があるのか。どうしてそういうことができるのかと…。しゃにむに勉強することで亡き母に思いを伝えようとしたのかなあ。とにかく不思議でしようがなかった。もしかしたらここから棋士・小林光一を意識するようになったのかもしれません。(続く)
■『NHK囲碁講座』連載「二十五世本因坊治勲のちょっといい碁の話」2016年1月号より
1月号ではいよいよ同門のライバル、小林光一(こばやし・こういち)名誉三冠が登場します。
* * *
ここ数か月、小林家のお話ばっかりでした。飽きましたか?(笑) まあ、小林禮子(れいこ・七段・平成八年没)さんから始まって張栩(九段)・泉美(六段)夫妻とくれば、この人をほったらかしにするわけにはいきません。小林光一(名誉棋聖・名誉名人・名誉碁聖)さんにご登場願いましょう。
光一さんとはあれこれ、いろいろとありましたと書きたいところですが、皆さんが期待しているような話になるかなあ。まあ、出会ったころの話から始めます。
光一さんとは同門です。木谷實(九段)先生の下で切磋琢磨(せっさたくま)しました。もっとも、ぼくは6歳で来日。そんな昔の記憶はほとんど残っていません。
彼はぼくより4つ年上ですが、木谷先生のところへやってきたのは遅かった。入門はぼくが昭和37年の夏、彼は40年の春だったかな。当時のことは本当に、全く覚えていません。光一さんは「腰におもちゃのピストルをぶら下げた子供が(中略)走り回っている。私はてっきり『近所の子が紛れ込んだのだろう』と思っていた」(平成26年4月号「棋士に聞く」より)と、出会いを語ったそうなんですが、これが8歳のぼくだそうです(笑)。ちゃらんぽらんで遊ぶことしか考えていなかったんでしょうね。
碁はぼくのほうが強かった。生まれ育った北海道の旭川では天才と言われ、棋士を目指して上京してきた小林さんには相当なショックだったみたい。これも残念ながら、記憶にはないんだけどね。
ただ、ここから二人は全く対照的な日々を過ごします。小林さんは年下に負けたのを発奮材料としてとことん勉強した。逆にぼくは、とにかく遊んでばかりいた。勉強すればするほど伸びるのが子どもです。碁への取り組み方の差は、プロ入りの時期にくっきりと表れました。光一さんは昭和42年に入段。ぼくは一年後れました。
出会ったころは、もしかしたらぼくが天才で彼は鈍才だったのかもしれない。それなのにあっという間に追い抜かれちゃった。ライバル心が芽生えたのは入段のあたりでは?なんて言う人がいるけれど、それはどうなんだろう。
一つ、強烈な印象として心に刻み込まれているものがあります。ちゃらんぽらんだったぼくでも、このときは光一さんを強く意識せざるをえなかった。
彼のお母さんが亡くなったときだと思う。北海道の実家から、そういう連絡が道場に入ったんだろうね。母親というのは子どもにとっていちばん大切で、いちばん身近な存在。子どもは何かに困って泣くときは、「お父さ〜ん」じゃなくて、「お母さ〜ん」って言うじゃない? 父親としては悔しいけれどさ。
光一少年、どうしたと思う? 泣き叫ぶのが普通だよね。彼はね、ずっと碁盤に向かって碁を並べていたんですよ。信じられますか? じっと正座して、黙々と碁石を盤上に運んでいる。その姿がね、今でもまぶたの裏に焼き付いているんだなあ。こいつはいったい何者なんだ、涙をこらえながら碁を並べている姿を見て、こう思いました。尊敬とかじゃなくて、得体の知れないものに対する恐怖心というのかな。そういう感覚が湧いてきたのを覚えています。
これが小林光一・趙治勲の原点。そう思っています。母親が亡くなったのに、何のために、どんな気持ちで碁盤に向かっているのか。もっと言えば、今碁を並べる必要があるのか。どうしてそういうことができるのかと…。しゃにむに勉強することで亡き母に思いを伝えようとしたのかなあ。とにかく不思議でしようがなかった。もしかしたらここから棋士・小林光一を意識するようになったのかもしれません。(続く)
■『NHK囲碁講座』連載「二十五世本因坊治勲のちょっといい碁の話」2016年1月号より
![NHK 囲碁講座 2016年 01 月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51dSBd7giOL._SL100_.jpg)
- 『NHK 囲碁講座 2016年 01 月号 [雑誌]』
- 日本放送出版協会 / NHK出版 / 545円(税込)
- >> Amazon.co.jp













