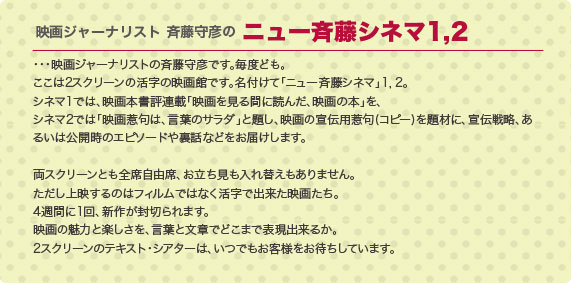【映画を待つ間に読んだ、映画の本】 第42回『映画館のまわし者/ある映写技術者のつぶやき』〜現役フィルム映写技師が語る、映画を「見せる」楽しさと喜び。

- 『映画館のまわし者―ある映写技術者のつぶやき (SCREEN新書)』
- 荒島 晃宏
- 近代映画社
- 972円(税込)

- >> Amazon.co.jp
- >> HonyaClub.com
- >> LawsonHMV
●かつて映画館は、映写技師の腕を堪能する場所だった。
映画サイトを運営している、知り合いの女性編集者が「映画館の支配人にインタビューしたい」と言うので、都内の名画座に連れて行き、支配人にお話を聞いた。話の流れで映写のことについてやりとりをすると、支配人が「うちの映写室には、まだフィルム映写機があるんです。見ますか?」と。そりゃもちろん見たい。僕も一緒に映写室に行くと、どどーんと鎮座しているフィルム映写機。その脇にはフィルムの編集台が。インタビュアーの女性は、えらく驚いた様子。「映画をフィルムで上映する時は、配給会社の倉庫から大きな缶に入ったフィルムがバラした形で到着するので、それをここで編集するわけ。フィルムは重いから、映写技師の人は必ずと言って良いほど、腰を痛めたんだよ」と、映画館バイト経験がある僕が教えてあげると、「信じられない!!」といったリアクションが返ってきた。
そうだろうなあ・・・今や映画はフィルムではなくDCP(デジタル・シネマ・パッケージ)と称するハードディスクに入って映画館に到着し、それをサーバーにコピーしてDLPプロジェクターで上映する形式が主流だ。それどころか映画館に必ずいた映写技師が、全国チェーンのシネコンには見当たらない。パソコンのキーを操作するだけで映写が出来る事から、専業の映写技師が必要なくなったのだ。技術面でのフォローは本部の専門家が担当し、機材のトラブルなどは保守契約を結んだ会社に修理を依頼する。『映画館のまわし者』の著者・荒島晃宏さんが書いている、重いフィルムを映写機にかけて、2台の映写機で1本の映画を上映する事は、今、ほとんどの映画館で行われていない。
かつて映画館とは、映写技師の腕を楽しみ、堪能する場所だった。画面の隅々までピントが合い、音響も的確。映写機の1台目と2台目の引き継ぎも滞りなく行われ、観客は映画の内容に没頭することが出来る。それが最高の映写というものだ。荒島さんは本書を執筆した時点では浅草の映画館で映写を担当していたが、現在は渋谷の名画座シネマ・ヴェーラで映写を行っている。そして現在においてもまだデジタル映写の経験がないそうだから、フィルム映写一筋の人と言えるだろう。
●「由美かおるのオッパイは、みんなのものだ」
その荒島さんが本書を刊行したのが2011年の2月。僕は即座に書店で購入し、映写技師の仕事ぶりを丁寧に分かり易安く、軽快なタッチで解説した荒島さんの文章に唸った。これはまさしく快著である。
とりわけ面白いのが、映写技師の道を歩む荒島さんを指導する師匠や映画館の人が、その都度発する的確なアドバイスや忠告だ。
由美かおるがバストを披露した東宝映画『エスパイ』を上映すべくフィルムをチェックした時、そのシーンがかなり短くなっているのを荒島さんが発見した時だ。どうやら他館で映写を担当した人が、編集時にコマをカットして持ち帰ることが頻発したらしい。営業係の人は荒島さんにこう言い放つ。「由美かおるのオッパイは、みんなのものだから、持っていっちゃあダメだよ」と。その通り。そういう不心得者は職人の風上にも置けない。気持ちは分かるけど。
●「映写室に向かって手を振る子供たちには、応えるように」
本書で荒島さんは「10年後には、フィルム上映は今の半分以下になっているでしょう」と書いているが、現実のスピードはもっと早かった。この本が刊行された2011年の夏興行あたりから多くの映画館、シネコン・チェーンがデジタル化に踏み切り、2016年末の時点で全国映画館3472スクリーンのうち、97.7パーセントがデジタル映写を採用しているというから、荒島さんの予測より早く本格的なデジタル映写時代が到来した。それ故本書に書かれたフィルム映写にまつわるたくさんのエピソードはアナログ時代の想い出に終始し、実用性の点では時代遅れだと言わざるを得ない。
果たしてそうだろうか?
この『映画館のまわし者』は、フィルム映写に関する技術書でも、フィルム原理主義者のための教科書でもない。この本に書かれている最も大切なことは、映画を「見せる」仕事の楽しさ、観客に向かって映画を映すことの喜びだ。
子供向け映画を上映した際、映写室に人がいると分かった子供たちが、客席から手を振ってくれる。そんな光景に出くわした時、荒島さんは子供たちに手を振り替えし、後輩の映写技師にも「映写室に向かって手を振っている子供がいたら、必ずこちらも振って応えてあげるように」と言うそうだ。
「映写室から手を振り返されたら、その子供はもっと映画に興味を持ってくれるに違いない。そうすれば、これからも映画を見続けてくれるに違いない」という荒島さん。
忘れてはならないのは、これまで映画を上映してきた映写技師たちは、雨の日も風の日も日夜映写室でフィルムと格闘し、そこに込められた作り手たちの思いをスクリーンに描き続けたことだ。映写室に手を振る子供たちが、これからも映画館で映画を楽しんで欲しい。それがフィルムであろうとデジタルであろうと。そんな願いを込めて、彼は今でも渋谷の名画座でフィルムを上映し続けている。
荒島さんに映写される映画は、それを見る観客と同じぐらい幸福であると、僕は思う。
(文/斉藤守彦)