テレビの現場では何が起きているのか? 元テレビマンの大学教授が業界の実態と未来を徹底分析

- 『混沌時代の新・テレビ論 (ポプラ新書 252)』
- 田淵 俊彦
- ポプラ社
- 1,100円(税込)
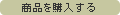
- >> Amazon.co.jp
- >> HMV&BOOKS
かつては学生が働きたい企業として高い人気を誇ったテレビ局。しかしその吸引力は次第に衰え、2024年前半総合の「就職ブランドランキング」では、業界人気トップだったフジテレビも全体順位150位に落ち込んでいます。また、ここ数年は各テレビ局から人気アナウンサーや有力社員が続々と退社し、テレビ自体が「オワコン」などと揶揄されることも。
テレビの現場ではいま何が起きているのでしょうか。テレビ東京の元プロデューサーで現在は大学教授を務める田淵俊彦氏が、著書『混沌時代の新・テレビ論』でその実情を徹底的に解き明かしています。
"現役バリバリの優秀なテレビマン"がテレビ局に愛想を尽かす原因として、田淵氏は次の3つを挙げます。
1、「メディア・コントロール」を受けてしまうという「なさけなさ」
2、異常なまでの「忖度」をするという「だらしなさ」
3、「何さまだ!」と突っ込みたくなるような強権を振るう「不遜」や「横暴」
(同書より)
どれもかなり手厳しいですが、その中でも注目したいのが2番目。いまテレビは、「『コンプライアンス順守』という名のもとの『忖度』でがんじがらめの状態である」「テレビ局はコンプライアンスという大義名分に乗じて自主規制をかけ、自らの報道責任を放棄している」「過剰なコンプライアンス順守で見る者の『考える力』を損なわせてはならない」(同書より)と指摘します。
そして私たちもまた、テレビを見る際は創り手による「意図」や「恣意」にだまされないようにしなくてはなりません。「テレビではこう報道しているが、本当だろうか?」「この番組のキャスターはこう言っているが、こういう考え方や見方もあるんじゃないだろうか?」(同書より)といったふうに、「見えているものの向こう側にある『隠されているもの』を見抜く力」(同書より)を大切にすることが必要です。
同書では「テレビ局の忖度」の実例として「ジャニーズ問題」にも言及。これまでメディアで報道されている情報と重なる部分が多いものの、実際に多くのアイドルやジャニー喜多川氏、メリー喜多川氏と接してきた田淵氏の話には、説得力が感じられます。
全体を通して厳しい言葉が並びますが、そこには叱咤激励の気持ちも込められている同書。巻末に収録されている伊藤隆行氏と村上徹夫氏との鼎談からは、業界を離れた今もテレビを愛する思いが強く伝わってきます。
最終章では、今後のテレビが生き残っていくためのヒントについても提言。ここで語られる2つの能力は、テレビ業界だけでなく、これからの時代を生きていくすべての人にとって必要なものとなるはず。ぜひ同書を読んで確かめてみてください。
[文・鷺ノ宮やよい]











