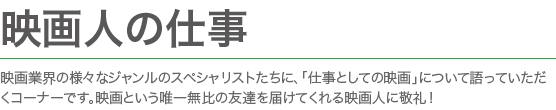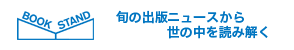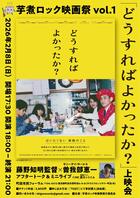映画業界で活躍するすごい映画人に、「仕事としての映画」について語っていただくコーナー。今回お話を聞くのは、西新宿にある輸入映画ソフト専門店「ビデオマーケット」の店主、涌井次郎(わくい・じろう)さんです。
*
いまや思い立ったら配信ですぐに映画を観られる時代。しかしながら映画好きならうっすらと気づいていることでしょう。この世には配信サービスでは見つけられない、珍作・名作が星の数ほどあることを......。「ビデオマーケット」(以下、ビデマ)はそんな好奇心を刺激し、ディープな映画の世界へと誘ってくれます。取り扱うジャンルはホラーが中心ながらも、SF、カルト、モンド、アジア、カンフーなど、全部数えると20種ほどあり、ものすごい充実っぷり。映画を「配信の時代」という形では到底、片付けられない!そんな熱い思いが湧き上がり、映画への愛情と好奇心が一層掻き立てられる貴重なお店です。
2回に分けてお届けする前編では、涌井さんが若くして抱いた映画ソフトへの所有欲、そしてビデマで勤務するまでの経緯を追います!
中学生にして芽生えた、映画所有欲
涌井さんの生まれは1970年、育ちは新潟県の上越市だ。映画との長い付き合いのはじまりは、自宅の斜め向かいにあった映画館に四つ上の兄とふたりで通い出したことにある。
6歳で映画館デビューを果たした作品は『キングコング』(1976年)。翌年には『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』(1977年)が公開され、テレビも雑誌も映画の話題作でもちきりの時代だった。波に乗っかるように、涌井さんはあっという間に映画に夢中になったという。中学生になり、兄抜きでも映画館に足を運ぶようになってから「痛く感激した」という作品は『ターミネーター』(1984年)。そうしてこんな感覚が芽生えたという。
「観て感激しただけで終わらずに、なんとかしてこれは映画ソフトで欲しい」
しかし、当時のビデオテープの価格は2万円ほど。中学生からしてみたら、なかなかのいいお値段だ。それでも涌井さんはお年玉を前借りしたり、お小遣いを貯めたりと中学生なりに資金をかき集めて『ターミネーター』をついに手に入れた。
「この辺りから『映画を観ただけでは終われない、物として所有したい』という欲求が生まれましたね」
どうしても観たくて、初めて手に入れた輸入盤
高校生になると、映画への愛情があふれるあまり、雑誌や音楽、小説などをとおして映画の世界をグイグイ広げることに熱を注いでいた。「観る術のない映画もなんとかして観たい」。そんな欲求まで、自然と芽生えていた。
「映画の本をどんどん読んでいくと、観たい映画が出てくるんですけども、どうしても観られない映画ってやっぱりあるわけですよね」
たとえばスタンリー・キューブリック監督の名作『時計じかけのオレンジ』(1971年)がそうだ。劇場公開はされたものの、涌井さんが同作を知った80年代にはまだソフト化がされていなかった。ふくらむ興味にどうにか対処しようと小説を読み、サントラを聴くも、肝心な映画はどうしても観られない......ならばどうするか。輸入盤だ!
「スターログだったかな。当時のSF系の雑誌があるんですけども、そこに通信販売で輸入盤を取り扱ってるお店の広告があって、日本ではなかなか手に入れられないタイトルがずらずらと並んでるんですよね。そこで『時計じかけのオレンジ』を見つけて、そうか、日本で観られないなら輸入盤という手があるのか!と輸入盤の存在を意識し始めました」
と、現職につながる視点を高校生のときに早くも見出していたそうだ。
注文した翌日に商品が届くのが皆無の時代に、涌井さんは熱心にショップのカタログを取り寄せ、注文ハガキを出した。そして、約3カ月越しにようやく手元に『時計じかけのオレンジ』が届いた。
「内容はもちろん小説や記事から知っていました。ああいう映画なので、深夜にこっそりですね。自分の部屋にテレビはないので、居間で観たわけなんですけども、その感激、感動たるものはもうなんでしょう......もう40年近く前の話ですけども、未だに新鮮に思い出せます」
店舗で映画ソフトを眺めるようになった大学生時代
勉強そっちのけで穴が開くほどカタログを眺め、お金を貯めてはレーザーディスク(当時、7,800円ほど)やビデオ(当時、2万円ほど)などの映画ソフトに注ぎ込む日々は、高校を卒業しても変わらなかった。大学のために上京すると、映画ソフトを店頭で眺められるようにもなり、ソフトはより身近な存在となった。ビデマはそんな学生時代に、涌井さんが足を運んだいくつかの映画ソフト専門店のうちの一つだった。
「西新宿界隈にはレコードショップなんかもありまして、学生の頃から割と来てたんですよね。その流れでビデオマーケットを覗いたりしていました」
当時のビデマは現店舗が位置する5階建てビルの全フロアを占めており、ホラーのフロア、アジア映画・カンフー映画のフロア、国内版のレア盤が手に入るフロア......と階ごとに異なる世界が広がっていた。「とても雑多で、どこからこんなもの仕入れてくるんだ!みたいなへんてこなものが結構ありました」
映像制作の夢を追いかけ、あくせく働いた20代
学生としてビデマで働くのだろうか......と思いきや、勤めるまでにはまだストーリーがある。
美術大学で映画コースを受講していた涌井さんは、「こんな瞬間はこの先、絶対にないだろうな」と大事に噛み締めながら送った学生生活のなかで、自然と映像制作を志すようになっていた。卒業後、名の知れた舞台照明会社に入るも、任された仕事は希望とややかけ離れていた。
「そこの映像制作部門になんとか潜り込めないかなという希望があったんですけども。結局、舞台大道具の営業として大道具の図面を書いたり、役場関係を回って営業したり、催しに使う雛壇を組んだりしてました。それでずいぶん失望しまして。学生時代が非常に楽しかったもので、もう働くのが嫌で嫌で仕方なくてですね。辛い日々でした」
このままでは制作の道に進めないかもしれない。そんな思いで会社をやめ、フリーターとして仕事を探す方向に振り切るも、世界は依然として厳しかった。
「いろいろトライするんですけど、やっぱり実務もなく、新卒より年もいっているのでなかなか採用されないんですよね。時間の調整が効くように日雇いの仕事もしていましたが、心がどんどんすさんでいきました」
先の見えない日々から逃れるように訪れていたのが、レコード店や映画ソフトの専門店だった。「本当に自分の生活を切り売りしながら会社に使われる日々だったんですけども、そういうお店にいる瞬間だけは自分が守られていたんですよね。好きなものに囲まれて、没頭できるといいますか。そういう時間が、結構かけがえのない時間だったんです」
ビデマに社員募集の貼り紙を発見!
そんなある日、いつものようにビデマに立ち寄ると、「社員募集」と書かれた貼り紙を発見。「そのときは29にもなっていたので、フリーターとして時間だけが過ぎていくよりは、自分が好きでずっと買ったり、見たりしてきたものの世界で働くのもありかなということで応募して、入社しました」
そうして1999年の秋、いよいよ(!)ビデマでの勤務がはじまる。ただ、"好き"に近い職場での再スタートでありながら、過酷な日々の幕開けでもあった。何せ当時のビデマは成果主義。担当セクションの企画をスタッフが毎月練っては実行し、売上目標を達成しなければ容赦なく減給される仕組みだった。担当セクションは定期的に入れ替わり、運悪く売れにくい商材に当たると、もう大変。
「外から見るとのんびりしているかもしれませんが、中は壮絶でしたね。映画をゆっくり見て、見識を深める余裕は全くありませんでした」
結果を出せない従業員は外部からの優秀な人材と置き換えられ、店長やスタッフは目まぐるしく入れ替わり、もはや働き続けることはある種のサバイバルだった。
ただ、数字には厳しい会社でありながら企画をどう実行するかはほぼ現場任せで、自由度は高かった。大好きな映画『悪魔のいけにえ2』(1986年)の登場人物、チョップトップ演じるビル・モーズリー氏に連絡をとり、サイン会(満員御礼!)を実現したこともあったという。楽しさや達成感もあったが、「ボロボロになりながらなんとか生き残ったという感じは、正直ありますね」と涌井さん。そこで約10年間も勤務したというので驚きだ。振り返ってみたときに、生き抜いてこれた理由はどこにあったと説いているのだろうか。
「趣味の感覚や好き嫌いをとりあえず捨てて、かなりクールに商材として見ないといけないなとよくも悪くも学びましたね。あと、30代で経験できてよかったなと思いましたね。自分が40代だったらあの勢いにはちょっとついていけなかったかと。逆に20代でも根性がなくて、早々に辞めていたかもしれません。いいタイミングだったのかもしれないですね」
そもそも勤務年数が10年で打ち切られたのは、ビデマの閉店が決まったからだ。しかしビデマの歴史はそこでは終わらない。当時店長まで昇格していた涌井さんが、ビデマを買い取ることを決意するからだ。
後編では、涌井さんが個人店として深い愛情をもって営むビデマに迫る。どうぞお楽しみに!
(取材・文/鈴木未来)
<店舗情報>
ビデオマーケット
営業時間:月曜(12時-14時)、水〜日曜(12時-14時および16時-20時)
住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-9-13 DKY15ビル 4F