『女刑事RIKO 聖母の深き淵』怒涛のご都合主義がオツムを痺れさせる
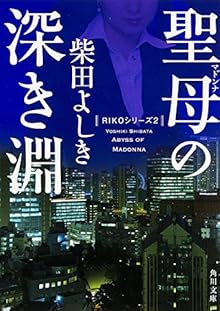
- 『聖母の深き淵 (角川文庫)』
- 柴田 よしき
- KADOKAWA
- 1,012円(税込)

- >> Amazon.co.jp
- >> HonyaClub.com
- >> HMV&BOOKS
女性警察官が活躍する映画やドラマ、小説というものは昔から一定の人気を誇るジャンルだ。美女が難事件を華々しく解決するという形式は、ある種の人々にカタルシスを与えるのだろう。
しかし、筆者が新聞記者をしていた時に見た警察内部は完全に男社会だった。幹部は男ばかり、刑事も男。女性の刑事はいないではいが、捜査の主力というよりも世間が男女平等を謳うから仕方がなく採用したような印象を受けた。警察官から「娘が大学へ行きたいというのだが、女に学歴は必要なのだろうか?」と素敵なことを真顔で訊ねられたことが再三ならずある。
彼らの男尊女卑ぶりは内部だけでなく外部にも徹底していて、男性記者が取材に行ったらけんもほろろに扱われた一方、美人記者が訪ねたら「関係以外立ち入り禁止」とでかでかと記された刑事部屋へ案内されていた。
もっとも、美人だから情報を得られた訳でなく単なる喋るお人形さんとして扱われたようで、肝心の取材はできずからかわれて追い返された様子だったが。
「日本は男尊女卑社会だ!」と怒る人々がこの事実を知ったら、泡吹いて死ぬんじゃないだろうか。上記のような見聞を踏まえて女刑事ものを鑑賞すると、現実と空想のギャップで荒唐無稽な不条理小説でも読んでいる気分になる。原作のジャンルはミステリだそうだが。
そもそも、警察庁の女性官僚が2015年に岩手県警本部長になっただけでニュースになる世界だ。物語は物語として楽しむことが正しいのだろう。
本作もそんなお花畑な構成になっている。主人公の村上緑子(滝沢涼子)は殺人事件などを捜査する強行犯係の刑事で2歳の子持ちシングルマザー。現実では仕事で帰れないために家庭が破綻している刑事が少なからずいるのに、彼女は子育てにも手を抜かない。家庭を顧みずに捜査だけをしていても無理と無茶が祟って早死にする刑事が少なくない中、彼女は明らかにオーバーワーク。劇中で過労死しないことが不思議でならない。
キャラクターの設定にケチをつけたら何の物語も生まれないと我慢して視聴していたが、内容はリアリティのリの字もない。連続殺人事件と誘拐事件の糸口が主人公の公園デビューの際に被害者と知り合うという、ご都合主義と呼ぶことさえはばかられるものだった。このほか恋愛やら何やらも起きるのだが、土台が崩壊しているものに何を乗せてもどうにもならない。まさに「もやもや」を体現した作品。うっかり鑑賞した自分をブン殴りたい!
本作よりも映像化した経緯を映画化してほしい。ケインズは穴を掘って埋めても経済が回ると説いたが、この映画も公共事業か何かなのだろうか。制作は1998年と、不景気ド真ん中だったので、多分そうに違いない。
(文/畑中雄也)



















