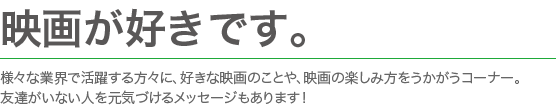その命に10億円の懸賞金がかけられた連続殺人鬼。そんな"人間の屑"を、命をかけて護送しなければならない警視庁警備部のSPの、心の葛藤を描いたサスペンス。漫画BE-BOP-HIGHSCHOOL』の木内一裕さん原作小説『藁の楯』が映画化! 4月26日の公開を前に、監督の三池崇史さんに『藁の楯 わらのたて』とご自身の映画観をインタビューしました。
──映画『藁の楯 わらのたて』、原作とどんな違いがありますか?
「ゼロから生み出した作家の思い、結果として書き上がった原稿と、印刷された出版物。それらを根っこからリスペクトするところから始めるのが、僕の個人的な映画の作り方。だから原作と対立する必要はないんです。ウケそうなところだけをいいとこ取りして、自分たちで勝手にアレンジするなど"利用"するのではなく、明らかに"そこから生まれたもの"であることを大事にしています。我々はその中に入り込んで、その延長上で自分たちの作れるモノを作っていく。それが結果として映画になるんです。著者の木内さんは、映画も何本か撮られています。本来ならば木内さん自身が映画化するはずの作品を、僕がお預かりすることになったという。これは原作のあるすべての作品に共通していますが、とにかく原作者をまず一番大事にすること。一番最初の観客として、映画化したことを後悔させないことがスタート地点。どんなに大ヒットしていろんな人に楽しんでもらえても、原作者ががっかりしていたのでは作った意味がないと思うんです。そして、相手が手強ければ手強いほど、自分たちの中にある普段眠っている部分も、戦うために覚醒してくる。その人の熱を借りて作品を作る。僕の映画作りの基本は、そういうことですね」
──人の熱を自分の熱に変換すること。なかなか難しいことのように思います。
「自分自身は、映画化するということに無関心なんです。あなたはどういう映画を作りたいですか?と問われても、"いや別に"って(笑)。自分からそれを求めなくても、来た話の中に熱があるんですよ。自分の熱で何かを作る......火種の元が自分だと、それはいつか消えてしまうんです。だから僕自身は空っぽの受け皿、あるいはスポンジのような状態で、他の人が作り上げてきた思いを全部自分のパワーに変えて作るんです。エゴのようなものは邪魔になるから、できるだけ出さない。でも映画学校でそんなことを教えたら、ダメな監督という部類に入るかもしれないですね。理想を持って、作りたいモノを追求していくというのが映画監督なのかもしれませんが、自分はあまり興味がないですね」
──どのようなプロセスで他人の熱を自分の熱に変えていくんですか?
「自然に、です。たとえば原作を読んで、自分が監督という立場で作らなければいけない。クランクインするまであと2ヶ月。どんな準備をするのか。主人公はどんな服を着ているのか。そうしているうちに、無我夢中になっていくんです。自分というものを意識して表現している自分って、やっぱりフェイクだと思うんですよね。"自分はこうありたい"という理想をなぞっているだけ。それよりも、とにかく追い詰められて、自分がどうとかそんなこと言ってる場合じゃないよねっていうなかで、自分も知らない本当の自分の匂いが出てくるのではないかなと思います」
──映画『藁の楯 わらのたて』は、どんな風に作っていったんですか?
「原作を読んでまず最初に虜になったのが、映画では大沢たかおさんが演じた「銘苅」というSPの普段の姿を描いた数行の文章。奥さんの誕生日に、仕方ないなと言ってケーキを買って帰るんですが、その奥さんは仏壇の中。削ぎ落とした表現で、銘苅がいかに奥さんを大事にしているかを伝え、なおかつ仏壇に食器がコンと触れるという描写によって、部屋の匂いや孤独感までも感じ取れる。たった数行で、小説ってこんなに表現できるんだなって。なおかつそれは、読者に対する裏切りでもあるんです。警察官の普通の家庭ってどんなだろう? 子どもはいそうにないな。でも奥さんすらもいなかった。見事に読者の裏をかいているんですよね。削ぎ落とした表現で見せるスピード感や、ストーリーだけでなくキャラクターそのものでも観客を裏切っていくこと。そういうものを映画でも表現できると楽しいかなと思って作っていましたね。
前作の『悪の教典』(2012年公開/監督・脚本)の時は、どれだけシンプルにできるかという取り組みをしたので、ボロボロになるほど読みましたが、今回は自分なりのテーマがしっかり絞れていたので、原作を読んだのは一回だけ。あとは脚本家やプロデューサーと話しながら、自分にない部分を強化していく。重要な役所を女性に変えるという発想(松嶋菜々子さんが演じています)であったり、興行ということを考えた時に生まれてくる発想は、僕らにはないわけです。そういうものを全部足してもらいながらも、どんな意見が入ろうとゆるがない根っこが自分の中にはあったので、それらを自分なりに咀嚼して映像化していきました。僕らは文章からイメージするものを映像化していくのが仕事なので、原作の小説とはいろんな付き合い方があるんですよね」
──最後に、三池監督の映画体験について印象的なエピソードをお聞かせください。
「映画が好きになったきっかけは、ブルース・リーなんです。日本にいると特殊なブルース・リー体験ができたんですよ。小学校6年の頃かな。1年間ぐらい『燃えよドラゴン』のロングランをやっていたんですよ。で、僕らは完全に魅了されて、毎週土日は『燃えよドラゴン』という生活。リピーターの走りかもしれないですね(笑)。その時に、大阪のどうしようもないゴミみたいな少年だった僕が、劇場の中で感じていたこと。それは、いきいきと暴れている憧れのこの肉体が、実際には1年前にもうこの世にない。それを観て、僕はいま感動している。1年前に死んでいる人を見て。これは僕らにとって大きな体験だったと思うんです。憧れたものがもうこの世にいないということ。
シアトルの映画祭に呼ばれた時には、どこへ行きたいか聞かれて、ブルース・リーのお墓に行きたいと答えました。お墓、シアトルにあるんですよね。湖の見渡せる綺麗な場所で、すぐ隣にはブランドン・リーのお墓がある。すごい家族なんだなって思いましたね。そこにはずーっとお花がいっぱいだし、見ているとひっきりなしに若い奴らがやってくる。いかにものし上がってやるぜ!という感じのヤンキーっぽいマイノリティな奴らが、花を持ってきてお参りに来るんです。高校時代に読みあさった三島由紀夫もそうですが、自分が共鳴してあとあとまで心に残る人たちの共通点は、すごく俗な言い方ですが、若くして命を絶つ、あるいは絶たれること。三島由紀夫もブルース・リーも、生き様そのものを作品に変えていった人だと思います。その主義主張ややり方には非難もあれば、いろんな考え方があるでしょうけど」
(取材・文/根本美保子)

『藁の楯 わらのたて』
4月26日より全国ロードショー
監督/三池崇史
出演/大沢たかお、松嶋菜々子、藤原竜也ほか
「この男を殺してください。御礼として10億円お支払いします」。大手全国紙すべてに掲載された、前代未聞の全面広告を発端に、日本中が殺気に満ちていく。"人間のクズ"の連続殺人犯を、命をかけて移送する警視庁警備部SPたちの活躍と心の葛藤を描くサスペンスアクション。