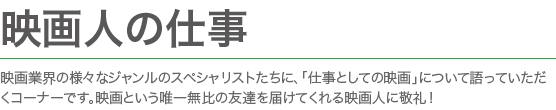『長江哀歌』や『罪の手ざわり』など、市井の人々の暮らしを通じて、中国そのものを描き続けてきたジャ・ジャンクー監督。その最新作『山河ノスタルジア』が今週末に公開になります。1999年、2014年、2025年という3つの年代をまたいだ壮大な叙事詩である本作は、常に時代を見つめてきたジャ監督の集大成ともいえる作品です。
ひとりの女性の過去、現在、未来を描くというテーマから、役者陣の自然な若返りや老けの表現が重要になってきますが、そんな本作で、ジャ監督のミューズとして知られる主演のチャオ・タオほか、メインの役者陣のヘアメイクを手掛けたのが、日本人ヘアメイクアップアーティスト・橋本申二さん。国内外の映画やCMなど映像作品のヘアメイクを数多く手掛ける橋本さんの仕事に迫ります。ちなみに女性のみなさん、パックはやっぱり、大事みたいです!
***
◆たるみ、くすみ&法令線......若返りはやっぱり大変です!
──主人公タオを演じたチャオ・タオさんの実年齢は30代後半(1977年生まれ)ですが、映画を観てもほんとは何歳なのだかよくわからないくらい自然でした。タオの20代から50代までを表現するにあたり、一番大変だったのはどの年代でしたか?
「若返らせるのがやっぱり一番大変でした。年齢とともに皮膚のたるみやくすみ、法令線が下がってくるようことは当然ありますが、それがわからないように肌を綺麗に若く見せていくことが大きなポイントになりました」

──どんなテクニックを使われたんですか?
「基本的にはパックとマッサージで保湿をしっかりすることで、肌をいい状態に持っていくことができます。また、この作品では、髪の毛を6点で引っ張って、顔をリフトアップしています。こめかみの辺りの髪の毛を少しだけ引っ張って目元をリフトアップし、襟足で顎のラインを作る、というようなことをしています」
──ゴムを使っているのですか?
「僕の場合は、日本髪に使う元結(もっとい)を使っています。ゴムだと弾力が出てバランスがとりにくくなってしまうのです。本来はまったく違う用途に使うものですが、いろいろ試してみた結果、元結にたどり着きました」
──男性陣の若返りも大変でしたか?
「リャンズー役のリャン・ジンドンは実際には40代後半です。ですから、27歳に見せてくれって言われた時には、27?と聞き返したい気持ちでした(笑)。まずは髪をしっかり刈り上げて、90年代後半の雰囲気に落とし込みました。当然、目の下のしわも深かったので、毎晩パックをしてもらいました。撮影がある日は朝もパックをして、シミそばかすを消して肌にツヤが出るように心がけました」

──やはり年齢肌にはパックが重要ですか?
「特に中国は、乾燥が激しく湿度が低いですから、しっかり保湿してあげることが重要でした。気温もマイナス10度くらい、寒い日はマイナス20度にもなるので、寒さにも耐えられるよう、保湿をしてツヤのある肌を作ることを心がけましたね。中国のような気候だと、本来はオイルを使った方がいいのかもしれませんが、撮影でオイルを使うと照明に反応して光ってしまうので、オイルは使わずに仕上げていきました」
◆実は俳優の演技を大きく左右する「眉毛」という存在
──髪型やメイクには、それぞれの国における時代ごとのカルチャーが反映されていると思いますが、今回の舞台は中国。どんな風にイメージを作っていったのですか?
「相当の数の写真を見ました。それからテストメイクをして監督に実際に観てもらいましたが、思った以上に監督のイメージに近く、安心しました」
──2014年のチャオ・タオさんはすごくエレガントでしたね!
「2014年パートの頭に当たるパーティシーンでは、赤い服を着た素敵な女性として立ち上げ、父親が亡くなったシーンのあとはすべてスッピン(素顔)でいきました。99年との差を作るためでもあるのですが、2014年になった瞬間に一度綺麗なチャオ・タオを見せ、そのあとにドンと落とすことで時代感を一気に変えようと思ったんです。ただ、息子と一緒にいるシーンでは、ほんの少しだけ肌のコントロールをかけています。子どもと一緒にいる時間は少し優しい顔に見せてあげたいですから。そんなことをちょっとずつヘアメイクで仕掛けていたりします」

──スッピンとはいえ、眉毛だけは描かれていたりするんですか?
「2014年に関しては、眉毛も描いていません。実は眉毛というのは、綺麗に整っていると感情移入しにくいものなんです。人形に近づきますからね。眉毛がぼさぼさの女の子が泣いている方が一緒に泣ける。つまり、人間臭いんですよ。日本でも実力派の女優さんたちに整えてない自然な眉毛の人が多いのは、そういう理由もあるんです」
◆脚本を読んで、ジャ・ジャンクーの本気を感じた!
──現場には62日間もいらっしゃったそうですね。
「撮影期間を通じて現場に入る場合、1〜2ヶ月というのは普通のことですが、今回の場合は最初のオファーの時点では、チャオ・タオを若返らせる1999年のパートのみで、7〜10日くらいの予定でした。でも蓋を開けてみたら、1部(99年)が終わったら2部(2014年)でも呼ばれ、3部(2025年)でも......と。どんどん増えて、最終的には62日間になっていました。こういうことは本当に稀ですし、ジャ・ジャンクーのオファーだったから受けたのだと思います」

──それほど、橋本さんにとってジャ・ジャンクー監督は大きな存在ということでしょうか?
「脚本が面白かったというのが絶対的な理由です。もし脚本が面白くなければ、たとえジャ・ジャンクーであっても受けなかったと思います。なおかつ今回は、主演がチャオ・タオで、その役名がタオです。ジャ・ジャンクーがどれほどの本気でこの作品に臨んでいるのかも、本(脚本)を読めばわかりました。だからこそ、自分にできることがあればやってみたい、と思えました。さらに、3部の2025年のパートにはシルヴィア・チャンが入るということで、自分としてもやってみたいという思いがありました」

──かなり異例なお仕事だったんですね。
「ほかの作品の仕事が並行でいくつも入っている中でしたが、ジャ・ジャンクーからオファーがきていることを伝えると、喜んで行かせてくださった方も多く、だからこそ安心して日本を離れ、この作品に思い切って参加することができました。ただやはり、そこまでして行ったのは、本当に本が素晴らしかった、そのことに尽きます。ひょっとしたら本当に、ものすごい作品になるかもしれない! そう思わせてくれるものでした」
──どんなところが、橋本さんの心を捉えたんですか?
「全体的な構成が、今までの脚本とは大きく違っていました。描写についてもそうですし、歴史的背景もしっかりと入っていて、紛れもなく"中国の作品である"ということがはっきりわかる作品になっている。日本の作品には、"これは日本の作品である"とわかるような歴史的背景の描き込みが、なかなかなかったりしますよね。その要因として大きいのが、ジャ・ジャンクーが国際人であることだと思っています。だからこそ、ジャ・ジャンクーならではの視点で、中国というものを客観的に捉えている。彼が見ているのは、エンターテイメントと呼ばれるものだけでなく、経済界であったり政治であったり、いろんなものが取り巻く中での中国と世界。さらに、今回の『山河ノスタルジア』の場合は、2025年という未来に対しても、絶妙なメッセージを観客に投げかけている。とにかく、問題視していることや、着眼点がすごいです。みんなが何となく感じていることを、映画の中でしっかりと、世界に対して問題提起しているんですよ」

◆橋本さんが、映画のヘアメイクにこだわる理由
──ところで、映画のお仕事は年間何本くらいされるんですか?
「だいたい10本くらい。多い時で20本くらいです。長編・短編は気にせずやっています。逆に短編の方がいろんなことにトライしやすかったりもします」
──映画のヘアメイクという道を歩まれている理由は?
「自分はもともとCMなど広告などのヘアメイクを多く手掛けていますが、美容師やパリコレもやっています。そんな中、年齢が上がるにつれて、昔から好きだったアイデンティティや社会問題、事件や歴史的背景といったものにより興味惹かれていることが、映画のヘアメイクの仕事が増えている理由でもあります。アイデンティティや社会問題といったものに対する自分の考えを、映画という形のパッケージで作品として残していけることは、とても楽しく魅力的だと感じています」
──これまで携わった作品の中で、特に思い出深い作品は?
「今回の『山河ノスタルジア』はもちろん思い出深い作品になりましたが、アッバス・キアロスタミの『ライク・サムワン・イン・ラブ』(2012)も一つのターニングポイントでした。キアロスタミと一緒にカンヌに行き、キアロスタミという監督がカンヌでどんな風に扱われているのかを目の当たりにしたこと。インタビューはもちろん、上映が終わったあとに延々と続くスタンディングオベーション、そしてパーティ会場にも錚々たる面々が来られました。一緒に仕事をしてわかったことですが、キアロスタミという人は、スタッフまで騙すようなことをしてまでも、作品を仕上げていくんです。『ライク・サムワン・イン・ラブ』の主人公のおじいちゃんは、元々キルケゴールの研究者という設定で、キルケゴールの本を借りてきたり、ノートを作ったり、セリフにもキルケゴールの引用がたくさん入っていました。でも、できあがった映画からは、キルケゴールに関する部分がすべてカットされていました。なぜかというと、キアロスタミは、映画の中にキルケゴールのエッセンスだけを残したかったのではないかと思うのです。キルケゴールが出れば引用したんだねと言われますが、キルケゴールが一切写らなければそれは完全にキアロスタミの映画です。しかも8割がリテイクですからね。本番さながらのテストシュートをずっと重ねていたと思います。それは本当に、キアロスタミの凄さですよね。スタッフを全員騙すようなことをして出来上がった画というのは、本当に凄く意味を持ったものになっていました。世界で闘っている監督の中には、こんな監督もいるということを知ることができたのは、すごく刺激的でしたね。そういった多様な監督たち、さまざまな役者たち、多くのスタッフと仕事ができることは、ヘアメイクという職業の面白さですね」
◆ル・シネマ通いをしていた頃
──橋本さんにとって、かつて衝撃を受けて今につながっているような作品はありますか?
「自分は、Bunakamuraル・シネマが好きでかなり通っていた時期があります。チェン・カイコーの『さらば、わが愛/覇王別姫』がタイムリーの頃です。フランス映画、パトリス・ルコント作品もよく観ていました。考えさせてくれる映画、観たあとに2時間しゃべれる映画が好きでした。今回の『山河ノスタルジア』もル・シネマで上映されますが、自分が作った作品がル・シネマでかかるというのは、ものすごく光栄で嬉しいことだったりします」
◆実写だから面白い!を追求した『ヒロイン失格』。未見の人もマストで観るべき!
──ご自身が携わった映画の中で、メイクに注目すべきおすすめ作品があれば教えてください。
「李相日監督の『許されざる者』では、北海道の大雪山の上で生きてきた人たちの肌を、高山焼けした赤茶けた色にしています。時代背景がしっかり作られた、リアリティを持った映画は、僕自身とても好きです」
──『ヒロイン失格』も橋本さんがヘアメイクを担当されていますよね。
「あれは44種類ヘアメイクチェンジをかけたんですよ。1つのヘアメイクが長く使われるシーンもあるので、実質2分に1回ヘアチェンジしているような。少女漫画原作には初めて挑戦しましたが、漫画だから面白いことではなく、実写だから面白いことに落とさなければいけない。そのためには、悩んでる時でも女の子はかわいくなければいけないんですよ。本当は女の子って、悩んでいる時はもっとボロボロでしょう? でも映画では、ばっちり作り込んだポニーテールやおだんご頭にして、すごくかわいい悩み方にしました。そこが、評判もとても良かったんです! おじさんたちが作った少女漫画ですけどね」
──すみません! ティーン向けだと思って侮っていました!
「登校する時には三つ編みだったのが、授業中は片側だけ結んであり、ご飯を食べる時は上に編み込みが入っていて、帰る時にはポニーテールに変わってる......みたいな。1日で7種類ぐらい変えています。でも実際、今の女子高生で器用な子だったら、こういう子いるよね!って思うんです」
──かなり面白そうです。観ずに死んだら損ですね。
「ちなみに、来年2月に公開の『彼らが本気で編むときは、』で生田斗真さんをトランスジェンダーとして、女性にしたのも自分です。いろんな作品をやっていますが、自分はアイデンティティがある作品が好きで、今、200作品ぐらいやってきていますが、それらの作品を集めてライブラリにできたら面白いなと思っています。過去の作品と向き合って、自分が何年に、どういうテーマで何を考えたかを振り返っていくことも、ヘアメイクとして、自分として必要なことだと思っています」
(取材・文/根本美保子)
***

『山河ノスタルジア』
4月23日(土)よりBunkamuraル・シネマほか全国順次ロードショー
監督・脚本:ジャ・ジャンクー
出演:チャオ・タオ、チャン・イー、リャン・ジンドン、ドン・ズージェン、シルヴィア・チャン ほか
配給:ビターズ・エンド
原題:山河故人
英題:Mountains May Depart
2015/中国=日本=フランス/125分
公式サイト:http://www.bitters.co.jp/sanga/
(c)Bandai Visual, Bitters End, Office Kitano