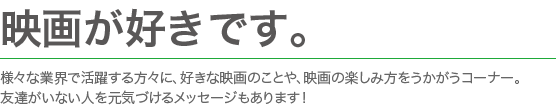視覚障碍者に向けて、映画の登場人物の動作や情景を伝える音声ガイド。前作『あん』で音声ガイドの製作をする過程で、その表現方法に感銘を受けた河瀨直美監督がつくり上げた最新作『光』。何度となく撮り続けた河瀨監督の故郷でもある奈良を舞台に、視力を失いつつある元写真家と、音声ガイドの制作者の邂逅によって紡がれる物語は、見終えた後、どうしようもなく心の震えが止まらない。カンヌでカメラ・ドール賞を受賞した、商業映画デビュー作『萌の朱雀』(1997年)から20年。カンヌでグランプリを獲得した『殯の森』(2007年)から10年。自身にとっての節目の年に発表した『光』が、第70回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に選出(グランプリは惜しくも逃すも、エキュメニカル賞を受賞!)された河瀨監督と、主演の永瀬正敏さんに、映画のこと、聞いてきました!(※インタビューは4月14日に行ったものです)
◆◆◆
──『あん』に続き2度目のタッグで、カンヌ国際映画祭の70周年という記念の年に、コンペティション部門に選出。お気持ちをお聞かせください。
河瀨監督「前作『あん』(2015)でも、"ある視点"部門のオープニングでカンヌに行かせていただきましたが、そのときに、次は公式のコンペで永瀬くんと一緒に行きたいと思っていました。それが現実のお知らせとして届き、まずいちばんに彼に電話をしました。あの場所に行けることは、事実として、映画にとって最高のお披露目だと思っています。なにもわからなかった『萌の朱雀』から20年の節目で、こうして選んでいただけるのは本当に嬉しいです」
永瀬さん「僕も監督と同じ気持ちです。カンヌはそこから世界に広がっていく、とてつもないきっかけになる映画祭でもあります。世界中の人に『光』を観ていただけるのは、本当にありがたいです。でも、今だから言いますが、監督はものすごいプレッシャーだったと思うんです。みんなが"カンヌ=河瀨さん"と言うけれど、そんなに簡単なものじゃないんですよ。だから、一生懸命、雅哉として生きて、少しでも監督の思いに答えられればとやってきた。(選出を知らせる)電話をくれたとき、監督はずるずるに泣いていましたが、僕も電話を切ったあと、ばーばー泣きました。今回は特に70周年ということで、世界中のすごい監督が素晴らしい作品で応募されたことでしょう。そのなかで日本代表、アジアでも数少ない作品に選ばれたことは、やっぱりすごい。監督には、本当に感謝しかありません」
──毎回、すべてをかけて映画づくりをされていると思いますが、やはり今回は特に強い思い入れがあったのでしょうか?
河瀨監督「前作の『あん』は興行的には私の作品ではいちばん成功しました。そういう意味での期待が高まっているところで、あえてやっぱり、オリジナルの脚本で勝負したいと思ったんです。周囲からいろんな企画をいただきましたが、何か自分の気持ちが乗っていきませんでした。そんななかで出合った"映画の音声ガイド"という題材。脚本は永瀬くんで当て書きをして、雅哉というその人が、そこで生きているように書いていったもの。そしてまた、映画というものをテーマに作ることは、大きな挑戦でもありました」
──弱視が進行し失明の危機にあるカメラマン・雅哉を主人公に、視覚障碍、認知症、劇中映画......さまざまな要素が相互につながり合う完璧なストーリー。脚本は1年以上かけて練り上げたそうですが、かなり苦労されたのでしょうか?
河瀨監督「脚本もそうですが、編集のほうが大変でした。60時間分のフィルムの中から、とりあえずOKカットだけをつないだ時点で、4時間くらい。そこから熟考して削ってもまだ3時間。これを半分にしなきゃいけないのかというところで、むしろ自分のなかで本当に大事だと思うものを削っていくことにしました。物語って、血管の中に"ストーリー=感情"を流していくようなものなんです。でもそこに大きな存在があると、なかなか血が流れていかない。別の人が編集したら、まったく違うストーリーになったのではないかと思うほど、大きなシーンがたくさんあるんですが、それを残してしまうと、なにかが絶対に滞って、無駄なものが見えてしまう。判断が鈍るところなんですよね。現場での思いと、両方を経験してしまっているので。削ることで感情を流していく。その取捨選択にとても時間がかかりました」

──実際にできあがった作品をご覧になって、いかがでしたか?
永瀬「河瀨組の作品は、客観的に観られないんです。初号というんですが、最初に完成した作品を観たときは、見終わったあとそのまま(撮影地の)奈良に行きたくなってしまいました。監督がよくおっしゃるんですが、その役を生きる、役を積んでいくことで、生きていたので」
──役を生きる。それは、ご自身と役の境目がなくなってしまうということなのでしょうか?
永瀬「撮影中は、映画のなかの雅哉の家に実際に住んで、雅哉として暮らしました。視覚障碍者の役だったので、弱視体験キットというものを購入して、お風呂に入るときと寝るとき以外はずっとつけている生活。そうして、その世界にずっといるうちに、わからなくなっちゃうんですね。その感情が、雅哉の気持ちなのか、永瀬の気持ちなのか。でもそれって、役者としてそれこそ基本中の基本なんです。原点ですよね。人の人生を、代わりに生きているわけですから。河瀨組では、その作業をものすごく真摯にやらせてもらえる。そういう場をつくってもらえることは、演者としてはすごくありがたいことです。ただ、そういう現場づくりって、決して簡単なことではないんです。大人の事情とか、いろんな槍を受け止めながら、監督が防波堤となって僕たちを守ってくれている。それは、『あん』のときも含め、ひしひしと感じていることです。頭から順番に撮っていくのもそう。たとえばシーン1と67はスタジオだから1日で撮っちゃおうというのが普通の映画なんだけど、そうではなく、役で過ごす時間を大事にしてくれるんです」

──撮影現場での河瀨監督はどんなですか?
永瀬「役にすごく寄り添っていただける監督です。さっきフィルムが60時間分、OKテイクが4時間とおっしゃってましたが、同じシーンを何度も何度もやって、それが積み重なった60時間ではなく、そのシーンの前後の雅哉として生きた時間を含めた60時間から監督が選ばれたものなんです。河瀨組では"用意、スタート"のかけ声は一度もありません。雅哉が部屋から現場に行くまで、カメラがまわっていなくても、監督が一緒に歩いていなくても、その存在は常にそばにある。いつも寄り添ってもらっているんです。そんな現場、なかなかないですよ」
──現場では細かな指示や演出などをされないそうですね。
河瀨監督「自分のイメージ、小さな枠の中にその人の表現は収まりきらないですから。もちろん、航海図としての脚本はありますし、雅哉はこういう人だというキャラクター設定はしています。でも、永瀬くんが雅哉として生きて、時間をそこで積んでいることに勝るものはない。だから、そこで表現してもらっていることに対して、こうしてください、とは絶対に言わないですね。信じているから。そしてそれが真実だから」
──では、おふたりがこれまでお仕事を続けてこられたなかで、仕事において大事にしていることはなんですか?
河瀨監督「自分を誰かと比べることはないし、自分の中で真っ当だと思うことをやっています。それは映画づくりでもそうなんだけど、それだけでなく、真っ当に生きるということ自体が大事なわけです。私の場合は、映画監督という役割をもらった生だと思うんだけど、そのために真っ当な人生を崩してはいけない。映画はもう一つの人生だから、人生ほどに魂を注ぐんだけど、それが本末転倒になってはいけないと思うんです。そして、映画を一緒につくっていく同志としての俳優は、自分と同じ眼差しを持っていなければ、一緒にはできないと思うんです。たとえば、言葉で言うととても簡単だけれど、"人にやさしく"だったりね。今回は、撮影のなかで視覚障碍者の方に役者のようにそこにいてもらいましたが、その方々のエッセンスをもらいながらリアリティを出していくわけだから、その存在はとても大切にしなければならない。でも、現場でのセッションって、すごく緊迫していると思うんです。自分は俳優だから俳優ができるのであって、素人には務まらないよって。そういうタイプの人もきっといると思うんです。もっとリハーサルを重ねて、自分がやりやすいように、光もこっちから当ててって。でも、私はそういうふうにはつくっていない。だから、そのセッションを引き受けてくれる俳優さんでないと、一緒にはつくれないんです。同じような眼差しのなかで、真ん中に映画を置いて、ちゃんとそこにアクセスしていけるような人たちとやることが、大事だと思っています」
永瀬さん「全部言われてしまいましたね。本当に、信じることを大事にしたいと思っています。映画というものを信じているし、人というものを信じてる。そこで迷子になっちゃうと、たぶんものはつくれなくなるかなと思うんです」

──映画のなかで、"映画とは誰かの人生とつながるもの"というセリフがありますが、おふたりが映画を通じてつながった人生のなかで、心地よかったものは?
永瀬さん「出るほうでも、観るほうでもいっぱいあります。でも僕としては、この『光』という世界、雅哉の人生を、映画を観た人がまた別の物語として紡いでくれたらいいな、という希望があるんです。だから『光』です!」
河瀨監督「『みつばちのささやき』のアナちゃんが、お姉ちゃんとこしょこしょ話をするところとか。普段だったら見えない世界を見せてくれる映画ですね。瞳が本当にきらきらしていて、そこに嘘がない。そういう人たちを観ていると、ほんとに私もそこにいて、同じ空気を吸っているような気になります」
──最後に、友達がいない人におすすめの映画を教えてください。
永瀬さん「映画館という空間で、まったく知らない他人と同じ時間を過ごし、一緒の作品を観てください。全然知らない人と同じものを観て、同じ瞬間に笑ったり、人は笑ってないのに自分だけ笑ったり泣いたり。そういう体験が、映画の醍醐味でもあるからね」
河瀨監督「『あん』を観て!」
河瀨監督、永瀬さん、ありがとうございました!
写真/平尾健太郎 取材・文/根本美保子
ヘアメイク/<河瀨直美>桑本勝彦、<永瀬正敏>勇見勝彦(THYMON Inc.)
スタイリスト/<永瀬正敏>渡辺康裕 (W)
***

『光』
新宿バルト9、丸ノ内TOEIほか全国公開中!
監督・脚本:河瀨直美
出演:永瀬正敏、水崎綾女、藤竜也 ほか
配給:キノフィルムズ/木下グループ
2017/日本映画/102分
公式サイト:http://hikari-movie.com
©2017 "RADIANCE" FILM PARTONERS/KINOSHITA、COMME DES CINEMAS、KUMIE