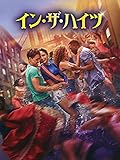大崎梢さんが語る、全社会人胸アツの『クローバー・レイン』

- 『クローバー・レイン (一般書)』
- 大崎梢
- ポプラ社
- 1,620円(税込)

- >> Amazon.co.jp
- >> HonyaClub.com
- >> エルパカBOOKS
2006年に『配達赤ずきん』でデビューして以来、書店や出版業界を題材にした作品を書き続けてきた大崎梢さん。新作『クローバー・レイン』で描いたのは、作家の手によって書き上げられた一遍の小説が世の中に出るまでのお話。熱い思いを胸に孤軍奮闘する若手文芸編集者の姿は、私たちに仕事の素晴らしさを見つめ直すきっかけを与えてくれます。
主人公は、老舗の大手出版社「千石社」で文芸編集者の仕事をする工藤彰彦、29歳。先輩から引き継いだ"出せば売れる"作家を担当する、端から見ればかなりエリートで順風満帆な男。そんな彼が、あるパーティの夜、タクシーで送り届けた作家・家永の自宅で偶然見つけた分厚い原稿の束。『シロツメクサの頃』と題されたそれは、家永曰くまだ"嫁入り先"が決まっていない原稿。夜なべして読みふけったその原稿は、想像以上に素晴らしい傑作でしたが......。
「出版社の営業マンを主人公にした小説(出版社営業・井辻智紀の業務日誌シリーズ)では、中小の出版社を舞台にして"大手はいいよな"なんて悲哀を込めて書きました。今回それとは別の出版社を想定するに当たって、大手を舞台にしたんです。大手の出版社って一見恵まれていて何でもできそうな気がするんですけど、大手だからこその不自由さもあるはずだと思ったんです」
大崎さんが言うところの"大手だからこその不自由さ"。それこそが、家永の原稿のために彰彦が孤軍奮闘せねばならなくなった理由。活躍のピークは十数年前、今では"過去の人"の烙印を押された家永は、彰彦が勤める千石社にはふさわしくない作家だったのです。なぜなら、作家としてのネームバリューと作品のクオリティ、その2つを兼ね備えたものが、老舗の大手出版社「千石社」から出すにふさわしい作品だから。作品の善し悪しだけではどうにもならないという現実を目の当たりにしながらも、彰彦はどうしても自分の手で『シロツメクサの頃』を世の中に届けたかった。編集長に丸無視されても、後輩の営業マンに思い切り頭を下げても、先輩編集者からきつい現実を告げられても。
デビューして丸6年。自身も様々な編集者と密接に付き合ってきた大崎さんが描き出した、黒子として小説を陰で支える編集者のリアルな姿。できあがった作品を読んだリアル編集者たちの反応は「編集の気持ちをどうしてこんなにわかるの?」。リアル編集者をうならせるリアリティ。かなり綿密な取材を重ねたのかと思いきや、
「今回の作品は、特に取材を一切していないんですよ」
と、意外な答え。実はこのお話にリアリティを与えているのは、デビューから6年の間にお付き合いをしてきた編集者たちとの雑談話から得たものなのだそうです。
「文芸書って、恐ろしく長いスパンで形にしていく世界なんです。この本も、こうして単行本になるまでに2年ぐらいかかっていますしね。そういった長い付き合いのなかで、一緒に出かけたり、食事をしたり、打ち合わせをしたりと、編集さんとはいろんな場面で話をする機会があります。作家さんとのやりとりや今の自分の仕事のこと、ときどきはプライバシーに関することも。聞かせてくださる話はとても興味深いものばかりです。それから同業である作家さんたちからは、自分と接点のない編集さんの話を聞く機会もあります」
そんなわけで、大崎さんの作家人生6年分の雑談を凝縮してできあがったのが『クローバー・レイン』。壮大です。
「主人公に特定のモデルはいませんが、現実に編集さんの中には彰彦を超えるぐらいの熱意を持った方が大勢いらっしゃいます。作品を書いたのは作家さんでも、自分の本だという意識がみなさんすごく強い。もちろん中身だけでなくて、帯の言葉も装丁もすごく一生懸命に考えて悩み、吟味する。この本の中にもそういう場面が出てきますから、担当の編集さんは"彰彦には負けられない"と、メラメラしていました(笑)」
「作家=小説を書く人。文芸編集者=小説のためには、何でもする人」。帯にはこんな言葉が書かれていますが、この本を読むと編集者ってまさにそういう人種なのだなと強く感じます。でもその熱意ってどこから湧いてくるんだろう?
「作中に、仕事には私情を挟むべきじゃないっていうやりとりが出てくるんですが、私はやっぱり個人の感情や思い入れが動かす部分が、仕事にもあると思うんです。人の心を動かすものを作ろうとするならなおさら。だから彰彦の場合も、熱意の裏側にすごく個人的で私的な理由や感情があると面白いな、と」
また本作では、編集者の人間的な熱と同時に、作家たちのひとりの人間としての悩みや哀愁も描かれています。
「終盤で、家永と同じように"過去の人"になってしまっている作家が彰彦にこんなことを言うんです。『ぼくがいいものを書いたら、君はきっと取りあってくれるね』。本来は、わざわざ言う必要もない当たり前のことなんですけどね。でも現実には、いい原稿を書いたらいい編集者が取りあって、いい本になるという当たり前のことが、当たり前でもなくなってる。だから作家は作家ですごく不安で、迷走したり焦ることもある。ほかで活躍している人を見て、『うまいことやったな』なんて思ってしまうことだってあると思います。かくいう私自身も、活躍している人を見るとうらやましくてしょうがないんですけどね(苦笑)」
ところで、同じ「千石社」を舞台に、ローティーン向け雑誌に配属された新米男子編集者の成長を描いた『プリティが多すぎる』では、女子中学生から「ローティーン雑誌の編集者になりたいので、とても参考になりました♪」なんてメールをもらったという大崎さん。本作では文芸編集を志す若者から似たようなメールが届きそうですが......!
「思いがけず40代以上のベテラン編集者さんたちからの反響をけっこういただきました。みなさん"若い頃を思い出す"とか"襟を正す気持ちにになった"とか"熱意を持って改めてやらなきゃいけないと思った"とか言ってくださって、すごく嬉しかったですね」
はい、そのベテランの人の気持ち、ベテランでなくてもすごくわかります。『クローバー・レイン』は仕事に対する気持ちを熱く蘇らせてくれる本なのです。まあこのぐらいでいいかなんて甘ったれた気持ちに喝を入れてくれる本なのです。本に携わる仕事をしている人、したい人、本好きな人はもちろん、物を作ったり売ったりしている人は必読です! いや、社会人全員必読でお願いします。
≪プロフィール≫
大崎梢 おおさき・こずえ
作家。東京都生まれ。書店勤務を経て、2006年に書店を舞台にしたミステリ『配達赤ずきん』でデビュー。『サイン会はいかが?』『平台がおまちかね』『背表紙は歌う』など著書多数。8月よりミステリ専門誌『ミステリーズ』にて本屋大賞の一日を、様々な人物の視点で描く新連載を開始! 『成風堂書店事件メモ』シリーズの書店員や『出版社営業・井辻智紀の業務日誌シリーズ』の営業マンも登場予定とのこと。