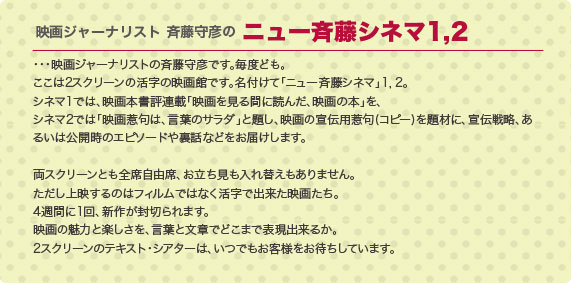【映画惹句は、言葉のサラダ。】第18回 『七人の侍』の広告惹句を公開順に追いかけていくと、その熱気が観客に憑依して行った経緯がよく分かる。
![七人の侍 [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/517weyvjokL._SX400_.jpg)
- 『七人の侍 [Blu-ray]』
- 東宝

- >> Amazon.co.jp
- >> LawsonHMV
●小林一三の写真付きメッセージ広告「その成果を信ずる」
いやあ、またハマってしまった。いくら名作の誉れ高き作品とはいえ、見るたびに新たな発見がある。黒澤明監督作品『七人の侍』。今回は「午前十時の映画祭」の1本として10月8日から上映されたのだが、この映像と音響が凄かった。東京現像所が今回の上映のために大規模な修復を行い、あたかも1954年(昭和29年)の初公開時、いやそれ以上に鮮明な映像とクリアな音響でこの名作を現代に甦らせたのだ。名付けて『七人の侍/4Kデジタルリマスター』。残念ながら上映は終了してしまったが、今回だけで3回この映画を見た筆者は、この映画が公開された時の宣伝惹句はどのようなものだったのかを調べてみたくなった。特に新聞に使われた惹句は、さてこの傑作をどのように表現し、どんな形で集客を目論んだのか。約62年前の朝日新聞縮刷版を開いてみると、飛び込んできたのは「その成果を信ずる」と題した、メッセージ広告だった。
「製作費二億一千万円、使用フィルム十三万呎、出場馬匹三千余頭等々、映画企業の常識では想像に絶する膨大な経費と血のにじむ努力、識者の方々から期待を寄せられた興味無壺の作品内容、この両者が相まって十二分に皆様のご期待に添い得る作品となったことを確信をもって御報告申し上げる次第です。
東宝株式会社取締役社長 小林一三」
東宝の創業者であり、当時社長であった小林一三をしてこう言わしめるほど、『七人の侍』は超大作であり、東宝としてもまさに「映画企業の常識では想像に絶する膨大な経費」を費やした、空前絶後の勝負作であったのだ。
●ハイテンションな筆文字惹句が連日紙面に踊った!
4月26日の公開を前に、広告展開も急ピッチで進められるが、『七人の侍』新聞広告に共通しているのは、そのハイテンションな姿勢だ。惹句の多くに筆文字を使用し、その内容も作品のスケールの大きさ、巨匠黒澤が2年をかけた時代劇大作であることを、強いタッチで紙面に叩きつけている。
「世界に誇る巨匠が西部劇に敢然挑戦
二年の苦闘の末遂に創った凄絶の時代巨編」
「野武士と侍との凄絶の闘い!
これは活劇のための活劇ではない!」
「波状攻撃を敢行する野武士 殲滅か玉砕か
最後の十三騎は暁闇を期し豪雨の部落になだれこんだ
迎撃する侍!」
また一方で、作品内容と登場人物を知らしめるべく、「何故でしょうか? 黒沢明作品の『七人の侍』が全映画界の話題を独占したのは」と、語りかけるような調子で、4つのカテゴリーを設けて『七人の侍』に登場するキャラクターの面白さや撮影時のエピソード等を語る等、単に煽るだけではなく「読ませる広告」も仕掛けている。
上映中の追い広告の惹句は、さらにハイテンションで「予想以上の圧倒的人気 この映画を見ない人は映画を語る資格なし!」と煽りまくる。では興行面ではどうだったかと言えば、『七人の侍』は配給収入2億6823万円をあげたが、同時期公開の松竹「君の名は・第三部」の3億3015万円には後塵を拝した。公開時に指摘されたのは3時間27分という上映時間の長さで、以後『七人の侍』はヴェネツィア映画祭出品のために黒澤自身が編集した2時間44分バージョンが興行に用いられることになるが、1975年秋、21年ぶりにオリジナル版がリバイバル公開される運びとなった。
●淀川長治「黒澤明の映画情熱をここに見た」
名作リバイバル公開時の宣伝惹句とくれば、「あの名作をもう一度」的な、どちらかと言えば大人しいスタイルが定番だが、『七人の侍』の場合は初公開時と同様、ハイテンションな姿勢で観客を煽る。1975年9月20日、テアトル東京でリバイバル公開された際の惹句がこれだ。
「全世界を熱狂させた不滅の名作が、
絶賛の声と共にいま帰って来る」
「全世界を沸かせたあの"七人"が
明20日〈土曜〉10:20 AM 地響きをあげて帰って来る!」
この時のリバイバルでは、著名人のコメントの類いも新聞広告に掲載されたが、このコメントには熱のこもったものが多く、発言者の強い思い入れには驚いてしまう。著名人コメントは、たっぷり26人分。井上ひさし、岡田茂(三越社長)、荒正人、赤塚不二夫、秦豊、石森章太郎、山藤章二、淀川長治、品田雄吉、色川大吉、水木しげる、秋竜山等々・・まさに各界を代表する著名人が「この一本で総理大臣級の待遇を」「これが本当の映画だと感じ、ボクも監督に・・」「黒澤明の映画情熱をここに見た」等、最大級の賛辞を『七人の侍』に献上。その熱きコメントの数々は、惹句が放つ訴求力を上回っていた。
『七人の侍』の新聞広告で面白いのは、初公開時の広告に見るテンションの高さが、リバイバルを重ねる度に沈静化していくのに比例して、有名人やオピニオン・リーダーの発するコメントは逆にヒートアップしていく様が見られることである。
●「今観ないで、いつ観るつもりだ」
1991年のリバイバル時の広告では、「見るべし!」とのアイキャッチを強調し多用されているが、惹句そのものは「黒澤明44歳のスゴサがここにある。」「全世界を熱狂させた痛快娯楽アクション巨篇。」と、陳腐極まる出来。そんなチープなコピーワークに対して、オピニオン・リーダーたちのコメントは、75年の時以上に熱い熱い。
「今観ないで、いつ観るつもりだ」
「理想の男に出逢えた−
『男に惚れる喜び・幸せ』をもたらしてくれる−
素敵な七人の侍たち。」
「こんなにおなかの底から熱くなるような映画は
観たことがない。」
そしてこのコメント惹句の極めつけは、コラムニスト・中野翠さんによる、涙が出るほど素晴らしい、このフレーズ。
「最上の娯楽が芸術的であり、
最良の芸術が娯楽的であるというのはこういうことだ。
急げ、映画館へ!」
初公開時、東宝が社運を賭けた大作を成功させるべく、小林一三のメッセージを皮切りに連日新聞紙面を飾った、ハイテンションで熱い広告たち。そしてそれは、『七人の侍』を観た観客たちに引き継がれ、彼らの熱き思いがリバイバル時の広告に反映されていく。この映画の持つ熱さ、そして黒澤明監督をはじめとするスタッフ、キャストの持つ熱意がスクリーンを通して、見る者に憑依していったようなこの流れは、今見てもエキサイティングかつ感動的でさえある。
今回の「午前十時の映画祭」では、オリジナル宣材は作られなかったが、初めて『七人の侍』に接した若い観客たちが驚き、興奮したことを、現在の彼ら自身の言葉で語っている様子はSNSでもよく目にした。
こうした言葉の伝播を経て、名作はまた新たな生命力を獲得するのである。
(文/斉藤守彦)