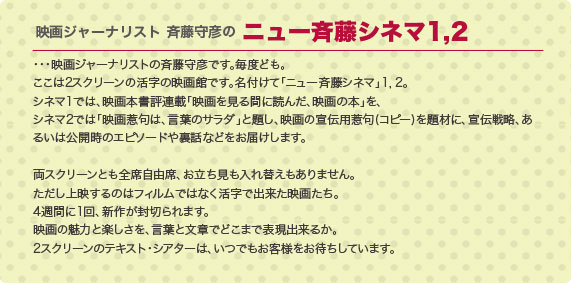【映画を待つ間に読んだ、映画の本】第34回『いつかギラギラする日/角川春樹の映画革命』〜角川春樹だから言えること。角川春樹にだけは言って欲しくなかったこと。

- 『いつかギラギラする日 角川春樹の映画革命』
- 角川春樹、清水節
- 角川春樹事務所
- 1,620円(税込)

- >> Amazon.co.jp
- >> HonyaClub.com
- >> LawsonHMV
●あの熱狂は、まだはっきりと覚えている。
角川春樹という人の存在は、巨大である。筆者が十代の頃、『犬神家の一族』『人間の証明』『野性の証明』といった「角川春樹事務所製作作品」(「角川映画」などと呼称してはいけない)が公開された。1本の新作映画が公開される。ただそれだけのことなのに、まるで地球が角川春樹を中心に回っているかのような連日の大騒ぎを、当時僕は観客という立場で経験した。その時の様子は、あの熱狂は、今でもはっきりと覚えている。ずっと「映画は監督のもの」と言われてきた我が国映画界において、プロデューサーとはいかなる仕事をする職種か、作品のどの部分をどうコントロールする権限を有しているのか、あるいは宣伝面において、どのような働きをするのか。それらすべてについて身をもって教えてくれたのが、角川春樹であった。
あれから40年近くが経過した。映画について文章を書くことを生業としている筆者も、何度か角川春樹へのインタビューを考えた。だがその都度「現在の彼は、過去の映画について発言をしたくないようだ」との噂が聞こえてきて、取材を断念したわけだが、今回同業者というか、類似業者である清水節がその難関を突破し、ロングインタビューを実行した。清水は筆者と同世代である。あの熱狂をリアルタイムで体験した人物でなければ、角川春樹にインタビューする資格なしと常々考えていた筆者としても、納得の人選である。
●明らかにされる、多くの事実と真実。
本書は雑誌に連載されたものを再構成し、新章を追加したものだが、役割分担ははっきりしている。語る角川春樹、聞く清水節。ただし清水の繰り出す質問は、これまで「角川春樹と仕事をした」と語る、当時の関係者の発言や情報を「確認」し、当事者としての見解を引き出すことが中心になっている。このあたりはいささかもったいない。なぜなら清水の文章が、とてもシャープで巧みだからだ。出版社の現役社長である角川春樹をして「そのうまさに舌を巻いた」と言わしめるほどで、例えば春樹への質問以前に、その時代がどういう時代であったか。映画界の状況などを少ない文字数で器用に解説した上で、質問に入る。それ故我々の世代以外の人も、すんなりと内容に入って行くことが出来る。単純なことだが、これはインタビューを文章化して行く上で、大切なことだ。
そうした清水による、的を射るような質問によって、本書ではこれまで明らかにされていなかった事実が、春樹自らの発言から明らかになる場面も見受けられる。例えば春樹が角川書店で大ヒットさせた書籍『ラブ・ストーリィ/ある愛の詩』の翻訳者が「板倉章」となっているが、これは春樹のペンネームだ。清水はさらに、このペンネームの由来を春樹に問う。「『つまらない答えになるから、どうでもいいよ(笑)』と交わす春樹に単刀直入に『女性関係か』と問うと、春樹は『そう』と言って相好を崩した。『結婚した相手ですけどね。同棲時代にお金がないので、翻訳料を生活の足しにしていたわけです』」(本文より)。
こうして新しい事実が次々に掘り起こされて行く。本書の多くが「確認」に費やされていることは事実だが、ひとつひとつが意味のある「確認」であることは確かで、まさに「あの熱狂」を体験した者であれば、当然知りたいと思う多くのことが、本書によって明らかになったことは特筆されよう。
●「有象無象がいるわけですよ」と言うが・・・・。
ただ、角川春樹の回答を読んでいて、時折疑問符がつくこともあった。例えば『犬神家の一族』の興行を予測した雑誌の文章に対して「予想を立てるだけの、興行ゴロみたいな男が書いているんでしょう」と答えている。「興行ゴロ」とは、聞き捨てならない。それが誰なのか、具体的にイメージが出来るからこそ、この回答には憤りと疑問を感じる。だって春樹さん、当時のあなたはこの興行ゴロに多くのことを教わり、彼の関係していた雑誌などのメディアで、威勢の良い発言をラッパよろしく噴き上げていたではないですか。
他にも疑問を感じる部分は少なからず存在する。自身のビジネス的業績は勝者として誇示する一方、実弟・歴彦との確執やハリウッド進出の失敗、映画への多額の投資から角川書店の負債が180億円にまで膨張したことに対しては、従来の報道や他者による記述を「歴史というものは、勝者の視点で語られてしまう」と愚痴ったり。
本書の中でも春樹が繰り返し「有象無象がいるわけですよ」と語っているが、この「有象無象」という言い方にも、ひっかかるものを感じる。おそらくは春樹にとって「自分に金があるから、それを目当てに近寄ってきた連中」と映るのだろうが、往年の春樹映画の大ヒットを支えたのは、そうした「有象無象」な人々の協力ではなかったのか。
本書には「角川春樹だからこそ発言出来ること」と同時に「角川春樹にだけは、こういうことは言って欲しくなかった」という部分が共存している。後者に当たる発言に対して筆者が疑問や憤りを覚えるのは、そうした発言をすることで、かつての春樹自身の仕事ぶりに影を落とすと思うからだ。そしてそれは、「あの熱狂」を経験した、当時の春樹映画の観客たる我々の気持ちにも影を落とすことになりはしないか。とにかく「興行ゴロ」「有象無象」という蔑んだ物言いには、疑問を感じてならない。
だが逆の見方をすれば、本書は角川春樹という人物が、ありのままに、正直に、現在の心境を吐露し、それを清水が抜群の筆致で表現した、嘘偽りのない書籍と言えるだろう。
かつて仰ぎ見た大プロデューサーが、少しだけ身近な存在に感じられるようになった。
(文/斉藤守彦)