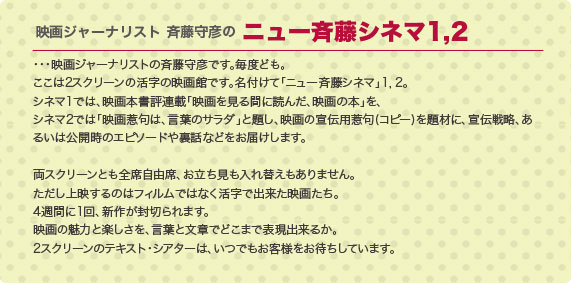【映画を待つ間に読んだ、映画の本】第32回『映画を撮りながら考えたこと』〜テレビの血、映画という筋肉。

- 『映画を撮りながら考えたこと』
- 是枝裕和
- ミシマ社
- 2,592円(税込)

- >> Amazon.co.jp
- >> HonyaClub.com
- >> LawsonHMV
●今や日本映画になくてはならない監督。
是枝裕和監督の存在を、最近の日本映画を語る上で無視出来なくなったのは、いつ頃からだろうか。
1995年12月公開の『幻の光』でデビューして以来、早いもので20年。現在までの間に『誰も知らない』『歩いても 歩いても』『空気人形』『ワンダフルライフ』など、そのクオリティが高く評価され、海外の映画祭にもコンスタントに出品されている。それでもこの監督は「作家性が強くて娯楽性が希薄な、単館ロードショー界隈で有名な人」というのが、僕の認識だった。それが覆ったのが2013年公開の『そして父になる』で、福山雅治、尾野真千子、真木よう子、リリー・フランキーと旬の俳優を揃えたキャスティングにまず目を見張り、このご時世に原作のないオリジナルだという、その気概に圧倒された。しかもこの映画が面白い。それだけではなく、カンヌ国際映画祭での審査員賞受賞が話題となり、これまでの是枝監督作品としては数倍となる、全国309スクリーンで一斉公開され、これが大ヒット。興行収入32億円は凄い。単館ロードショーからスタートした監督が、ここまで全国的な大ヒットに恵まれたのは稀と言えるだろう。以来2015年の『海街diary』、今年5月に公開された『海よりもまだ深く』とフィルモグラフィを重ね、いずれも質的に高い評価を得ているあたりは、映画監督として理想的な人生を歩んでいるように見える。その是枝監督が8年間を費やして書いた(正確には口頭で話したことをライターが文章化して行き、最終的に監督が確認するというプロセス)のが『映画を撮りながら考えたこと』だ。
●彼が社会と向き合う姿勢は、いかにして形成されたか。
最近ではテレビやイベントで、その姿を見る機会が増えた是枝監督の発言を聞いていて感じるのは、「ああ、ちゃんとした大人の人が言うことだ」という安心感だ。映画監督と言えども成人男子が社会的に行っている経済活動であるから、その発言にも年齢に相応しい社会人としての常識や良識は求められる。その点是枝監督は、自身の主張や考えをきちんとした言葉で的確に伝え、所謂「分別をわきまえた」成熟した社会人、言論人たらんという姿勢が感じられるのだ。
『映画を撮りながら考えたこと』には、デビュー作からこれまで監督した映画について、映画化までの経緯や自身の思い、実感などが語られているが、ここでの発言からも「社会ときちんと向き合う」姿勢が感じられる。「映画監督だから」「特殊な職業だから」という言い訳は許されない。本書の帯に「この時代に表現しつづける」と大きく書かれているのは、まさしく表現者として社会と、時代と対峙することから、作品を生み出そうという姿勢を表している。その姿勢を基盤とし、作品を作る。集団作業の中でも自身のポリシーや哲学を見失うことなく、しかもそれを表現として成就させる。作品として観る者に満足感を与え、さらにその作品が商品として利益を生むことまで求められる。1本の映画を世に出すことは、大変な作業というか事業なのである。
●「フィクションは陶酔、ドキュメンタリーは覚醒を引き起こす」
監督自身による1本1本の映画についての発言を読むのも楽しいが、本書では是枝監督がテレビマンユニオン在籍中に撮ったドキュメンタリーにも多くの紙数が割かれている。是枝監督によるドキュメンタリーは、フジテレビ「NONFIX」などでオンエアされたが、本書を読むと1本のドキュメンタリーを作るたびに、「ドキュメンタリーとはどうあるべきか?」を真剣に考え、行動したことがうかがえる。単に劇映画を監督するだけでは、そうしたことは不可能であったに違いない。
是枝監督自身は「フィクションは陶酔を、ドキュメンタリーは覚醒を、観た者のなかで引き起こすのだと考えています」と自らの考えを示している。その上で、「僕はずっと劇映画--フィクションを撮りながらも、正直に言えば陶酔よりは覚醒を目指してきました。でも『花よりもなほ』では、陶酔に、つまり古今亭志ん朝的フィクションに挑戦しようと思ったのです」などと、「陶酔」と「覚醒」の関係性を、制作する映画によってバランスを変える等の挑戦・冒険をしたあたりの発言は面白い。
テレビで発表したドキュメンタリーと、映画館で有料鑑賞される劇映画。ふたつのスタイルの映像に対する姿勢を俯瞰しなくては、是枝裕和という表現者の思考は理解出来ないだろう。「映画を撮りながら考えたこと」は、そうした作家研究に対して、たくさんの気づきを与えてくれる、読み応え充分な書籍と言って良い。
最後にひとつだけ指摘をしておきたい。本書の『海街diary』に触れた部分で、監督が「イメージしたのは、東宝のお正月映画『細雪』です」と発言している。『細雪』が4人の女優を揃えた絢爛豪華な作品であることは分かるが、公開されたのは1983年の5月21日。つまり正月映画ではなく5月番組というのが正解。なぜこんな些細な箇所にまで言及するのかと言えば、筆者が『海街diary』と『細雪』を溺愛しているからなのだが・・・。
(文/斉藤守彦)