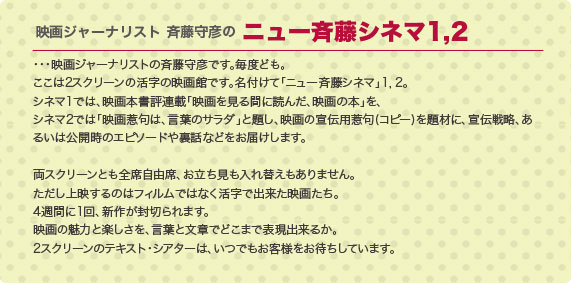【映画惹句は、言葉のサラダ。】 第12回 百花繚乱ヘラルド惹句。
![地獄の黙示録 劇場公開版/特別完全版 [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51rnja4giEL._SX400_.jpg)
- 『地獄の黙示録 劇場公開版/特別完全版 [Blu-ray]』
- NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン

- >> Amazon.co.jp
- >> LawsonHMV
●『エマニエル夫人』の大ヒットが、
ヘラルド映画にもたらしたもの。
ゴールデン・ウィークのちょっと前。4月の中旬に、NHK BSプレミアムの「アナザーストーリーズ 運命の分岐点」という番組で、『エマニエル夫人』が扱われていた。真木よう子の、ほとんどやる気が感じられない棒読みの進行ぶりが印象に残るこの番組では、『エマニエル夫人』がどのように製作され、フランスで大ヒットした後に日本でも1975年の正月映画として公開され、女性層から圧倒的な支持を得て大ヒットしたことを、当時の関係者が語っていた。もちろん日本でこの映画を配給し、巧みな宣伝展開で大ヒットに導いた、日本ヘラルド映画についても触れられている。ヘラルドの宣伝といえばこの人。『エマニエル夫人』公開当時宣伝部長だった原正人さん。今や往年のヘラルド映画のことを知る、数少ない証人だ。ところがこの原さんが番組に登場しないので、何かあったのかと思い携帯電話を鳴らしてみた。既に80歳を超えるご高齢だし。すると御大はすこぶる元気で、あきれたことに「そんな番組が作られたの? え、もうオンエアしたの? 見逃したなあ・・と言うより、番組そのものの存在を知らなかった」と笑う。そこから先は例によっての雑談で、『エマニエル夫人』が当時のヘラルド映画にもたらしたことが、いかに大きかったかを改めて知った。『エマニエル夫人』が大ヒットしたことで、翌年夏とその年末のヘラルド社員へのボーナスは、それぞれ給料1年分が支給された。これだけの大ヒットになったのは、『エマニエル夫人』のことをメディアの人たちが取り上げてくれたお陰と、試写室の椅子をフランス製の豪華なものに代えた(以後、この試写室は「エマニエル試写室」と呼ばれることになった)。そして最も大きかったのは、当時ヘラルドが『エマニエル夫人』で手にした20億余円が、フランシス・フォード・コッポラ監督の『地獄の黙示録』の諸権利獲得に使われたことだった。
●『地獄の黙示録』と『テス』の意外な接点
ヘラルドという社名を耳にすると、『エマニエル夫人』のタイトルを挙げる人と、『地獄の黙示録』と言う人の2種類がいるが、筆者の場合は圧倒的に『地獄の黙示録』だ。『エマニエル夫人』の頃はまだ中学生で、さすがに映画館に行く度胸はなかった。
最近もリバイバル公開された、その『地獄の黙示録』の宣伝惹句は、もはや有名なこの1行。
「劇場が、戦場になる」
『エマニエル夫人』で儲けた金で買い付けた『地獄の黙示録』だが、この場合は映画が完成する以前に、いわば製作出資の形で日本での配給権を得た例で、フランシス・フォード・コッポラ監督はヘラルド映画の当時の社長・古川勝巳の英断に深く感謝したという。そんなコッポラとのやりとりの中で提案されたのが、ロマン・ポランスキー監督の『テス』の買付だ。ポランスキー監督は1977年に未成年への強姦容疑で、アメリカを脱出してヨーロッパで活動していた。ポランスキー監督の才能を高く評価するコッポラは、彼をバックアップすべく、ヘラルドに『テス』の買付を提言。ヘラルド側もこの薦めに応じて『テス』の日本での配給権を獲得する。当時17歳のナスターシャ・キンスキーが卒倒するほど美しい『テス』の宣伝惹句は、文芸タッチでロマンティックな逸品だ。
「テスがはじめて愛を知った日、
ヒースの丘に悲しみの風が舞った。」
●文芸エロ調映画を女性に売るなら、ここにまかせろ
当時のヘラルド映画の宣伝は、とりわけ女性層に作品のイメージを伝えることに長けていた。『エマニエル夫人』のように、エロティックな要素をそこはかとなく漂わせるものの、それによって女性層の興味を惹きつける。決してエロスだけを前面に出さない。また『テス』の場合は、文芸的要素と大作感のある恋愛映画というルックスを堂々と押し出してみせた。どちらもターゲットとした女性層の獲得に成功した例だ。
もう1本、1985年に日本公開された『ナインハーフ』の場合もまた、ちょっとエロいラブ・ストーリー的な雰囲気を、巧みに漂わせて、これまた女性客を多数獲得してヒットした。
「輝き時に出逢った男と女に 愛のルールはいらない。」
『ナインハーフ』には、確か「女は下着の中に、天使と悪魔を飼っている」という惹句があったはずなんだけど、この惹句がどこに使われたのか発見出来ない。「輝き時に・・」よりエロ濃度が濃いけれど、リアリティのある惹句だと思うなあ。
●「生きろ」か「熱く死ね」か、どっちやねん?
もちろんヘラルド映画は、女性向け映画を専門にした配給会社ではなく、アクション映画やSF映画も手がけていた。宣伝的に見て面白かったのは、1987年に公開された、香港ノワール(という言葉も、ヘラルドが発信源であろう)『男たちの挽歌』で使われた宣伝惹句だ。
「生きろ。死に急ぐな。」
チラシやポスターといった映画の宣伝材料は、公開数ヶ月前に制作・配布されるティーザーと呼ばれるものと、公開直前に作られるものの2種類があるのだが、上記の惹句が使われたのはティーザーの段階。黒をベースにしたデザインで、主演のチョゥ・ユンファ、レスリー・チャンらの姿が格好良くレイアウトされていて、新しいアクション映画の出現を予感させた。
ところが公開を数週間前に控えた時、映画の宣伝方針が変わったのか何なのか分からないが、新しいポスター、チラシが配布され、そこにはこんな惹句が使われていた。
「恥じて生きるより、熱く死ね!」
ティーザーでは「生きろ」と言っていたのに、今度は「熱く死ね」とは。「いったいどっちにすればいいんだよ!?」と、当時この映画を手がけていたヘラルドの宣伝マンに詰め寄るも、笑顔でスルーされた記憶がある。映画は面白かったけどね。
数多くのヒット作を輩出した日本ヘラルド映画は、2005年に角川ホールディングスに買収され、角川グループの映像d事業の中核となる。現在、ヘラルドの名を冠した配給会社は存在しないが、ヘラルドのDNAを受け継ぐ者たちは、今も映画業界で活躍を続けている。
(文/斉藤守彦)